「誕生日おめでとう。何歳になったの?」
「わ〜ありがとうございます。29歳になりました……」
「えっ、もうそんな歳になるっけ?(笑) やばいね(笑)」
年明けめでたい空気が残る中で、不意に目の前で起こった会話だった。
23歳を過ぎた頃から、周りは優しく危機感を摺り込んできて、そして当事者の私たちはしきりに確かめ合うようになる。「そろそろやばいかな?」なんて。
変わらないままいるなど、許されないみたいだ。
『あの頃。』のあらすじ
マネージャーやプロデューサー、ベーシストとして「神聖かまってちゃん」などのバンドや音楽ユニットにかかわってきた劔樹人の自伝的コミックエッセイ「あの頃。男子かしまし物語」を、松坂桃李主演で実写映画化。大学院受験に失敗し、彼女もお金もなくどん底の生活を送る青年・劔。松浦亜弥のミュージックビデオを見て「ハロー!プロジェクト」のアイドルに夢中になった彼は、イベントで知り合ったコズミンら個性的な仲間たちとともに、くだらなくも愛おしい青春の日々を謳歌する。しかし時は流れ、仲間たちはアイドルよりも大切なものを見つけて離れ離れになっていくーー。
“ハロヲタ映画” という引力に引かれて
わたしはハロヲタだ。ハロー!プロジェクト*(以下ハロプロ)のアイドルが好きで、推している。映画『あの頃。』は、とあるハロプロ好きの人達を描いた “ハロヲタ映画” だ。この映画は、主演があのイケメン実力派俳優・松坂桃李さん、そして監督には映画好きなら知らない人はいないであろう今泉力哉さん、他キャスト・制作陣もすてきな方々の名前がずらり。かなり豪華。観に行く理由なんて、余るほどあった。なのにわたしは、この映画の紹介文の “ハロヲタ映画” という文字だけで、観に行くことを決めた。それだけで、理由は十二分だったのだ。
念の為、まず伝えておきたい。先述したように、ハロプロが大好きだ。大好きな全てに、迷惑なんて絶対かけたくない。なら尚更言葉にして書くべきではないんじゃない? と、思われるだろう。わたし自身、何度も思った。 “言葉はナイフ” だから。怖くてたまらないです。でもそれでも、わたしの心の叫びを記事にしてみたかったんです。ここから映画『あの頃。』のレビューを下敷きに、日常にも、ハロプロの楽曲にも現れる「女の旬」について考えます。ちょっと長くなっちゃうかもしれないのですが、聞いてくれませんか。
映画『あの頃。』では、人生に迷い、苦しんでいた主人公の劔が松浦亜弥に救われる。主人公と同じくわたしも、ハロプロのアイドル達に、何度も救われてきた。ハロプロのおかげで、強く生きていいんだと知る事ができた。迷った人生も好きになれた。「ここがこうで最高」を話しだすと、すんごい文量になっちゃいそうなのでやめておきます。とにもかくにも、彼女達が最強でいてくれる事に、毎日感謝している。実際推しのインスタグラムやアメーバブログが更新される度に「今日も最強でいてくれてありがたすぎる〜〜〜」と家で1人で拝んでいる。

もしハロプロに出会っていなかったら、わたしはきっと他人に流され続け、簡単な人間になっていたと思う。そんな、わたしの人生の指南書くらいに思っているハロプロが題材の映画だなんて、観るっきゃない! と意気込んで観に行った。
*ハロー!プロジェクトとは、アップフロントプロモーションをはじめとするアップフロントグループ系列の芸能事務所に所属する女性アイドルグループ・女性タレントの総称
記憶の中の青春は、綺麗でしかなかったのに
“「ハロプロ」という4文字が登場しているという理由だけで鑑賞を決めた” というのもあって、正直内容にはあまり期待は寄せていなかった。もちろんバカにしているとかでは全くない。監督、脚本、俳優陣の豪華さから、「おもしろいだろうな」と謎の確信があったのだ。でも、億が一おもしろいと感じられなくっても、ハロプロが出てくる映画が観れただけできっと満足するだろうな、と。
アイドルとアイドルヲタクを題材にしている作品は近年増えてきている。『あの頃。』は、ジャンル的にはコメディということもあったので、 “笑いあり、涙ありのキラキラ青春グラフィティ” だと予想していた。聞こえは悪いが、少々軽めの、そんな映画だと思っていた。映画を重量で表現するのはあまり良くないんだけど。ただなんというかこう、気分的な事で、落ち込んでいる時でも軽やかに楽しめてしまえるものと、身構えて慎重に観に行くものとでの、各々の心持ちの度合いだと思ってほしい。
そういう意味で、この映画は軽やかなものだと予想していた。ところが、鑑賞後のわたしの脳内第一声は「いや、全っ然違うじゃん!」だった。ハロプロ、ハロヲタというポップなパワーワードに隠れて、この映画もまた、指南書のような映画だった。いい意味で、全然ただの “ハロヲタ映画” じゃなかった。
そもそも、“青春” を勘違いしていた。青春って、儚くて美しいもの、楽しいもの、最高の瞬間というようなキラキラしたポジティブなイメージだった。でもこの映画を観て、 “青春” ってたまらなく恥ずかしくて、狂気的で、稚拙だったということを思い出してしまった。
作中ではハロプロの名曲が次々と流れ、ビジュアルコピーでも “青春” を慈しむような言葉が使われている。ストーリーもやはりコメディ調で、思わずクスクスと笑ってしまう場面も度々あった。陽気で軽快だった。だけど、鑑賞中言い表せない怖さや、圧迫感があった。
きっとそれは、気づかないフリをしていた青春時代の未熟さも綿密に描かれていたからだと思う。青春って、最良と最悪が常に隣り合わせでいる、一番不安定な時期だったんだ、と気づかされた。でもむしろ、未完成なもの程不思議と魅力的だ。だからわたし達は、「青春とは最強の時期だ」と簡潔に美化してしまうのだろう。
過去や若さは賛美されがちだ。映画作品にのみならず、現実の社会においても。
「あの頃はよかった」
「若いっていいね〜」
「あの頃のわたし達、最強だったよね、青春だったな〜」
日常の至るところでこんな会話を耳にする。
映画『あの頃。』では、ヲタク仲間と一緒にハロプロに熱中し追いかけまくった青春時代を思い出し、懐かしむシーンが度々ある。思い出す度に、「あの頃は楽しかった」、「あの頃はほんまにおもろかった」と言うのだけど、必ず「今が1番楽しいけれど」という言葉がセットになっている。そして、覚えている限り、 “戻りたい” という表現は一度も発されなかった。個人的に、過去も現在も丸ごと全部賛美する作品は珍しいなと思う。
知らぬ間に買っていた青春
そんな風に “青春” のことをあれやこれやと考えていたら、気づいてしまった。わたし達が、彼女達(ハロプロアイドル)の “青春” を買っていたということに。
今でこそアイドル業界ではメジャーな制度になっているが、ハロプロにも割と昔から「研修生制度」というシステムがある。研修期間といいながらも、入所したてのメンバーは “研修生” というジャンルとして公開されるのだ。そこから偶発的に選抜され、新グループや既存グループでデビューしていく。メンバーを研修生の頃から推し、追っている人がハロヲタには大勢いる。もちろんグループ直結のオーディションもあったりするので、 “メンバー全員研修生だった” というわけでもない。でもどちらにせよ、9〜16歳くらいの少女が切磋琢磨し成長していく姿が見れてしまう。
青春とは、未熟で未完成なものだ。それは精神的にというのもそうだけど、そもそも身体的に未熟な頃に、精神年齢が身体を遥かに追い抜いている事なんて少ない。11歳の女の子が、30歳くらいの精神を持ち合わせているだなんて、フィクションだよ。だから幼い彼女達も、わたし達が乗り越えてきたように、 “青春” という成長過程を進んでいく。
でも、彼女達とわたし達の青春では、決定的に違う所がある。それは、彼女達の青春は少なからず商売道具にされているという点だ。
ハロプロの魅力を聞かれたとき、わたし達は無意識に「成長が見られるというのもいいんだよ〜」と紹介する。大前提として、もちろんそれ以外の魅力もめちゃくちゃある。でも、色々な所で魅力のひとつとしてそこに触れられることが多いのも事実だ。一応記載しておくと、この “成長” とは幼い少女が綺麗な女性に成るという成長のこともきっと含むが、歌やダンス、精神面や個性のスキルの成長も含まれる。彼女達の様々な成長過程のもがきは、ドキュメンタリーとして、わたし達ファンに金銭を介して知らず知らずの内に切り売りされているんじゃないだろうか。
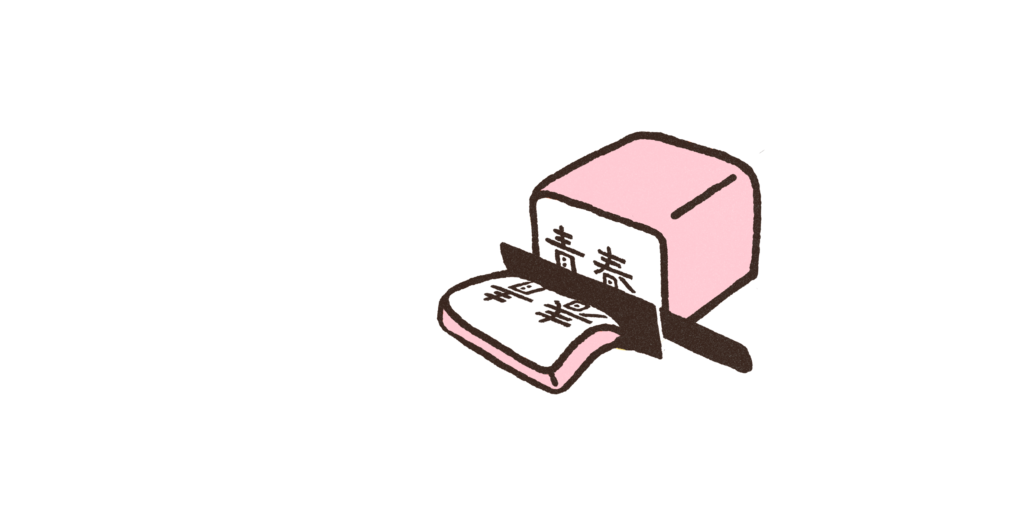
彼女達アイドルは、最強で儚い、どうしたって貴重な時間をも、わたし達に魅せてくれている。貴重な青春の一部を。本来売るべきでないものを、売ってくれているのだ。こんなの奇跡でしかない。
でもそれを、わたし達ファンは奇跡だと認識せずに買ってしまう。そしていつの間にか、自分達も一緒にその青春を駆け抜けている感覚に陥る。一度でも自分の青春を駆け抜けた経験のある人は、青春の恥ずかしい一面をもう知っていて、だからこそ彼女達を正そうとしてしまうことがある。彼女達の人間関係や、ファッション、大人の女性に成ろうとするときの背伸びを、自分の経験と物差しで測り押し付け、制限してしまう。本当はそんなことしていいはずないのに。
例え消費者であろうと、いくらお金を使っていたとしても、彼女達の青春は端から端まで彼女達のもので、わたし達のものにはならない。アイドルは偶像と言われるが、彼女達は実在する人間だ。それを見えていないフリして、
「アイドルの部分しか見えないんだから」
「好きでアイドルをやっているんだから」
「全部ちゃんと、偶像を全うしてくれ」
と強要するのはあまりにも乱暴なんじゃないだろうか。この乱暴を、頭では解っていながら、わたし自身、きっと無意識に何度もやってしまっていた。
“他人と自分は全くの別もの” 。当たり前のことなのに、わたし達は自分でも知らぬ間に彼女達の青春に縋って、買い、重ね、やり直そうとしてしまっているのかもしれない。賛美する過去を取り戻したくて、境界線がぼやけてしまっているのかも、しれない。わたし達ファンの声は、思うよりも大きくて鋭い。彼女達の青春は、芸能活動をしていない人の青春よりも、多くの風に晒されている。だからこそ慎重に、敬意を持って彼女達を応援していけるといいな。
若さというタイムリミットに追われて
ここ最近、わたしも周りも、過去の若さを賛美することに慣れすぎている。23歳を過ぎたあたりから、急に周りから、頼んでもいないのに勝手にカウントダウンされるようになった。
「30歳まではあっという間だよ、“気をつけなね” (笑) 」
「 “もう” 25歳?」
「やばいね」
「早くいい人見つけて “結婚しなくちゃ” 」
「26歳くらいまでなら婚活パーティで超チヤホヤされるよ」
度々こんな声をかけ合うようになる。みんな悪気なんて無い。ごくごく自然に、礼儀作法のように言い合う。「女は30歳まで」という、いつから言い伝えられているのか分からない格言や、「女性の年齢=クリスマスケーキ」という、小洒落た風の例え。わたし達はこんなものにずっと取り憑かれている。最早常識だとさえ言われるくらいに。
「いやいや、年齢なんて関係ないでしょ!」と自分では思っていても、振る舞いやあり方、ライフステージを「年齢」という枠に無神経に当てはめてくる人の方が圧倒的に多い。聞きたくなくても耳に入ってくるもんだから、どんなに嫌でもその思想をぶったぎることができない。無意識下で、根強く、わたし達に訴えかけてくる。突っぱねられない自分がいつも悔しい。
「常にピーク」はジョークなんかじゃない
女性の若さを賛美する人の方がマジョリティな社会で、映画『あの頃。』では過去も現在も丸ごと全部賛美する。だから鑑賞中、全ての過去を繰り返し肯定する登場人物達に違和感を持たずにはいられなかった。でもそんな違和感は、終盤作中で引用された言葉ですんなりどこかへ飛んで行った。
「10代はかわいい、20代は超かわいい、30代は超超かわいい、わたしは常にピークなんです」
元モーニング娘。であり、現役ソロ活動をされている道重さゆみさんの名言だ。
いつかのインタビューでの発言。通称ナルシストキャラの道重さんなので、たぶんちょっぴりコミカルな空気で答えたのかな〜と想像する。でもこんな最高な名言ってない。それに、どれだけコミカルに見えようとも、きっと彼女は本気だし、事実だとも思う。だって本当にずっとかわいいを更新している。
この名言も、映画と同じく、全時代を賛美しているのだ。「そうだ、そうなはずだった」と、呆然とした。未熟だった成長過程も最高で、そのもがきを経たわたし達はもっともっと最高になってるんだぞ! 年齢という数字が重なることに、怯えなくて大丈夫なんだよ、と言われている気がした。
映画『あの頃。』は、忘れていた「青春」の輝きはもちろん、恥ずかしさをも繊細に描き、慈しむ。そして「現在」を丸ごと肯定する力を与えてくれる作品だった。この作品が放つメッセージはとても普遍的なもので、ハロヲタじゃない人の背中をも押すはずだ。物語の面白さもピカイチで、きっと、ハロヲタじゃなくても楽しめる。そういう意味で、この映画はただの “ハロプロ映画” ではない。
ハロヲタじゃなくても楽しめる。それでもきっと、作中に登場するアイドルはハロプロじゃなきゃいけなかった。
過去も現在もいつでも全力で、その時々が常に1番楽しい主人公達。そんな姿は、過去も現在も常に最強を更新していくハロプロアイドル達とどこかリンクしている気がする。こんなの、 “全力のハロプロ映画” じゃんか。
“アラサー” と “やばい” は定番セットメニュー
「わたしは常にピーク」と、堂々と言い切れるって本当にすごい。綿菓子で人にたんこぶを作るくらい難しい。

でも、容姿、スキル、人柄、そして年齢全てを大勢の人に評価される職業・アイドル。伝説で完璧なアイドルと言われる道重さんも、ぐるぐる迷った頃があると思う。アイドルの適齢期や、女性が “かわいく” いられる期間について、きっと。
現に、彼女が27歳でソロデビューした時のコメントで「自分のかわいさのピークは25歳だと思っていた」と言っていた。結局今も彼女はずっとかわいくて、綺麗でかっこいいけれど、この境地に辿り着くまでにかなりの険しい道のりがあったんじゃないだろうか。
というのも、ハロプロにも、所謂女の適齢期が絡む噂がある。“25歳定年説” だ。25歳が近づいたハロプロメンバーがことごとく卒業していくこと、そして25歳を過ぎても現役でそのままのグループで続けているメンバーがいないこと。そんなことから、ファンの間では、 “ハロプロアイドルは25歳が定年とされているらしい” という噂が囁かれているのだ。この噂に対して、「まあ25歳って結婚適齢期だったりするしね」、「女の旬ギリギリまだ間に合うみたいな丁度いい年齢だしね」みたいな意見をちらほら見かけた。
楽曲でも、20代危機感煽りの曲や歌詞がいくつかある。それこそ、25歳定年説の噂が大きくなってきた頃に、元 Juice=Juice の宮崎由香さんの卒業ソング*としてリリースされた「25歳永遠説」(Juice=Juice)。めちゃくちゃざっくりだけど、25歳は終着地点じゃないんだよ、というような歌。パッと見25歳以上の人に向けた応援ソング。だけどやっぱり、結婚適齢期が20代だと暗喩されているような表現がある。冒頭の
地元の子 ママになった
という歌詞だ。この歌詞がわざわざ最初に入ってくるのってやっぱり、社会的に「25歳は結婚しててもおかしくないし、子供がいたっておかしくない」という考えが根付いているからだと思う。何よりも25歳定年説という噂を聞いたときに「結婚適齢期」、「ギリギリ」という言葉が飛び交っていたのが現実だし。“女性の旬=20代まで” という認識風潮は、どうしても、ある。
「16歳の恋なんて」(安倍なつみ, 矢島舞美)という曲でも、26歳が恋愛・結婚に焦っている様が描かれている。
この曲は16歳の「恋でなんにも手につかないよ〜! わたしの世界、どうなっちゃうの〜!?」というなんともかわいらしくアタフタする少女と、26歳の「若い頃の恋愛なんてどうとでもなるよ、いいなあ、この年になったら夢見た恋愛なんてしてられないの」という現実主義な女性との掛け合いになっている。 “結婚” というワードも歌詞の中に使われている。そしてここでもやはり、「26歳=焦らなきゃいけない年齢」として描かれているのだ。16歳の恋も、26歳の恋も、どちらも時間制限なんて無くていいはずなのに。
こういった目に見えない、勝手に押しつけられる制限時間を、仕方のない事だとずっと思っていられればよかったのだが、カウントされる度に、どうしようもない違和感でたまらなくなる。“やばい” って、なにが? なんにも “やばい” 事なんてないじゃない。
*ハロプロは卒業するメンバーがいるとそのメンバーのフューチャーソング、卒業はなむけソングをリリースするのが定番となっている
女の旬、あなたといなくても永遠ですか
わたしは今25歳だ。やはり日々の端々で年齢のこと、恋愛や結婚のことをつつかれ「まだ大丈夫かもしれないけどさ」、「そろそろやばいよ〜」などと何気ない言葉をかけられる。
“一般的” な認識だって、理解してる。「女は若い方が容姿が綺麗=女は30歳まで」。だから “綺麗な内に” 、“ピークの内に” 、“結婚という契約書を交わしておかないと、綺麗じゃなくなったら相手にされなくなるよ” ということだろう。子供を産みたい場合の身体的な体力のこともあるだろうし。わたし自身も気づかず言ってしまっていることもある。実際そうかも? なんて思っちゃったりもする。正直、年齢と共に増えるシミ・シワ・たるみは嫌だし、老いは怖い。抗いきれない本音。
でもどうにも拭いきれない違和感や、モヤモヤが溜まっていくのも事実だ。「容姿で女を決めつけてるって言うなら、30代や40代、それ以降の年齢でも綺麗な人なんていっぱいいるし! 若さと容姿の綺麗さ=女の旬って言うのは違うんじゃない?」と言われるかもしれない。たしかにそう。年齢関係なく綺麗な人はたくさんいる。でも、結局わたし達は、無意識に容姿を年齢という数字でジャッジしてしまっていることが多い。例えばその容姿が綺麗な30代女性に対して、世間は
「すごい綺麗〜!20代に見える!」
「30代 “なのに” 綺麗すぎる」
「30代には見えない、 “まだまだいけるよ” 」
と称賛をしませんか。純粋な褒め言葉として、綺麗さを若さで例える。 “まだまだいける” というのも、 “本来なら旬は過ぎているであろう年齢なのに” という言葉が自然と含まれてくる。女の魅力って、やっぱり容姿や肉体なんだろうか? 女って、なんなんだろう。
疑問や違和感を両手いっぱいに抱えながらも、女であること、女である以上抗いきれない社会の視線に適応するしかないんだと諦めていた。だって、あんなにかっこいいハロプロアイドル達にも、厳しい年齢ジャッジの目は多く向けられているんだし。彼女達は “かわいい女の子” である以外の魅力をたくさん持っている。それでも、“女” であることに重きを置かれる。実際、大好きなハロプロで25歳定年説は囁かれているし、なにより女性の適齢期やピークを示唆する曲もあるんだもの。抗うとか抗わないとかじゃない、“仕方ないんだ” 、と。
でも、勝手に思い込んでいただけだった。ハロプロ曲の中にも、ちゃんと、ささやかな抵抗が込められていた。それに気づいたキッカケは、ふと聴いた、「チクタク 私の旬」(Juice=Juice)という曲だった。
この曲は、「25歳永遠説」(Juice=Juice)の作詞を担当した児玉雨子さんという方の過去作詞曲だ。表面だけ切り取れば、自分に自信がなくて不器用な女の子の、かわいい恋模様がキャッチーに描かれている。でもすぐに、この歌には、残酷な言葉が散りばめられていることに気づく。
私、バカじゃないの
自覚もしてる
賞味期限
チクタク女の旬
「女の旬」と「賞味期限」、このワードが共に使われるのって、ひどく残酷に感じませんか。
もちろん、この歌を否定したいとかじゃ全くない。ただ、なんとなく社会の共通認識になっている結婚適齢期や「女は30歳まで」などの謎格言。そしてこの歌詞を20代前後の女の子たちが歌っているということ。色々な要素を足し算していって単純に考えてみると、この「女の旬」を20代もしくは10代後半などで解釈設定する人が多いんじゃないだろうか。推定16歳〜20代の “私” に “賞味期限”がチクタクと迫ってきている。それが “女の旬” 。「女の旬=16歳〜20代=賞味期限」と考えられる。そして “賞味期限” って、安全においしく食べられる期限のこと。期限を過ぎたら、安全でも、おいしくもなくなる。「女の安全でおいしい期間は若い内だけだぞ! 分かってっか!?」と、胸ぐらを掴んで脅してきているように感じる言葉達なのだ。
とは言ってもこの歌詞の中では一切具体的な年齢は明記されていない。それに、何よりも入りサビだけ、「女の旬」の部分は “私の旬” となっている。
女には旬があるということ、賞味期限があることが描かれていて、使用ワード頻度も “私の旬” より “女の旬” の方が多い。 ならばタイトルは「チクタク 女の旬」でもよかったはず。じゃあなんで、この曲の題名をわざわざ “私の旬”にしているんだろう?

これはあくまでわたしの勝手な解釈で、考察なんだけど、この歌は女性の年齢に対するタイムリミット色や風潮への「アンチテーゼ」なんじゃないか。
この曲の主題は「女の旬」ではなく、「私の旬」なのだ。自分が女であることも、社会の目線も、そしてそれが仕方のないことも、全部全部知っている。 ”自覚もしてる” 。だけど納得はしていないから、ささやかな抵抗として「私の、自分だけの旬」をタイトルにしているのだ。「女の旬ってなんなんだよ! 私はいつだって今が旬だ! 誰がなんと言おうと “私の” 旬は私のものなんだから、私が決めるんだよ!!」と。
そう考えると、「16歳の恋なんて」も「25歳永遠説」も、実はそういったアンチテーゼとして解釈する事ができる。
「16歳の恋なんて」は、一見16歳の少女と26歳の女性、別々の人間2人の掛け合いに取れる。でも実はこれ、26歳の女性1人の内面での葛藤じゃないだろうか? 自分が16歳だった頃の恋への姿勢と、26歳になった自分の恋の焦燥感。そのギャップへの葛藤ソングなんじゃないか?
『25歳永遠説』に関しては、そもそも25歳以降の人への応援ソング。 “一般的” な25歳女性像も描かれているけれど、 “一般的” じゃない、どんな25歳も、魅力的だと伝えてくれている。
「いやいや、深読みしすぎでしょ」、「都合よく思い込みすぎ」って、思われるかもしれない。でもそれでも、年齢の概念に諦めていたわたしにとってこれは “希望” になった。
とはいえ、仮にわたしの解釈通りハロプロ曲にアンチテーゼが含まれていたとしても、やっぱり完璧に拭きれないものはまだまだある。「チクタク 私の旬」の先述の歌詞は、以下のように続く。
女の旬
あなたといれば永遠かも
わたしはこの部分が特に大好きで、とても苦手だ。手放しでわんわん泣いてしまいたくなる。
「あなたといれば永遠」、じゃあ、“あなたといなければ” 彼女の旬は “有限” なの?
最初は「なんて甘酸っぱい歌詞なんだろう、かわいいなあ」と思った。単純に「あなたと永遠に一緒にいたい」という歌詞だと思ったから。でも、じわじわと、歌中の彼女が抱える不安がこの一節に一気にこもっている気がして、息が詰まった。
「今この若くて綺麗な旬の内に永遠を約束して」、「あなたが結婚してくれたら “賞味期限切れ” を防げるのに」、「あなたがどうにかしてくれなくちゃ」という、悲痛な叫びが込められているようで、たまらなくなる。もちろん全然そんなことなくって、前者のようなハッピーなだけの歌詞かもしれない。ただわたしは、漠然と、あなたといなくても永遠でいさせてよ、と思ってしまった。
もしも、自分の大切で大好きな女性達が、会話の中で「年齢的にも早く結婚相手探さなきゃ〜」だとか、「若いっていいな〜戻りたいよ」、「今のこの若いうちに」など言っていたら、全力で「あなたはいつだって最高で綺麗です」と伝えていきたい。彼女達の魅力が、容姿以外でも、若さ以外でもあり余っていることを知っている。だからあなたの旬は、いつだって永遠であってほしい。
どうしたって今までできょうが1番かわいいんですよ、僕も私も。
先程は “女の旬” についてだけ触れてきたけど、実は謎格言「女は30歳まで」の前には「男は30歳から」という言葉がセットになっている。「男は30歳から。女は30歳まで。」だ。この言葉、29歳以前の男性は旬ではないととれてしまう。
例えば25歳や27歳の男性は「まだまだ半人前だね〜」だったり「若いね〜 (笑) 」と言われているのを見たことがある。30歳にならないと発言権が弱かったり、少々ナメられたりしている風潮も度々見てきた。女性は若くいることを求められ、男性は老いることを求められる。
同世代の恋愛面でもよく、「彼氏いくつなの? へ〜32歳? ちょうどいい歳だね!」みたいな、30歳以降が色々と “ちょうどいい” らしいことを、結構聞く。たぶんこれには、精神の成熟具合や平均収入などの意味が含まれているんだと思う。先日結婚した26歳の同僚男性は、周りから「まだ若いのに」、「よくその歳で決心したね! すごい!」と言われていた。純粋な祝福の言葉なはずなのに、やっぱりここにも「男は30歳から」という文化が少なからず垣間見えた。求められるものは違えど、男性にだって年齢でジャッジされる現実がある。年齢による容姿の選別にも、勝手に旬を決めつけカウントダウンされることにも、納得できず苦しむ人だっているだろう。
全てにおいて、誰かの旬を他人が勝手に決めつけていいものじゃない。人間の成長スピードは人間の数だけあるし、魅力も違う。それぞれ全く違う種類の旬があるはずで、年齢はただの数字に過ぎないのだ。『あの頃。』で登場した5人とも、「あの頃に戻りたい」という表現をしなかった。癌を患い闘病したコズミンにも、その台詞は用意されなかった。「今が1番楽しい」という言葉が、何度も何度も使用された。
青春は年齢に関係無く、何度だってある。青春という、たまらなく恥ずかしくて、狂気的で、稚拙な成長期間を乗り越え続ける。そうしてわたし達は、ちゃんと、常にピークを更新していく。変わらないまま、あの頃のままでいられるはずがないのだ。あなたの旬は、あなたが決めていいものですから。
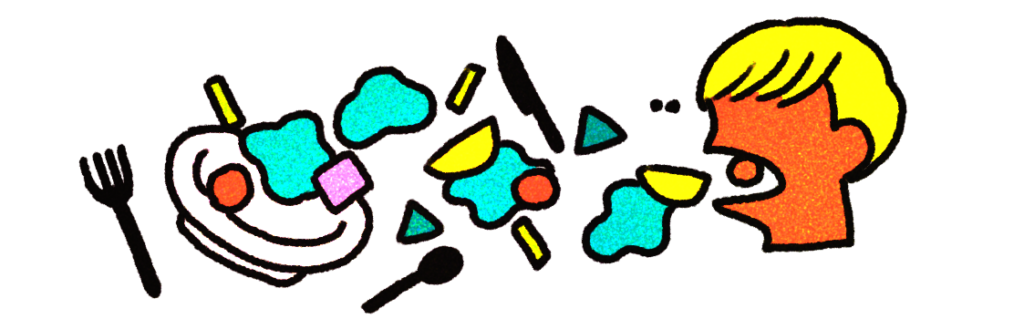
文とイラスト・くどうしゅうこ
編集・和島咲藍
フラスコ飯店の最新の更新をチェックしてみてください!
上のイラストをクリックすると遷移します!
解説:映画『あの頃。』(2021)
原作:
劔樹人
監督:
今泉力哉
脚本:
冨永昌敬
音楽:
長谷川白紙
出演:
松坂桃李、仲野太賀、山中崇、若葉竜也、芹澤興人、コカドケンタロウ、山崎夢羽 ( BEYOOOOONDS ) 、など
バンドや音楽ユニットにかかかわってきた劔樹人の自伝的コミックエッセイを、『愛がなんだ』の今泉力哉監督が映画化。
この映画全体的に豪華。キャストも、制作陣も豪華すぎる。松浦亜弥さん役ではハロプロ現役アイドルの山崎夢羽 ( BEYOOOOONDS ) さんが起用されていたのも「いや、最高かよ! 」となりました。作中ではばっちり “あやや” で衝撃でした。山崎夢羽さんなんだけど、ちゃんと “あやや” だった。すごい。そしてかわいすぎる。映画館で「ハゥ……かわいい意味わからん……!」って叫びそうになりましたが、間一髪ギリギリ喉元で抑えきりました。
原作がエッセイである事、実力派俳優陣の演技技巧、温度、音楽、台詞の言い回しなど全てがいい形で作用していたことで、生々しさと、お伽話のような創造物感が絶妙なバランスで混在していた。不思議だったけど、それも含めてとてもおもしろかった。
記事でも書きましたが、本当にハロヲタじゃなくても十二分に楽しめる映画。なんですがやっぱり作中でちょこちょこ出てくるハロメン小噺やハロプロの名映像祭り、名曲祭りにはただのハロヲタとして沸きまくってしまいました。
最後に、わたしの推しはアンジュルムの佐々木莉佳子さんです。



