©️1986 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.
12歳の頃、友達を探していた。12歳が終わるまでに親友と呼べる存在が欲しかった。日々失われる少年時代。中学受験を控えて私は焦っていた。というのも、映画『スタンド・バイ・ミー』の最後にある言葉を額面通り信じていたからだ。
「あの12歳の時のような友達はもうできない」
エンディングが流れる前に、作家となった主人公がコンピューターに打ち込む言葉。
それを見た小学校低学年の私は、「親友を見つけるなら13歳になるまで」なんていう風に信じてしまったのだ。おかしな話だけど、でも切実だった。
猪名川の図書館
どの年齢で出会ったとしても、大切な人は大切な人だし、そうじゃない人はそうじゃない。同じ関係性なんて一つとしてないのだから、友達に順序をつける必要なんてない。
でもそう思えるのは25歳になったからで、当時は映画に出てくる4人の冒険に心酔しきっていて、12歳までに親友を見つけないといけないと思い込んでいた。
図書館のブースで母と祖母と見て以来、本当に好きな映画だった。
祖母の家から車で20分のところにある猪名川町の図書館。隣にジャスコがあって、買い物のついでに図書館でよく映画を観た。たいていはディズニーやドラえもんのアニメだったけれど、時々実写の映画も観た。その中に『スタンド・バイ・ミー』があった。5歳や6歳そこらで、正直よくわからなかった。
劇中劇というものが理解できなくて、今までいた4人の少年がいなくなって急に始まる、ブルーベリーパイの早食い競争がさっぱりわからなかった。あと、ヒルも現実世界で見たことがなかったので、ゴーディが気を失うシーンも理解できなかった。
母にも祖母にも「どうしてみんなゲロを吐いているの?」とか「血を吸うってことは、ヒルは蚊みたいなものなの?」とか訊いた記憶がある。納得いく答えは得られず、ずっと考え込んでいた。数年後、学童の遠足で川遊びをした時に、私はうっかり「本物の」ヒルを見つけてしまい大パニックを起こすのだけれど、それはまた別の話だ。

©️Photofest/AFLO
映画にあるアメリカの少年達にあこがれていた。映画にあるようなツリーハウスの秘密基地を作りたかったし、焚き火を囲んで普段できないような話をしたかった。死体を探しに線路を歩いて行くのは無理でも、友達と自転車でどこまでも走るみたいなことならできそうだった。
だがしかし、小学生の私にそんなイベントが訪れることはなかった。5年生の自然学校ではキャンプファイアーを囲んで歌ったりしたけれど、それは親しい友達同士だけではなかったし、仲のいいグループで、バスに乗って甲山まで登ったこともあったけど、母親軍団もなぜかついてきた。次第に中学受験の塾が忙しくなってきて、それどころじゃなくなってきた。
結局私が12歳までにやったことといえば、神社の池で釣ったブルーギルを野良猫にあげるとか、すっぽんを発見して捕獲を試みるも惜しいところで逃すとか、友達の飼い猫と遊んで猫アレルギーが判明するとか、用水路で釣ったアメリカザリガニをいじめるとか、そういうのだった。
今思えばそれはそれで素晴らしい経験だったのだけど、当時は何か物足りないと感じていた。なにせ親友が欲しかったのだ。それもとびっきりの親友が。しかしいつになっても私のもとに「親友」は現れず、中学になっても「親友」探しは続いた。
塚口の彼
受験して入った中学校。よく一緒に帰る友達がいた。人気者ばかりのサッカー部の中で彼と私は何となく浮いていた。同じように映画や音楽が好きで、周りの金銭感覚に違和感を抱いていた。
変な話だけど、『スタンド・バイ・ミー』への憧れが強すぎた私は、塚口駅で降りるその彼が、映画にあるような「親友」なのか見極めている時期があった。
誰もまだ英語の曲を歌えない時期に彼はカラオケでボン・ジョヴィの「It’s My Life」を歌っていたし、サッカーのスパイクも、みんなは履いていないアンブロのを履いていた。みんなが気づいていないような、かっこよさを持っていた。もしかしたら当時の彼も気づいていなかったかもしれない。
彼も私も美大に進学することを考えていて、高校に上がる春休みに予備校の無料体験に一緒に行ったりもしたけれど、高校では違う部活に入ったこともあって次第に離れてしまった。
一度、彼と梅田のTOHOシネマズで『Super 8』を観た。その映画は『スタンド・バイ・ミー』と『E.T.』を足したような爽やか青春映画という触れ込みだったのだけど、二人ともそれほどいい映画だと思えなくて、その後無言でサブウェイを食べた。エル・ファニングがかわいかったと私は言ったけど、彼はシアーシャ・ローナンの方がいいと言った。いかにも彼が言いそうだと思った。なんなら今でも思う。
中学校に慣れるまで、かなりの時間が必要だった。もしかすると慣れるより先に卒業を迎えたかもしれない。それぐらい受験をして入った中学校は、小学校と別世界だった。学校帰りのコンビニでみんなが使う金額とか、持っている本の質と量とか、遅刻しそうになってタクシーで学校まで乗り付けるのとか、そういうのに毎回驚いていた。塚口の彼もきっと同じように感じていて、だからよく一緒にいたのだと思う。
昨日までいた小学校では、クラスメイトが駄菓子屋での万引きを自慢したり、来たる他校との対決について話し合ったりしていたのに、中学校のクラスメイトは教室の中で無邪気に追いかけ合っていた。
追いかけっこなんて幼稚なことをする友達は欲しくなくて、中学に入ったばかりの頃は、ずっと一人で本を読んでいた。けれど、森絵都やあさのあつこ、湯本香樹実の本には仲の良いティーンズが出てくるのだった。私は焦っていた。
悩みを共有できる友達が欲しかった
4人の少年がそれぞれ事情を抱えていなければ、私は『スタンド・バイ・ミー』にこんなにも拘らなかったかもしれない。無鉄砲なテディは父親に虐待されているし、クリスは兄たちがぐれていて誰からもまともに育たないだろうと思われている。バーンも同じようなところだ。4人の中では一番まともそうに見えるゴーディの家庭でも、両親が長男デニーの死から立ち直れずにいる。高校のアメフト部でもクォーターバックで人気者であった兄に比べて、自分には愛情がそそがれていないようにゴーディは感じている。
小説だともっと露骨でシリアスである。兄デニーを溺愛する両親はゴーディをほとんど無視していて、ゴーディは、家庭内で自分がまるで存在しないかのように感じている。
ノルマンディー帰りのテディの父親も、小説では詳細に書かれていて、息子の頭を薪ストーブに打ち付けて火傷を負わせて退役軍人の病院に入る。周囲は理解しづらいが、テディはそれでも父親を愛していて、病院にお見舞いに行っている。まだ PTSD なんて言葉がなくて、ベトナム戦争も始まってない時代だ。
飲んだくれの父親に殴られるクリスの怪我も家庭の描写も読んでいて悲しくなる。父親と兄のことがあるために、学校でミルク代を盗んだと決めつけられたりする。
4人それぞれのストーリーや背景があるから『スタンド・バイ・ミー』が好きなのだと思う。

©️1986 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.
私は私で、10代を通じて父親がいないということに悩んでいた。でも中学校の同級生はみな両親ともに揃っていて幸せな家庭にいるのだろうと思っていたから、友達には、ほとんど誰にも相談できなかった。
後になって、同級生の誰かも両親が離婚していたり、親が病気だったり、みなそれぞれに何かしらを抱えていたのだと知った。そういうのは友人になってから知るのであって、そういうのがあるから友達同士になるわけではなかった。
中学も高校もとにかく「親友」が欲しかった。文化祭や体育祭、修学旅行といったのがやって来るたび、このイベントがきっかけで親友ができないだろうかと考えたりした。
修学旅行の夜、ホテルの部屋で話したり、劇の練習を一緒にする時に、この人かなと思っても、何か違うのだった。とんだおバカさんだった。親友なんてものは作ろうと思って作るものじゃないのだ。自然とできるものなのだ。
「友達」は出来たけれど、どの「友達」も「親友」とは違う気がした。「これ面白いよ」って言って貸した本が、読まれず、お茶をこぼされて帰ってきて、悲しくなったこともあった。好きなだけ小説とか映画の話をしたり、家族のことを安心して打ち明けたりできる人が欲しかっただけなのだ。けれど少しやりすぎている感もあって、選り好みしていたのかもしれないと今なら思う。
全部フィクションだとしたら?
高校を卒業して浪人した。結局美大に進むのは諦めて、国公立大学を目指した。センター試験が終わった頃だったと思う。勉強の合間に、キングの原作を読んだ。
映画とあまりに違うことにびっくりした。映画と比べるとだいぶ大人向けだった。大体、始まりからしてすごい。いきなり最初のページに「なににもまして重要だというものごとは、なににもまして口の出して言いにくいものだ」なんて書いてあるのだから。
映画では1960年の9月の2日間しか描かれていないが、小説ではその後の顛末も書かれていて、大学進学クラスに入って猛勉強することになったクリスは、「中流家庭の身なりのいい」生徒に混じって、不良の身なり——本にはダックテイル・ヘアとか革ジャンとか、ペイズリー柄のシャツとかが出てくる。それらは大学に進学する人の服装ではないらしい——でゴーディと一緒に授業を受ける。
2人で猛勉強して同じ州立大学に入る。1960年の時点で英語の文法も怪しかったクリスは法学部に入りラテン語をすることになる。映画ではクリスは弁護士になっているが、小説では修士課程の2年目で刺されてしまう。
一方で、テディとバーンとの関係は薄くなってしまう。キングは「友人というものは、レストランの皿洗いと同じく、ひとりの人間の一生に入りこんできたり、出ていったりする」
なんて書いているけれど、本当にあっさりと関係は切れてしまう。
父親を侮辱されたテディをクリスが慰めるシーンも、汽車が迫る橋の上でバーンを追い立てながら走るシーンも、ツリーハウスでの時間も、ゴーディが作ったパイ食い競争の話をみんなで聴く時間も、小説には書かれているのに。4人は同じものをたくさん共有して、あんなに近くにいたのに、でも遠くなってしまった。くるりの歌にこんなんあったなとか思う。
結局のところ、なんて前置きをして、自分の友人達の顔を思い浮かべる。中学時代、高校時代、大学時代——まだ卒業してないけど、卒業した気分でいる——、それぞれの時代にそれぞれの人がいて、昼休みにサッカーをしたり、塾帰りにお菓子を食べたり、始発を待ちながらお笑いの話をしたりした。でも、今現在の時点でも大事なのは何人かだけなのだ。全員を全員愛するには時間もエネルギーも足りないのだ。
テディもバーンも、学校ですれ違う時に挨拶する程度の関係になってしまい、そして2人とも大人になる前に死んでしまう。キングの書き方は悲しすぎるくらい簡潔だ。
『スタンド・バイ・ミー』はスティーヴン・キングの自伝的小説だ。12歳から13歳になろうとする夏の思い出を書きながら、キングは何を考えていたんだろう。キングくらいの書き手なら何も考えずともサラサラ書けるのだろうか。
自分が書くなら「あの頃はよかったな」なんていう懐古主義で終わらせたくない。けれど、少年時代の世界をそのまま小説にするのは難しそうだ。キングは1960年当時の野球の話をしたり、流行った曲の名前を出したり、ケネディとニクソンの大統領選に触れたりしているけれど、そんなことを書いてもあの夏はもちろんもう戻ってこない。
でも小説の中で再生産されたあの1960年の9月は小説にも映画にもなって、2000年代の日本に住む男の子が「親友を13歳までに作らないといけない」なんていうおバカな勘違いをするまで大きくなった。もし、嘘を交えずに本当のことだけを書いていたら、こんな風に広がらなかっただろう。自伝的小説なんていうけれど、ぶっちゃけ、キングが書いたのはフィクションなのだ。
最近、久しぶりに猪名川のあの図書館に行った。小さい頃はあんなに大きかったのに、とても小さくて悲しくなった。図書館の本も少なかったし、ロビーの前の芝生はサッカーコートの半分しかなかった。低学年の頃は永遠に広がるように思えたのに。思い出の中の図書館は、2021年にはもう存在していなかった。
そして現れた親友
最後に私に親友が現れたかどうかだけ書いて終わろう。
友達なんて、人によって定義は違うし、多分文化によっても違う。一方的に友達だと思っていてもしっぺ返しを食らうことだってある。
年齢にとらわれずに、どの時代に友達を作ってもいいし、友達だと確かめる術がもう無かったとしても、友達だと思っていればもうそれは友達だ。友情は時空を超える。十三で乗り換えてから塚口まで車内で交わした会話を、彼はもう忘れたかもしれないけれど、私は当時を思いだしてまだうっとりすることができる。2021年も、多分これからも。
簡潔に書くと、親友は現れた。田中君。別に出会った瞬間にビビビッがあった訳でもないし、ゴーディとクリスのようにお互いがお互いを支えながら頑張る時期があったわけではない。何となく生きていたら出来ていた。一緒にミスタードーナツで駄弁ったり、焼肉を食べたり、映画について話していたら、いつのまにか親友だった。めちゃくちゃ幸せだと思う。
彼は今東京にいて、アルバイトをしながら自分の夢を目指している。むこうも私のことを親友だと思っていたら嬉しい。これはフィクションだと困る。
文・石黒優希
編集・和島咲藍

もしよろしければ応援してください!(店主より)
参考文献
スティーヴン・キング 山田順子訳
新潮文庫『スタンド・バイ・ミー ——恐怖の四季 秋冬編——』P 26, P 339
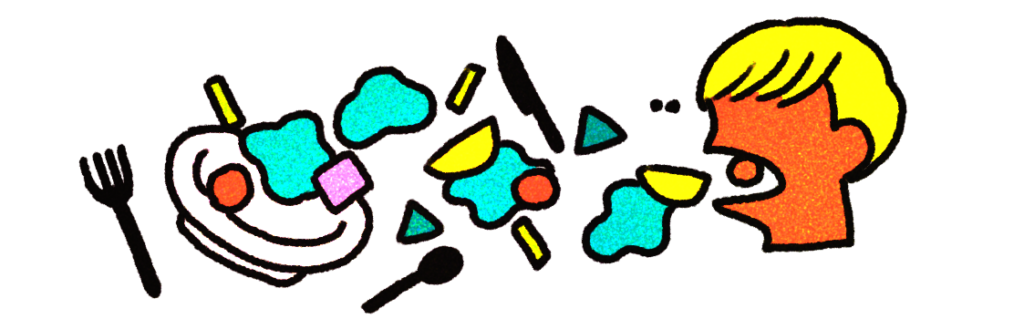
解説『スタンド・バイ・ミー』(1986)
監督:
ロブ・ライナー
原作:
スティーヴン・キング
キャスト:
ウィル・ウィートン、リチャード・ドレイファス、リヴァー・フェニックス、コリー・フェルドマン ほか
スティーヴン・キングの自伝的小説をロブ・ライナー監督が86年に映画化したもの。小説の舞台はキングの育ったメイン州だが、ロケ地になったのは西海岸のオレゴン州。天気がいいからか、明るい挿入歌のせいか、映画版の方が小説版より、陽気で朗らかな雰囲気になっている。
少年達の夏の冒険に自分の青春を重ねるもよし、若くして亡くなったリヴァー・フェニックスの煌めきを堪能するもよし。色々な楽しみ方がある映画だ。悪役の中にいるキーファー・サザーランドを探すのもよい。そして最後は、エンドロールで流れるベン・E・キングの歌声に合わせて、みんなで歌って踊ろう。
90分以内の短い映画なので、忙しいあなたにもオススメ。ちょうど大学の授業1コマと同じ時間なので、授業準備をしていない日の大学教員は、潔く授業を諦めて、プロジェクターで『スタンド・バイ・ミー』を流すだけの90分にしてほしい。大学生からのお願いである。

====== koukoku desu======

スティーヴン・キング 山田順子訳
新潮文庫『スタンド・バイ・ミー ——恐怖の四季 秋冬編——』
あまりにも有名な本作ですが、原作を読んだことがある人は多くはないのではないでしょうか。
石黒さんが記事のなかでも引用し「もっと露骨でシリアス」「映画に比べてだいぶ大人向け」と語る小説版も、ぜひ楽しんでみてください。
¥850-
この作品を Amazon でチェックする
====== koukoku owari======

