子どもの頃に迷子になったことがある。
あるらしい。
その時の記憶はほとんどないけど、大人になってから母親から何度か聞かされたから、なんとなく「ぼくは迷子になったことがある」という事実だけが記憶として残っている。
振り向くと、いるはずの母親がいない。子どもながらに「なんとかなるかな?」という感じで周りを見渡す。本当にいない。
不安や恐怖が押し寄せてくるけれど、できるだけ感情を抑えながらいるはずの母親を探し回ってみる。「落ち着け!落ち着け!」と思えば思うほど焦りは膨らみ、歩くスピードが早くなっていく。心とは裏腹に体温が上がり、油汗と涙が滲み出てくる。煽るようにいつもより速いスピードで夕陽は沈んで行く気がする。その頃には自然に軽く走り出していたりして、その歩幅や心拍によってさらに恐怖が押し寄せてくる。暗くなる前に母親を見つけなければ。そう思っている頃には頭の中の冷静さは消え去っている。声を出して母親を呼んでみるけれど喉の奥の粘膜が邪魔をして涙声がこぼれ出す。
「ぼくは迷子だ!」
気づいた頃には母親を探し、泣きながら走っている。誰がどうみても迷子だ。
ほとんど覚えてないけど、迷子になった時の自分はきっとこんな感じだ。
そんな迷子になった時の恐怖の記憶を呼び覚ます映画がある。
小学生の頃レンタルビデオ店で借りてきた『クレヨンしんちゃんヘンダーランドの大冒険』(1996)を見たぼくがあの映画に対して感じた印象は恐怖だった。
遊園地で迷子になるしんのすけ。それをきっかけにドンドン事件に巻き込まれていくのだが、両親も友達も幼稚園の先生たちも事件に巻き込まれている本人の言葉を信じてくれない。
ヘンダーランドという遊園地を本拠地に世界を乗っ取ろうと企む悪の組織にしんのすけはひとりきりで立ち向かわなければならないのだ。
助けを呼んだって誰も駆けつけてくれない状況。『クレヨンしんちゃん』という世界の中で迷子になった5歳児。野原しんのすけ。
ぼくはあのしんのすけの不安な表情を時々、思い出す。
強がりは恐怖を育てる餌になる
15歳のころ、初めてアルバイトの面接を受けた。ホームセンターの事務所に電話をかけて履歴書を書き、面接を受けに時間通りに事務所に向かう。
何もかも初めての経験でビクビクしている15歳のぼくは、まるで自分が何度も面接を経験している大人であるかのように振舞うことでなんとか心を保っていた。
本当は今すぐにでも電車に飛び乗って家に帰りたかった。
恐怖心は強がれば強がるほど大きくなっていく。もしぼくがビクビクしているということが面接官にバレてしまったらどうしよう。面接を落とされるんじゃないか?というか、ビクビクしてると感づかれることに対してさらにビクビクしていた。
今思えばバレバレだったんだろうな。そもそも、15歳という年齢は自分が思っているよりまだまだ未熟で社会経験もほとんど積んでいない当時のぼくが、どれだけ平然と面接を受け答えしたところでボロが出るのが当たり前だ。
面接会場はホームセンターの店舗の中にある事務所で行われる。事務所に足を踏み入れる方法すらわからなかったぼくは電動ドリルの棚を整理している女性従業員に声をかけた。
「アルバイトの面接?あちらの事務所を尋ねてみてください」
電動ドリルの芯を束ねて片手で鷲掴みにしている30代後半くらいの女性従業員はもう片方の手で茶髪を整えながら愛想は振りまいているにしても、めんどくさそうにぼくをあしらった。
「その尋ね方がわからないんだよ!」
そう叫びたくなったところをグッと堪えて、お礼を告げ、逃げるように電動ドリルコーナーから立ち去った。
誰もぼくに「事務所の尋ね方」まで手取り足取り教えてくれるはずがないことはわかっていたけれど、もう少し親切に対応してくれるものだと勝手に考えていたから驚いた。
ホームセンターの中をあくまでお客さんの立場で歩いているかのように振る舞いながら、頭の中では「事務所の尋ね方」をいくつもシュミレーションしていた。
その間も何人かの従業員とすれ違うのだけれど、これ以上あの電動ドリルさんみたいなあしらわれ方をすると心が折れてしまいそうで声をかけることができなかった。すれ違う従業員たちの顔が「忙しいから声をかけないでくれ!」と無言の威圧をかけているように見えたのだ。
ようやく事務所のドアの前に立ち止まった時に考えていたのは、「今事務所から誰かが出てきたらどうしよう。心の準備ができていないのにうまく話ができるだろうか」という焦りだった。
そうなる前に腹を括ってドアをノックしなければ。
気の抜けたシンセサイザーによるJPOPの再現BGMが店内には響いていた。木材やゴム製品が混ざったような独特の匂いを嗅ぎながら、ジワリと汗が染み込んだ手でゆっくりとドアを叩いた。
ど緊張の中行われた面接は、声のトーンがやたらと高い男性従業員がギャグを交えながら出勤希望などを質問してくれたので、予め履歴書に書いてきた内容を口頭で答えているうちに15分くらいであっという間に終わった。
どうやら来週からぼくもこの店の従業員になるらしい。
冷房の効いた店内から自動ドアをくぐり、生温い外の空気に肌が触れた時、両肩に力が入っていたことに気がついた。ストンと肩の力を抜いて体の緊張を解した時に達成感と安心感が一気に溢れたのを覚えている。それと同時にさっきまでビクビクしていた自分を客観的に思い出して笑けてきた。
平気な顔をしながら冷静を装うことで更に緊張と恐怖が膨らんでいたことに気がついたからだ。
こんな風に恐怖は自分自身が強がって平気な顔をすればするほど余計に膨らむものなのだ。そしてそんな平気なふりをしている表情の裏には今にも泣き出しそうなほどの恐怖が隠れているんだとぼくは考える。
大人になった今でも不安を隠して平気なふりをしている時には『クレヨンしんちゃんヘンダーランドの大冒険』を思い出す。

映画.comより
しんのすけが見たヘンダーランドの夢と現実
「まいったなぁ。みんな勝手にどっか行っちゃうんだから……」
そんな独り言をこぼしながら平気な表情で園内を歩くしんのすけ。それまでシンプルでカラフルに、楽しい夢のような世界として描かれていたヘンダーランドという遊園地の作画が突然変貌する。
空に浮かぶ遊園地のマスコットキャラクターの巨大バルーンにリアルなグラデーションタッチの影が描かれ、遠巻きに聞こえるジェットコースターの滑走音と乗客の悲鳴。噴水の縁に腰を下ろし小休憩を挟んでいるカップル。さっきまで夢のような世界だったはずの遊園地がリアルに、あくまで作り物の世界として描かれはじめる。
しんのすけの不安を、表情ではなく背景や演出で表現するのだ。巧みな演出が子どもの頃の “迷子の原体験の記憶” を呼び起こす。平気な顔をしながら、まるで大人のように振舞うしんのすけ。小走りになって道を引き返すワンカットの彼の挙動からは焦りを感じる。
映画を観ている大人からすればどうってことのないシーンかもしれない。だけど、不安や恐怖を隠しながらホームセンターの事務所のドアをノックしたぼくのようにしんのすけの目にはヘンダーランドが不気味でリアルな風景に見えているのだ。
迷子になったあの恐怖の感覚を内面ではなく背景で描いたその技法で表現された世界は未だにぼくの心に焼きついている。大人になった今、あのシーンを初見で観たとするとそこまで恐怖を感じただろうか。大人になってからでは感じることはできないかもしれない。
そんな子どものトラウマ体験を意図的に作り出しているあのワンシーンが頭に焼きついて離れない。
覚えてないのに覚えている恐怖の記憶
ぼくは迷子になったことがあるのだけれど、その記憶はほとんどない。子どもの頃の記憶というのは歳を重ねるごとに薄れていくもので、その記憶のビジョンを呼び覚まそうとすることは不可能だ。
ビジョン、つまり景色やその時何を考えていたかは覚えていないにしても潜在意識の中の感覚だけは覚えているみたいだ。特に「恐怖」や「不安」といったような痛烈な感覚はぼくの意識の奥にこびりついている。
『クレヨンしんちゃんヘンダーランドの大冒険』を見ることで思い出す子どもの頃の恐怖の記憶。あの作品はぼくにとって「なぜか覚えている映画」であり、「なぜか覚えている恐怖の記憶」を呼び覚ます、薄れていく記憶へのカンフル剤のような存在なのだ。
迷子や初めての面接のように未知であるという恐怖は経験を経て記憶から消えていく。
あの電動ドリルの女性従業員は一緒に働いてみると意外と優しかった。平気な顔で冷静に振る舞おうとしていたぼくの心が、勝手に彼女から恐怖を感じていただけだったのだ。
自分で自分の心を縮ませることで恐怖は更に肥大する。ぼくにとって迷子になったしんのすけの、あの平気そうな表情こそが『クレヨンしんちゃんヘンダーランドの大冒険』の一番のトラウマシーンなのだ。
文・金城昌秀
編集・川合裕之(フラスコ飯店 店主)
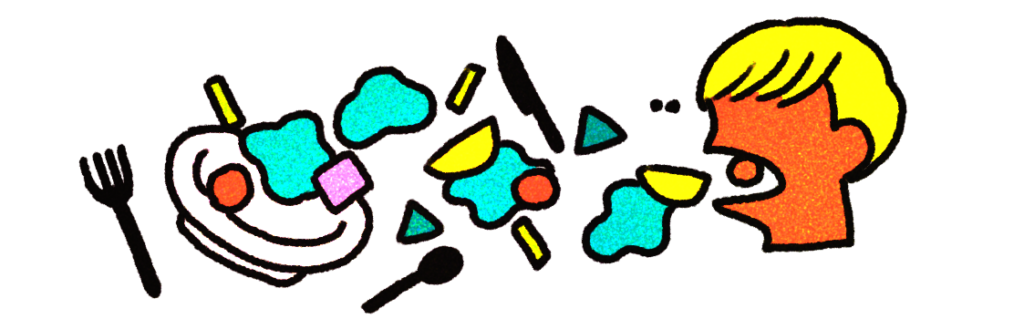


———————
解説『クレヨンしんちゃんヘンダーランドの大冒険』(1996)

映画.comより
監督:
本郷みつる
脚本:
原恵一,本郷みつる
原作:
臼井儀人
出演:
矢島晶子,ならはしみき,藤原啓治,渕崎ゆり子,大塚芳忠,田中秀幸,雛形あきこ ほか
この作品には、本作も含む「お話」というもののメタ表現が施されている。
悪役のオカマの魔女であるマカオとジョマの目的には「この世界を奪う」という表現が使われている。この場合の「この世界」というのは『クレヨンしんちゃん』の世界を指していて、決して我々が暮らしているリアルな世界を指してる訳ではない。
マカオとジョマは魔法の力を使ってあらゆる「お話の世界」を飛び回り、支配していく「お話」に対するメタな存在のキャラクターなのである。
そのため、作中一度だけ登場するマカオとジョマの命でもあるトランプのジョーカーは「(映画を見ている)子どもたちが退屈しないように……」などという言葉を使う!これはスクリーンの中のキャラクターが観客に対して話しかけるメタ表現にも似ている。
本作冒頭、紙芝居を聞き終わったしんのすけたちの疑問「めでたしめでたしの後、その二人はどうなったの?」という言葉で始まりながら、エンディング最後のシーンは「めでたしめでたし」で締められる。
この演出によりメタな存在のマカオとジョマを倒し、『クレヨンしんちゃん』の世界を救った野原一家の「お話」はこれでおしまいです。というように “メタ表現をさらにメタ表現で締める” という複雑な構造を持った作品となっている。


