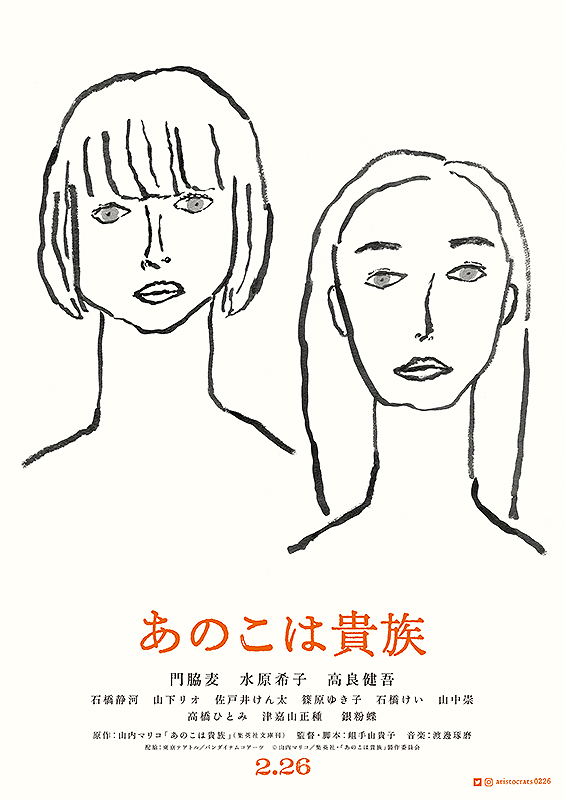(C)山内マリコ/集英社・「あのこは貴族」製作委員会
「あのこ」が誰なのか、映画がはじまるや否やわたしたちはすぐに察する。元旦の東京をタクシーで移動する彼女の身なり、運転手のどうでもいい話に返事をせず、かといって流れる夜景にも関心を示さない物憂げな表情。そして立派なホテルで豪華な食事を楽しむ彼女の家族を見て「このこが貴族」だと確信する。じゃあわたし(たち)はなんだろう。
映画『あのこは貴族』はあらゆる「対比」が散りばめられた作品であり、その対比はタイトルから既にはじまっている。家族との優雅な会食とそこでの話題、「おばあちゃま」呼びなどなど、わたしたち観客は華子との生まれ育ちの比較をせずにはいられない。
視覚的に描かれた “映画的対比”
華子は自己主張がなく流れに逆らわない人物に見える。その性格は彼女のファッションにも表れている(服装やヘアメイクで人の内面をアレコレ推測するのは失礼だけど、映画なので!)。チクチクなんて絶対しなさそうなワンピースとストール、傷のない綺麗なバッグ、靴。全て有名なブランド物だろうが、どれもオーソドックスで、上品さは感じても彼女の本心はよくわからない。手入れの行き届いた髪と爪、シンプルなメイクも何かのお手本通りみたいだ。華子はどんな時も「華子そのまま」で存在している。その存在が周りから望まれている、許されているとも言える。
対して美紀は時と場合によって服装とメイクを大きく変える。お金に余裕がなかった大学時代の私服、バイト中のドレス、実家で着替えたジャージ、幸一郎に呼ばれたパーティーでのスーツ。その数だけいろんな自分がいる。
華子はどこに行っても何をしても「松濤にある榛原家の末娘」だ。その肩書き全ては他者からもらった土台であり、彼女自身で獲得したものはまだ、彼女のプロフィールには含まれていない。
華子と美紀が異なるキャラクターであることはファッションの「対比」からも伝わってくる。このような対比の構図がちりばめられた作品だが、今回は特に注目したい「建物」と「移動」の2つにテーマを絞って考察していきたいと思う。
アフタヌーンティーはビビる

(C)山内マリコ/集英社・「あのこは貴族」製作委員会
まずは「建物」を利用した対比から。
大学時代に美紀と同郷の里英が、大学の知人とお茶をしたビルの高層階にあるカフェと、美紀と里英と二人でお茶していた地上階にある喫茶店。お店の雰囲気やメニュー、価格も違えば建物の高さ、窓から見えている景色も違う。逸子が美紀を呼び出したカフェも前者の高層ビル系だ(逸子は華子たちの仲間内ではかなりアウトローなタイプのようだけど、幼い頃から染みついたソレは逸子の傍から決して離れない)。華子と逸子が幼馴染たちと会っていたホテルのカフェは、階数は低いが席から見える風景は美しい。ビルの群れと小さな車たちに代わって、職人が手がけた見事な造園が客を出迎える。
美紀と幸一郎が会っていた中華料理店は、不透明な窓ガラスで外の様子は把握できないが、建物の高さは低めに見えた。きっと幸一郎はこの店が気に入っていたと思う。美紀とだったら入れるこの店を。なんとなく、年季の入った薄暗いお店の雰囲気と、幸一郎の心の内を重ねてしまう。高い場所から見下ろす東京の姿に、視界に入ってくる整備された景色に彼は疲れているのかもしれない。

(C)山内マリコ/集英社・「あのこは貴族」製作委員会
実は原作にない場面がいくつも追加されているこの映画。里英との喫茶店も、幸一郎との中華料理店も、映画を作ることで生まれたシーンだ。
建物から少し話はずれるが、里英は作中で最も見覚えのあるキャラクターだとわたしは思っている。友達か、友達の友達にいそうな感じ。原作の美紀は里英のことを苗字で呼んでいたが、映画では下の名前で呼んで、昼だけどお酒飲んじゃおうかって笑いあえる関係に変更されている。里英という、一見なんでも効率よくできて特別な、よくよく思い返せばありふれた人(それはわたしたちの誰かかもしれない)の内面を丁寧に描き足している。
そして美紀との中華料理店のシーンも、幸一郎つまりは「貴族」という、わたしたちから遠い場所にいるキャラクターの肉付けにも成功している。
同じ人物の2つの部屋

(C)山内マリコ/集英社・「あのこは貴族」製作委員会
そして、建物の高低差という観点からは外れるが、美紀の過去の部屋と、映像化によって追加された現在の彼女の部屋との鮮明な対比も描かれている。
富山にある実家の、今の美紀とはかけ離れた過去の自室。ベッドと勉強机を中心に構成された独特な空間では、東京で一人で暮らす大人の美紀は部屋の「異物」であるし、同時に部屋は美紀の「遺物」にも見える。東京とは違い、実家の窓から景色なんて眺める必要ないでしょ、と言わんばかりに家の外の景色は画面に映らない。窓の外を映さない演出は幸一郎との中華料理店を思い出す。
使い込んだ参考書、カーテンと布団の柄の幼さ……この部屋の時間は止まっている。部屋だけでなく、家族も商店街も駅も。美紀と似た故郷を持つ人なら知っていると思う。電車の車両の少なさ。左右が畑の道。閉まっていく小さな店たちとたまに新しくできるデカいスーパーみたいなもの。東京ではほとんど耳にしない言葉のイントネーション。わたしは徳島出身で、2年ほど東京に住んだことがあり、自分と美紀が重なる部分も多かった。
華子は現在の美紀の部屋を眺め、全部美紀さんのものだから落ち着く、と言った。美紀は東京で大人になった。自身の選択によって確立されたその空間は、おそらく華子の部屋とは正反対だろう。もちろん過去の美紀とも違う。美紀の東京の部屋は原作では一切触れられていない部分だっただけに、美紀のストーリーをより強固なものとしつつ、華子に変化をもたらす一つのきっかけとして強く印象に残った。
飲食店や自室という身近な空間を用いた比較は、空間そのものだけでなく、そこに存在する人間の内面的な描写をも含んでいる。「対比」することでストーリーが展開し、ストーリーが展開する時には何かしらの「対比」が誕生している。
全ての「移動」はメッセージ
わたしはこの映画の「移動手段の対比」描写に心を掴まれ、いちばん大きくて長い長い拍手を映画の向こうの人々に送りたかった。それほどに見事でした……熱くなりすぎないうちにテンポよくいきます。最初はタクシーと自転車の違いについて。
とにかく華子はタクシーに乗る。東京の素晴らしい点の一つ「少し歩くと駅があってしかも次の電車がすぐ来てくれる」を全く利用しない。電車は一期一会の巣窟だ。乗れば必ず知らない人と遭遇する。だが、電車やバスを避ける華子は知らない世界の人間と出会う機会を排除しているようにも感じる。これには家庭の教育の影響もあるはずだが。タクシー内唯一の他者、運転手は透明な板越しに背中しか見えない。
対して美紀の自転車を漕ぐシーン。タクシーに乗る受動的な華子とは違って、目的地に向かって自分で選んだ道を自力で進んでいく。ペダルを回しハンドルを操作し、自分が起こした風に長い髪がなびく。この移動方法はまるで、いろんな苦労を乗り越え東京で生活をする彼女を象徴しているようだ。
対岸の2ケツ
自転車といえば、二人乗りのシーンが印象に強く残っている。『キッズ・リターン』『さよなら歌舞伎町』『耳をすませば』など、2ケツする映画が好きなわたしは自転車に人間が二人が跨った瞬間、それだけで嬉しくなってしまう。この映画では2つの2ケツがあったが、美紀の部屋から帰る華子が橋で出会った女性たちの場面に注目したい。
彼女たちのフラフラと安定しない走行を楽しむ笑顔は、夜の遠目からも眩しく映る。自転車を押しながらゆっくりと二人で進んでいく彼女たちと、逆方向に向かってひとり歩く華子はわかりやすく「対になる関係」として描かれている。両者には車道という「線引き」が存在し、華子と女性たちはそれぞれにとって「対岸の存在」であることが視覚的に表現されている。
華子を見つけた二人は、特に理由はなさそうだが彼女に手を振る。「こちらが見えますか?」それくらいの気持ちで。最初は遠慮がちに手を振り返す華子の動作はどんどん大きくなる。このささやかな交流は、彼女にこれから訪れる、そして自身が起こすであろう変化をわたしたちに予期させる。この「向こう岸」表現の素晴らしさは「対比」と「対等」を同時に叶えているところだ。
車、後ろに乗るか?
前に乗るか?
次にタクシー乗車と車の運転を比較してみる。終章は、隣に逸子を乗せ車を運転する華子から物語がはじまる。安心して眠る逸子の様子から華子の運転は素人ではないことがわかる。あのタクシー使いだった人が……! 同じ車でもタクシーの後部座席に乗るのと、自分で運転するのでは全く違う移動となる。
この演奏会に向かう移動、原作の二人は新幹線と電車を乗り継いで現地に到着する流れになっている。映画で改変した運転描写は、離婚して華子に起こった変化を明確に示すと同時に、冒頭のタクシーでホテルに向かう華子との対比でもある。そして、隣に友人を乗せて自分が望む場所へと舵を切る行為は、華子の人生における前進と捉えることもできる。
「建物」と「移動」は映像ならではの手法だ。文字よりも、複雑な情報を一瞬でこちらに届けてくれる。自転車を漕ぐ美紀、橋で華子と手を振り合った女性二人、2ケツする美紀と里英、どれも原作では見かけなかった場面。映画『あのこは貴族』において、映画で追加されたシーンは重要な描写を担っていると言っていいだろう。
一歩下がると見えてくる
「縦」と「横」の関係
いくつもの「対比」を見つけたところで、今の視点から後ろに下がりさらに大きな「対比」について考えたい。
主に「建物」では高低差が、「移動」ではその手段がポイントだったが、この2大テーマを「縦」と「横」に置き換えることができる。ということは「建物」と「移動手段」自体も対比可能な対象なのかもしれない。
その両者を対比するならば、「どう生きてきたか」と「どう生きていくか」になると思う。
まずは前者について。「建物」は自身の過去から現在までを表すものではないだろうか。生まれや育ち、これまでの経験で養われた価値観によって選ぶお店は異なる。今の自分を形成している生活様式の影響を大きく受ける。美紀の過去と現在の部屋も、彼女がその場所でどのように生きていたかを物語っているように。
そして後者。「移動手段」は現在の自己認識と、未来に向けた選択として見ることができる。そうすると「どう移動するか」は「どう生きていくか」と似た意味を持つ。様々な移動手段がある中で華子はタクシーを、美紀は自転車を選んだ(時には里英を後ろに乗せて走った)。それらは彼女たちのいま現在の等身大の姿である。しかしそれだけでなく、各キャラクターが選択する移動手段には、その人の未来が関連してくるのではないだろうか。箱入り娘が離婚後に仕事の一環として車を運転する、それはわたしたちが知る由もない華子の「これからの生き方」を少しだけ教えてくれる。

(C)山内マリコ/集英社・「あのこは貴族」製作委員会
美紀が東京で過ごした空間をいくつか思い返してみる。東京出身者に呼ばれて行った2つのカフェ、里英と一緒に働いた綺麗な商業施設のテラス、東京で借りている部屋。この「高さ」とは、「みんなが憧れ続けるまぼろしの東京」のイメージの一つの側面でもある。縦軸は上下の世界なのかもしれない。上と下、それらが持つイメージはどの時代も似ている。「上京」という表現も、この作品のテーマの一つ「階層社会」の言葉からも、ある種の高さと低さを想起させる。
とある風景を上か下か、または同じ目線で見る縦軸の動きに対し、横軸上の移動は風景そのものが変化する。横の移動は時に、今の生活から離れることを意味する。社会人になった美紀と里英、逸子、終章の華子には横軸の動きが見受けられるのに対して、幸一郎は縦軸を上昇し続けているように思えた。「横」はその人の意思が関係し、「縦」は自身ではコントロールできない「宿命」のような力が影響しているのかもしれない。
そしてこの映画は最後に「縦」と「横」を大きく俯瞰して終わる。
対比は続く、どこまでも
映画冒頭、年始の会食後に行う恒例の写真撮影の場面では、華子は椅子に座っていた。しかしラストシーンの演奏会では、自分の意思でその場所に行き、立っていた。この身体の状態は見た通りの華子の「自立」を意味している。「タクシーに乗って、座って、写真を撮られる」が「自分で運転して、立って、演奏を聴く」という能動的な行動に変化したのだ。冒頭と終わりの華子は、縦軸=「どう生きてきたか」と横軸=「どう生きていくか」を対比する、俯瞰的な視点をわたしたち観客にもたらしてくれる。
そして、その最後のシーンに2つめの「対岸」が現れる。写真撮影の作り笑顔とは真逆の、本心の微笑みを華子は見せた。客席を挟んで立つ幸一郎との微笑みの往復は、手を振り合う対岸と同様に、両者の「対等」な関係性を示している。出会いも結婚生活も全て縦軸の中で起こった出来事だったから、二人の視線は交わることなく終わってしまった。幸一郎を見る時の華子はずっと見上げる苦しい姿勢だっただろう。だが、華子が横軸の移動をしたことで、はじめて幸一郎を無理のない角度で眺めることができ、二人の目は合った。
華子が自身と対比できるようになったのは、他ならぬ美紀と出会ったからだ。美紀は自分と地元、東京、東京に住む人たち、幸一郎との比べっこの先へと到着した。自分と他の存在を縛ることをやめた彼女は自由だ(もちろん自由には困難が伴うけれど)。他者との比較は時々わたしたちを疲弊させる。だから。比べるのなら、いつかの自分と、今の自分にするのはどうだろう。改めて「あのこは貴族」は秀逸なタイトルだ。映画を観終わったわたしたちは「あのこ」と自分の対比をひとしきり終えて、今度は自分と向かい合う機会を与えられたことに気づく。

文・コムラマイ
写真を撮る人。アフタヌーンティーに行ってみたい。
公式サイト: https://www.comuramai.com/
編集・安尾日向
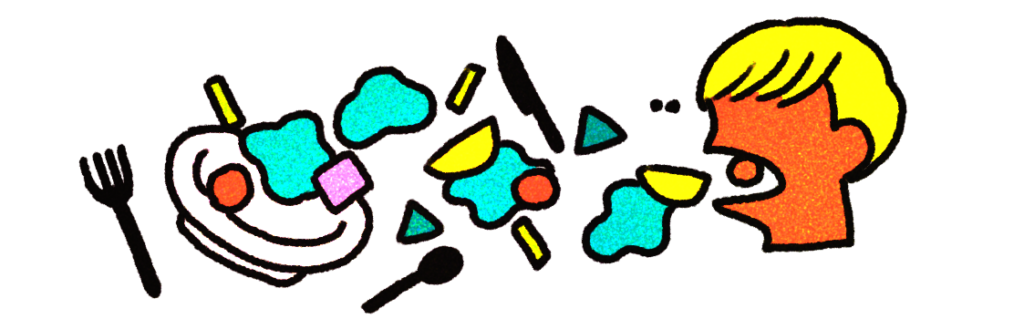
フラスコ飯店の最新の更新をチェックしてみてください!
上のイラストをクリックすると遷移します!
解説:映画『あのこは貴族』(2021)

(C)山内マリコ/集英社・「あのこは貴族」製作委員会
監督・脚本:
岨手由貴子
原作:
山内マリコ
出演:
門脇麦、水原希子、高良健吾、石橋静河、山下リオほか
『ここは退屈迎えに来て』『アズミ・ハルコは行方不明』などが映画化されている小説家・山内マリコの同名小説『あのこは貴族』(2016、集英社)を、『グッド・ストライプス』(2015)の監督・岨手由貴子が映像化。
本記事でも幾度となく触れているように、映像化にあたって追加されたシーンはいずれも名場面となっており、監督に拍手を送りたい。
主演の門脇麦・水原希子がキャラクターそれぞれのバックボーンをたたずまいから滲ませる鮮やかな演技を見せたことはいわずもがなだが、脇を彩った石橋静河・山下リオの二人の存在感もすごい! 最高のキャスティングです。
また、ふつうなら悪役的な立ち回りのみで終わってしまいそうな幸一郎に、苦々しい深みを出した高良健吾もさすがだ。彼の表情こそが、幸一郎が与えられ、縛られている語りづらいつらさを表現していた。これがあるのとないのとじゃ大違いだっただろう。(編集・安尾)




写真を撮る人・コムラマイが綴る
“写真の怖さ”
IMDbより
『ヴィオレッタ』(原題「My Little Princess」)は母イリナが娘エヴァのヌード写真を撮影し、1977年に出版した写真集「EVA(初版タイトル:Temple aux miroirs)」が大きな議論を呼んだという実話を元にエヴァ自身が監督した映画。本作では母の名前をアンナ、娘の名前をヴィオレッタに変更している。
映画のキーとなる3つの対立関係がある。「母 / 娘」と「撮る / 撮られる」そして「ヌード / ポルノ」だ。
つまり、ヌードを撮る母とポルノを撮られる娘が存在し、常に前者が権力を掌握する。
それぞれを対比させ、それぞれの感情や問題点を描いている。この分かりやすい対立構図は最後まで貫かれているが、どちらの立場に肩を入れて鑑賞するかで引っかかるシーンが違ってくる。
〈続きを読む〉