これもマスト?あれもマスト?
世の中にはコンテンツの品数が多すぎる。
どんなカルチャーを食べてよいかわからないと悩まないよう、フラスコ飯店が食べ合わせの良い「定食」を自信をもってご提案いたしましょう。ひとつのテーマに沿って映画・書籍・音楽 …… などなど媒体を横断した鑑賞セットを考案します。
今回のテーマは「社会に着せられたいろいろを一旦脱いで、たった一人の、愛おしい生命体としての “自分” を取り戻す」、題して「ハピネスチャージ!ひとりカラオケ定食」です。
「ひとりでカラオケに行く」というのは、何か特別な行為のように思います。友達や家族とではなく、一人で、誰にも気を遣わず、歌う曲の順番も知名度もおかまいなし。好きな曲を、好きなように、好きな顔で、好きなアレンジで、声に出して歌う。下手くそな歌だって、自分が気持ちよければそれで100点です。
歌っているのは自分のはずなのに、ひとりでにリズムを刻みだす手や足に苦笑してみたり、「わたしってこんなにはっちゃけられる人間なんだ」と気付いたり、普段は聴きながす歌詞が妙に刺さってしまって涙ぐんだり。一人でカラオケに行くと、社会で真っ当に生きていくための武装をぜんぶ取り払った、無防備な、だからこそ愛おしいひとつの生命体としての “自分” と出会えるような気がするのです。
「ひとりカラオケ」のように、社会に着せられたいろいろを一旦脱いで、たった一人の、愛おしい生命体としての「自分」を取り戻す勇気を与えてくれる作品をご紹介します。
ハピネスチャージ!
ひとりカラオケ定食 の献立
・映画『プラダを着た悪魔』
・小説『82年生まれ、キム・ジヨン』
・評論『「女らしさ」とは何か』
『プラダを着た悪魔』(2006)
最初にご提案するのはニューヨークの一流ファッション誌編集部を舞台とし、2006年に公開されてから、10年以上が経った今もなお多くの人を虜にし続ける『プラダを着た悪魔』です。
もはや説明不要の名作ですが、なかでも印象に残るのは主人公・アンディ(アン・ハサウェイ)が自分の力で自分の人生を取り戻してゆくさま。
この映画の中で、アンディは2度自分を見失います。
1度目は、自分の本当にやりたかった仕事ではなく、たまたま用意されたポストに甘んじたとき。彼女は、プライドを持って働いている同僚たちの食習慣やファッションへのこだわりを理解できないばかりか、嘲笑するのです。
そんなアンディに転機を与えたのは、仕事への並々ならぬ情熱とこだわりを持ち、無茶な要求で彼女を苦しめるカリスマ鬼編集長ミランダ(メリル・ストリープ)その人でした。ミランダはアンディの着ているセーターを指して「その色は何年も前に我々が流行色として決めたものだ」と言い、アンディが自分とは無関係と思っているこの業界も、実は生活に密接に関わっているものなのだ、と指摘します。
ミランダの指摘によって、アンディの世界の「解像度」が上がりました。想像もしなかった世界に想像が及んで目の前のことがよく見えるようになり、今まで「興味がない」と拒絶していた世界が自分ごととなって彼女の身に迫ってきたのです。
また、ミランダの右腕であるナイジェル(スタンリー・トゥッチ)の幼少期の、ファッションに対するきらきらした思い出を聞いたことも大きいでしょう。「同僚」、「理解できない種類の人々」だったナイジェルが、奥行きをもった生身の人間としてアンディの前に立ち現れたのです。
2度目は仲間への尊敬と仕事へのやりがいを得たアンディが仕事に没頭するあまり私生活とのバランスを崩してしまったとき。
しかし彼女は、今度は自分の力で自分の人生を切り拓きます。ミランダと同じ道を歩かないという決断。彼女にそれだけの力があったのは、世界をよく見ることによって自分のこともよく見えるようになったからだと、わたしは感じます。
恋、友情、仕事への葛藤をテーマにしたこの作品は『働く現代の女性のための映画』として語られることも多いのですが、これは女性に限らず「自分が生きる世界の解像度をあげたからこそ見えた新しい人生」の物語でもあるのです。
『プラダを着た悪魔』
監督:デヴィッド・フランケル
脚本:アライン・ブロッシュ・マッケンナ
原作:ローレン・ワイズバーガー
製作:ウェンディ・フィネルマン
出演:メリル・ストリープ, アン・ハサウェイ, スタンリー・トゥッチ, サイモン・ベイカー, エミリー・ブラント, エイドリアン・グレニアー
音楽:セオドア・シャピロ
『82年生まれ、キム・ジヨン』(2019)
「フェミニズム小説」として売れまくっている言わずと知れたベストセラー。この小説は、子育て中のある日、母親や友人に突然憑依したかのような異常な行動をとるようになったキム・ジヨン氏をカウンセリングした精神科医のカルテの体裁で書かれています。その淡々とした語り口と随所に挟み込まれる統計の数々は、キム・ジヨン氏が「女だから」という理由で直面した様々な理不尽を浮き彫りにし、その切実さは読み進めるのに苦痛を覚えるほど。
韓国人アイドルが「この本を読んだ」とSNSに投稿しただけで「フェミニスト宣言だ」として大炎上、とある政治家は「キム・ジヨンを抱きしめてください」という文言とともに本書を文在寅大統領にプレゼントするなど、韓国内で一大旋風を巻き起こし、日本でも韓国文学ブームの火付け役となった一冊です。
さて、「フェミニズム」という言葉を見て思わず「ウエッ」となったあなた、うんざりしてしまったあなた、ちょっと待ってほしいのです。これは他でもない「あなた」の小説でもあるのですから。
社会や周囲からの見えないプレッシャーに疲れ切ってしまったことはありませんか。自分が心から納得していないことを、それでも選ばなければならなかった経験はありませんか。
これは確かに優れたフェミニズム小説ではあるけれど、男性を糾弾するための小説でもなければ女性を不当に礼賛するための小説でもありません。この小説に出てくる男性登場人物たちもまた、「男だから」という理由で、兵役によって青春を中断させられたり、家族からの跡取りとしての重圧にさらされているのです。そんな彼らが、自分に近しい女性たち、例えば妻や恋人にはたっぷりの愛情と礼節を持って接している描写も随所に見られます。
男女の隔絶のその裏には、それぞれが抱える「生きづらさ」が潜んでいます。われわれが生きる現実世界がそうであるように、この小説にも完全な悪役はいません。
この小説は、1982年に生まれたたったひとりのキム・ジヨン氏(注)が懸命に生き、そしてこわれてしまう物語であると同時に、社会から背負わされた「生きづらさ」の中で生きるわれわれの物語でもあるのです。
(注:あとがきによれば1982年生まれの女児の中でもっとも多かった名前が「キム・ジヨン」なんだそうです。その意図を汲んだ表紙も印象に残りますよね。その匿名性、設定のうまさ、そこに具体的な人生を与える筆致よ……!)
傷だらけになりながらこの小説の最後のページを読んで、読み終わったとわかった瞬間にあまりの救いのなさに絶望で鳥肌が立ちました。涙にもならない何かが鼻の奥を突き刺します。それでも、この小説を読んで「私 / 僕のことだ」「彼女 / 彼のことだ」と感じ、その人のたったひとつの人生の、たったひとつの物語を思いやるところから全てが始まるんだと、そう信じてみようではありませんか。
『82年生まれ、キム・ジヨン』(2019)
著:チョ・ナムジュ
訳:斎藤 真理子
筑摩書房
『「女らしさ」とは何か』(1921)
2019年のフェミニズム小説に打ちのめされたあとにお勧めしたいのがこちら。明治から昭和初期にかけて歌人、作家、思想家として活躍した与謝野晶子が今からおよそ100年前に書いた「女らしさ」にまつわる評論です。
この評論が書かれたのは女子にも男子と同等の高度な教育を受ける機会と職業選択の自由を求める「女子解放運動」の真っ只中。与謝野晶子は「女子の中性化」と言う言葉を使って女子解放運動に反対する論者に反論する形で、「そもそも「女らしさ」なんて存在するのか?」、「「女らしさ」は最高最善の基準として女子の人格を支配するべきものなのか?」という問いを立て、歴史や社会状を紐解きながら「女らしさ」について考察します。
驚くべきはその論の普遍性。取り上げられているのは教育、職業から結婚、子の養育に至るまで、今日もなおわたしたちがぶつかり、議論が続けられている問題ばかりです。しかし、100年前に書かれた与謝野晶子の論は決して古くない。当時の情勢から、女子の権利に肩入れしている論調ではあるのですが、現代の男性が読んでも救われる部分は大いにあると思います。それは彼女が「女らしさ」を「人間性に吸収・還元されるもの」と定義しているからに他なりません。論者は「女らしさ」を愛、優雅、慎ましやかさだと言うけれど、それは「女らしさ」でも「男らしさ」でもなく「人間らしさ」であり、それを欠いている者は男子でも女子でも批難されてしかるべきだと、彼女は述べているのです。
(注:高度に教育を受け、人間性を鍛えた男女がそれでも子供を持ちにくいようなことがあれば、それは女子が「女らしさ」を失ったからではなく社会の経済的分配が不法に不公平で、無産階級の生活が子を持つことはおろか結婚にも不適当だからだ。それ以前に、結婚してもしなくても子供がいてもいなくても、それがその人の人間性の表現なのだからそれでよろしい、という論の先見性にも目を見張ります。)
私はこの評論を与謝野晶子から「人間」へのエールだと受け取りました。
与謝野晶子が「新社会」と夢見た、男女が(少なくとも表面上は)平等に高度な教育を受ける権利と職業選択の自由を獲得した2019年のこの社会。言うまでもなく、解決すべき問題はまだまだ山積みです。そんな中でも「女らしさ」「男らしさ」から解放され、「人間らしく」あることを諦めなくて済むように。100年前からの祈りを感じてみてください。
『「女らしさ」とは何か』(1921)
著:与謝野晶子

いかがでしたでしょうか。もちろん、「ひとりカラオケ」ほど気軽に、今回ご紹介した作品が取り扱っているようなことがらに取り組むのは容易なことではありません。しかし本来は、それらはわれわれの生活とは切っても切り離せないものなのです。
それに、わたしたちは真の意味では「ひとり」ではありません。私たちのそばにはいつでも、この世界に生きる「たったひとり」たちが残した背中を押してくれる作品が在るのですから。いつかはこんな息苦しい、それでも逃れられない問題を、私たちの日常の句読点にできるように、そして、それぞれがたったひとりの「自分」を大切にできるように。この定食は、わたしからの祈りです。
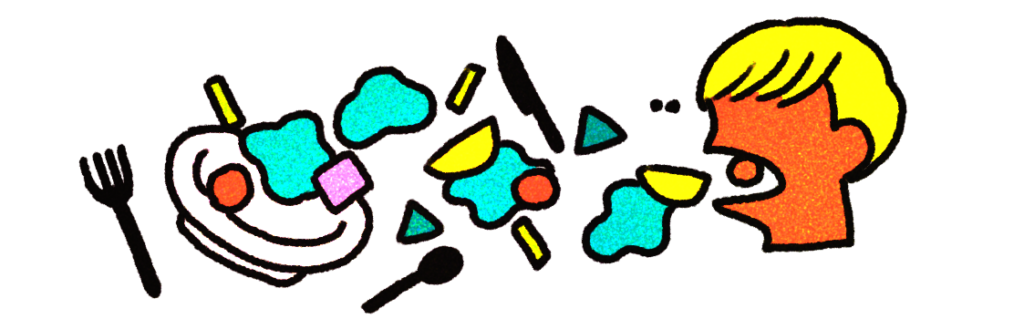
文・和島咲藍
編集・安尾日向
絵・くどうしゅうこ
▷そのほかの定食






