IMDbより
初めてこの映画を見たのがいつだったか、どうしても思い出せない。わたしが写真を撮りだした時か、もしかしたら写真の道を目指そうなんて思ってもなかった時かもしれない。どっちにせよわたしは「撮る」側の気持ちになってこの映画を眺めていた。全ては共感できないけど、理解はできるなあとか考えていた。それはわたしに写真を撮る覚悟ができていなかったことを意味する。
わたしは大学生の時にヌードに惹かれ、写真に惹かれ、今は写真家として生きている。人を撮っている。
文・コムラマイ
93年生。写真家。
わさびが食べられないけどスシローが好き。
そもそも、ヌードって何だ

IMDbより
これってヌード? ポルノじゃないの? そう悩んだことが何度もある。ヌードと聞くと絵画や彫刻、写真といった芸術作品で扱われる裸で、ポルノは性的欲求を刺激する猥褻なもの、性的に消費してもOKと認識されている。みたいなイメージがあるかと思う。両者にぼんやりとした線引きがあっても、実際ヌードとポルノの区別はかなり難しい。人によって「裸」の捉え方や作品の見方は違うし、その認識を統一することは不可能だから。ヌード作品は見る人とそれを生み出す人の判断にどかっと委ねられている。つまり、「ヌード」の定義はずっと曖昧で危ういのだ。
『ヴィオレッタ』(原題「My Little Princess」)は母イリナが娘エヴァのヌード写真を撮影し、1977年に出版した写真集「EVA(初版タイトル:Temple aux miroirs)」が大きな議論を呼んだという実話を元にエヴァ自身が監督した映画。本作では母の名前をアンナ、娘の名前をヴィオレッタに変更している。
実際にエヴァが被写体となった時期は4歳から13歳。まだ論理的な思考力や意思決定能力がない子ども。この年齢が示す通り、彼女は母の支配下で写真を撮られていた。この映画の原題もまさに “My” Little Princessだ。所有格の持ち主はあくまでも母である。
映画のキーとなる3つの対立関係がある。「母 / 娘」と「撮る / 撮られる」そして「ヌード / ポルノ」だ。
つまり、ヌードを撮る母とポルノを撮られる娘が存在し、常に前者が権力を掌握する。
それぞれを対比させ、それぞれの感情や問題点を描いている。この分かりやすい対立構図は最後まで貫かれているが、どちらの立場に肩を入れて鑑賞するかで引っかかるシーンが違ってくる。
母が雇っていた若い女性ヌードモデル ナディアが、画家エルンストから「ヌードに抵抗は?」と質問され、「別にない 裸って美しいもの」とさらりと答えるシーン。ここだ、と思い出した。初めて『ヴィオレッタ』を見た時は何も違和感はなかった。裸は美しく、だから作品のテーマにしたくなるのだと同意した。撮る側も写真を見る側も惹きつけられる魅力的な題材だから、裸を変に恥じらったりするより大胆に取り入れた方がかっこいいだろう。そう思っていた。
ナディアはきっと本心で話したはずだ。自分を被写体にした写真作品も、今ここに存在する自分のこの裸も美しいと。では幼いヴィオレッタのヌード写真も「裸って美しいもの」の一言でカタがつくのだろうか。
同じ写真家の被写体を務めている二人だが、決定的に違う部分がある。それはナディアは成人していて、自分の意思で自分のためにヌードモデルを引き受けているという点。ナディアの本職は別にあり、ヌードモデルは副業と明かしている。彼女はヴィオレッタと違い、自身の決定権を持っている人間だ。
ヌードの被写体は、自分に対する客観的な視点を持った大人であることが条件だ。
もう一つ決して無視してはいけないポイントがある。写された裸は写された人間が所有し、それが芸術か否かの決定権もまた被写体こそが有するべきであるということだ。
自分の裸が写った写真を公開されたくないと拒否する娘に母は「映画スターや銅像 絵のモデルを見なさいよ みんな脱いでる」と説得を試みる。母が例に出したヌードはポルノ的な消費はされておらず、あくまで芸術として受け入れられ一定の評価を得ている。つまり「あなたはまだ子どもだから理解できないだろうけど、ヌードは芸術表現の一つだから怖がらなくていい」と娘に言いたいのだろう。だが母が撮った娘のヌードは果たしてヌード(=芸術)だったのか。誰がどんな基準を持って芸術表現だと確信を持って宣言できるだろう。ヌードとポルノの区別は困難と先述した通り曖昧で難しい。写真家にとってはヌードでも被写体自身にとってポルノなら、それはポルノとして消費される裸なのだ。
母は自分が撮った他者の裸を芸術と主張し続けているが、裸が芸術表現を目的とした裸かどうかを決定するのは写真家でも写真を見たり評価する人でもなく、写真に写っている本人が決めることだ。そうあるべきだと強く言いたい。
【 映画『あのこは貴族』解説レビュー 】
ヌードに麻痺した世界

IMDbより
この映画で思い出す日本の写真集がある。1991年に発表された宮沢りえさんの写真集「Santa Fe」だ。当時18歳だった宮沢りえさんを、マネージャーを務めていた母の提案により、篠山紀信氏が撮影した。爆発的な話題性で、累計150万部以上の大ヒットを記録した。宮沢りえさんは「撮影がヌード撮影だと事前に知らされなかった」と話している(撮影は問題なく進んだそうだ)。
もし当時18歳の宮沢りえさんがヌードにならなくても、この写真集は同じぐらい話題になったのか、と考えずにはいられない。エヴァたちがいたフランスもわたしの住む日本も、言ってしまえば世界が、若い女性のヌードに興味を示している。ヌードがどうして話題になりやすいのかなんて、答えは明瞭だ。裸だから。普段隠している至極プライベートな領域だからこそ、ビジュアルの非日常的インパクトと想像力を掻き立てる強いパワーがある。
『ヴィオレッタ』では撮影とは関係ないタイミングで母が娘を撮っている。いきなり母がトイレのドアを開け、撮影衣装を着たまま用を足すの娘をいきなり撮るシーンだ。娘は「こんなとこ撮らないで」と激しく怒鳴った。実際のエピソードかはわからないが、かなりショッキングな場面だった。厳密には全裸でないのでヌードではなくセミヌードと分類するのだけど、セミかどうかはこの際もう関係ない。トイレ中の姿はヌードではなく、もはや盗撮ポルノに近い。だが母は「軽いおふざけよ」と怒る娘を適当にあしらう。
ヌード写真を制作する時、写真家は被写体の身体のイメージを一時的に貸してもらう。被写体は身体を明け渡してはいない。なのに履き違える写真家は後を立たない。この映画の母も勘違いしたまま、もうどうにもならないところまで突っ走ってしまう。
「映画スターや銅像 絵のモデルを見なさいよ みんな脱いでる」。これに該当するモデルはほとんどが女性だと思う。もちろん男性がモデルになったヌード作品もたくさん存在するが、全体で見ると女性が高い割合を占めるているはずだ。私たちは作品としての女性の裸に見慣れすぎている。しかも老人ではなく若い女性の裸。この事実がじわじわと撮る側の加害意識を麻痺させていく。若い女性のヌード表現が世界に許されている、求められているように思ってしまう。
ヌードは誰にとっても身近なテーマだ。いつもあなたのすぐそばにいる。だからこそ神経を尖らせデリケートに扱う必要がある。あなたが見たヌード写真は、誰かの大切な裸なのだから。
写真は怖い

IMDbより
危険なのはヌード写真だからではない。そもそも写真自体がある種の暴力なのだ。写真は撮る側に多くの判断が託される。今撮るか、撮らないか。撮るならどう撮るか。どの写真をセレクトするか、セレクトした写真をどう使うか……撮る側のセンスはもちろん良識や人間性を試される機会が、カメラを構えた瞬間から永遠と続く。
『ヴィオレッタ』は撮影中も撮影後も母が決定権を握って進んでいく。撮っていいか、掲載してもいいかと娘に確認をしない。それどころか娘が撮影を拒否しても無理やり続行させ、写真を使うなと言われても勝手に使いまくる。そうしてお金と名声を手に入れ、芸術家としてのエゴは誰にも止められなくなる。もしかしたらここまでは絵画や彫刻に置き換えても、少し同じ部分もあるかもしれない。ではなぜ写真が暴力的なのか。
撮る / 撮られるのパワーバランス
わかりやすい話がある。撮影は英語で「shoot」と言う。知っての通り「銃を撃つ」と同じ単語。そう聞くと撮影中の様子もなんだ狩りの風景に思えてくる。撮る側が銃を持ち、被写体に狙いを定めて1発の引き金を引く。その結果が1枚の写真となり、そこに写された者は撮った側の所有物となる。二者間のパワーバランスは常にカメラを持つ人間へと大きく傾いているのだ。
銃を撃つ瞬間も恐ろしいが、撃たれてそのあと誰かに所有された人間の写真の行方がわたしは一番怖い。『ヴィオレッタ』でも「写真となった自分」を自分で管理できない娘の不安が描かれている(エヴァは母にネガを所有・管理されており、撮った写真全てを確認することも廃棄することも叶わない)。しかも彼女の写真集や掲載された雑誌は大々的に出版されており、どれだけ頑張っても完全に回収することは不可能だろう。これはネットでも同じで、写真を削除してもその前に誰かが自分の端末に保存しているかもしれない。時代の変化で機械の性能、撮影・現像の仕方は変わったが、この不可逆性は今も続いている。
執筆に際して改めて鑑賞したのだが、わたしは被写体の娘ヴィオレッタ(つまりエヴァ)に共感しまくりの106分だった。わかる、わかると頷きながら彼女の凄まじい経験を追体験した。
というのも、数年前わたしは自分の写った写真数枚が掲載された写真集がわたしに無許可で販売されたことがある。販売後も撮った本人から連絡は来なかった。ネットでこの件を知って長い時間かなり憔悴していた。自分の姿を他者に所有され勝手に使用され、回収不可能な事実がこんなに傷つくものなのかと、この時初めて知った。
「私の作品は見た人の心にずっと残る それって何よりすごいことでしょ」
映画中盤、観覧車で語った母の顔をした写真家の言葉だ。これはわたしが作品を制作するモチベーションの一つでもある。自分が消えた後も誰かの心に残りたくて写真を撮っている。でも娘からするとこんなに残酷な真実はない。
絵画や彫刻ではモデルの姿は自ずと抽象化されるが、写真では目の前にあるモデルの姿がそのまま切り出されてしまう。だから写真に写った自分と、本物の自分が切っても切り離せない関係となる。それが見た人の心にずっと残ってしまうなんて。
母と娘の関係性

IMDbより
ついつい写真の話が多くなってしまったが、監督エヴァが最大のテーマとして置いたのは「母と娘」。この関係を無視して『ヴィオレッタ』に潜ることはできない。
二人の間にあったものは一体なんだったのだろう……。きっと愛の搾取だ。恐らく母はわかっていた、母親の愛に飢えた子どもが拒否するわけないと。娘は最初の撮影で体感してしまった、自分が被写体をする間は母親の関心がこちらに向くと。もともと希薄だった二人の親子関係は、皮肉にも写真を介して強く繋がってしまう。
ただ、搾取の登場人物は母と娘だけではない。幼い娘をヌードモデルとして搾取する母、を搾取する世間という、壮大な構造が成立している。
しかし母のアーティストとして大成したい、「母」や「誰かの恋人」ではない独立した「何者か」になりたいという強い意思は、同じ写真家、同じ女性として全く理解できないわけではない。むしろ最初に『ヴィオレッタ』を見た時、わたしは母の一直線な狂気にエネルギーさえ感じていた。
写真家として世間に認められるために娘を利用した反面で、ヌード表現に新たな可能性を見出し単純に探求したとも解釈できる。人を傷つけるアーティストを擁護はしないが、母から感じたアーティストの虚しさと愚かしさを、憎むことはできても一生忘れることはできないだろう。
母と娘の歪な関係はたとえば2020年の日本映画『MOTHER』に近い。世間的にアウトな関係を、本来ならば諭す親の不在。親自身が加害の立場であり、子どもはその加害性から自身の存在価値や親子の絆を実感し、それなしに生きてはいけない。
だがラストシーンでヴィオレッタひいてはエヴァは、自分に許しを乞うために訪れて来た母を避けて、全速力で遠くへと駆けていく。走り出した彼女は一度も振り返らない。母の呼び掛けも「愛してるの」も、彼女には届かない。いい終わり方だと思った。自分を傷つける人間から逃げ出すことは簡単じゃない。でも映像の中のヴィオレッタは最後にそれをやってのける。
関連記事
「描かない」ことで沈殿する MOTHER というテーマ|映画『MOTHER マザー』
撮られた自分を取り戻す
『ヴィオレッタ』の脚本と監督は娘エヴァ本人であることも、強調しておきたい。凄まじい過去を映像化するのは勇気のいる行為だったはず。
エヴァは大人になり、自分のことを自分で決定し管理できる人間となった。母にカメラを向けられていた時とは違う。当時は母と世間に搾取される側に立っていたエヴァだったが、この映画を制作することで彼女は幼かった頃の自分自身を取り戻したのではないだろうか。
出版した写真集や表紙を飾った雑誌などは、誰かの本棚やネットの海の中で半永久的に残るだろう。でも彼女の意思が反映された『ヴィオレッタ』が存在することで、彼女は自分の言葉で体験を語ることができる。起こった出来事は変えられないからこそ、自分で説明したかっただろう。
この「自分奪還作戦」は他の誰でもない、エヴァ本人が監督したからこそ成功した。人を撮るわたしにとって、映画『ヴィオレッタ』は一つの道しるべであり続けるだろう。
最後に:若い女性をモデルにしたポートレートやヌードを撮影している人たちへ。
健康で容姿が魅力的な、若い女性の身体美をテーマにしたヌード写真を否定したいわけではありません。わたしもそういう写真を撮っていたし、今も同年代の女性にモデルをお願いするときもあります。
しかし、写真家がそういった被写体を選択し、女性性を写した写真を生み出すことには大きな責任が伴います。
なぜなら、これまでの女性を性的に消費した写真(その中には被写体を無下に扱った写真もあるでしょう)を肯定するリスクを避けられないから。作品にちゃんとしたテーマがあったとしても、被写体との信頼関係があったとしても。
人を撮る時、ヌードを写真に収める時、わたしたちは正しく怖がりながら撮らなければならない。そして撮った後も考え続けなくてはいけない。一緒に考えていきましょう。
文・コムラマイ
写真を撮る人。フラスコ飯店 店主と同じ映画サークル出身。
サイトURL:
https://www.comuramai.com/

編集・川合裕之(店主)
フラスコ飯店の最新情報は、
当店のTwitter でチェックしてみてください。
上のイラストをクリックすると遷移します。
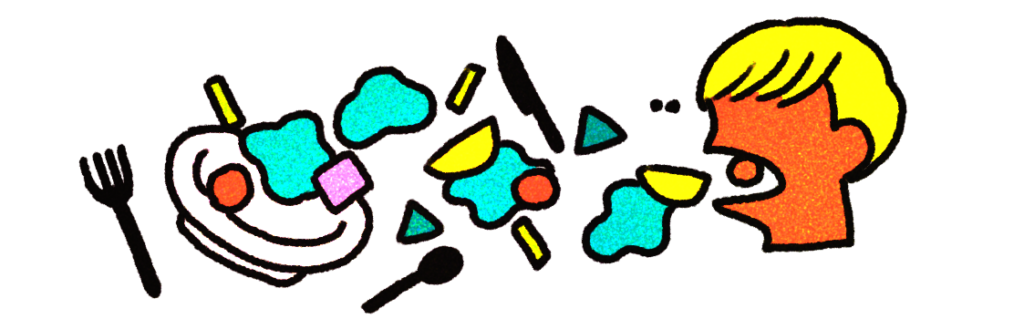
参考
・宮沢りえ『Santa Fe』秘話、「ヌードって聞いてなかった」
https://www.crank-in.net/news/38095/1
・E・イオネスコ、美少女A・バルトロメイを迎えた「ヴィオレッタ」でアートの限界を問う(映画com)
https://eiga.com/movie/57099/interview/
解説『ヴィオレッタ』(2011)

監督:
エヴァ・イオネスコ
出演:
イザベル・ユペール, アナマリア・ヴァルトロメイ, ドニ・ラヴァン ほか
監督のエヴァ・イオネスコの実体験ベースの劇映画。自身初の長編作品であり、第64回カンヌ国際映画祭にも出品された。
本稿でも触れられたが実話をもとにした創作物というメタ構造が強烈に存在する。たとえば日本の文芸で言うならば、村田沙耶香「コンビニ人間」や又吉直樹の「火花」、あるいは(又吉で思い出すが)太宰の諸作品群がそうだろうか。
皮肉なことに本作もまた児童ポルノに該当するのではないかと激しく議論された。以上の理由から、ヴィオレッタ役のアナマリア・ヴァルトロメイを「可愛い」と称賛することは気が引けるが、その美貌には舌を巻く。何レイヤーにも重なった抽象的対立構造に翻弄されながら自己をなんとか保とうとする思春期のナーバスさを巧みに表現している。彼女もまた「作家」のひとりだろう。いつしか彼女がこの映画に出演したときのことを映画にするかもしれない。そしてまたいつしか……。 (川合)

写真を撮る人・コムラマイの
映画レビュー
(C)山内マリコ/集英社・「あのこは貴族」製作委員会
|映画『あのこは貴族』”>どうしても比べてしまうわたしたちの、これからの選択|映画『あのこは貴族』
「あのこ」が誰なのか、映画がはじまるや否やわたしたちはすぐに察する。元旦の東京をタクシーで移動する彼女の身なり、運転手のどうでもいい話に返事をせず、かといって流れる夜景にも関心を示さない物憂げな表情。そして立派なホテルで豪華な食事を楽しむ彼女の家族を見て「このこが貴族」だと確信する。じゃあわたし(たち)はなんだろう。
映画『あのこは貴族』はあらゆる「対比」が散りばめられた作品であり、その対比はタイトルから既にはじまっている。家族との優雅な会食とそこでの話題、「おばあちゃま」呼びなどなど、わたしたち観客は華子との生まれ育ちの比較をせずにはいられない。
|映画『あのこは貴族』”>〈続きを読む〉

>はじめての絵画の歴史 ―「見る」「描く」「撮る」のひみつ―





