(C)2016「ディストラクション・ベイビーズ」製作委員会
意識を失って目覚めた時、冬の始発に充ちる空気のように頭が透き通っている感覚が忘れられない。山岳ベース事件を起こした連合赤軍の森恒夫が「自己批判」「総括」として他人に暴力を振るい、共産主義を盲目的に信奉する革命戦士として生まれ変わらせようとした契機は、自身が気絶した後に「生まれ変わったような心地がした」からであるらしい。
正直、分からなくもない。顎に足先が掠めただけなのに、いとも簡単に意識が攫われる。幼い頃から空手を習っていた自分にとって、暴力は隔日の夜に訪れる信仰対象のようなものだった。
意識を失えば
小学生の時分から無駄に体が大きかったせいで、いつも大人に混じって殴り合いをさせられていた。門を叩いたのはいわゆる「フルコンタクト」の流派で、道着を掴まない・顔面を殴らないという二点だけを守っていかに相手を叩きのめすかを教えるところだった。最初の半分は基本稽古。突きや蹴り、型を反復する。残りの半分は実践稽古で、ミットを殴りつけたり人を殴りつけたりする。
稽古に行くのが嫌で嫌で仕方がなかった。人にいかに痛みを与えるかのメソッドを週に三回教え込まれる。人間の急所の名称が昇級の筆記試験に出され、回し蹴りの威力を高めるために軸足を返し、砂の入った袋を殴り続けて拳を血だらけにして、身体を武器化する。
ミットを蹴る時にぱしん、と乾いた音が鳴ると、「まだ軽い。そんな蹴りじゃ相手の内臓を破壊できない」と師範代が言っていたことを覚えている。事実、彼の足がミットを蹴りつける時は、「ドッ」とか「ぼあぁん」とか、そんな重い音がした。いつ相手の内臓を破壊する必要に迫られるのかは、終ぞ聞くことができなかった。自分のものも他人のものも含めて、今のところはまだ一臓一腑も壊していないが、安心はできない。
中学に入って、道場にPという名前のアフリカ系の男性が入門してきてからはますます稽古が地獄と化した。彼の日本語は決して達者であるとは言い難く、「コンニチハ」と話しかけてくれるのはいいものの、最後は訛りの強い英語で何かまくしたててきて、一人で笑う。当時は(今もだが)英語がからきしだったので、自分も雰囲気でなんとなく笑っていた。
武道は素人らしかったが、組手(≒スパーリング。殴り合い。蹴りあい。喧嘩)を行おうものなら恵まれた体格と運動神経でもって道場を蹂躙するので恐ろしくて仕方がなかった。もちろんPは手加減してくれていたとは思う。が、Pがなんとなく差し出した拳が、まるでテトリスの青くて長い棒が予め組み立てられたスポットにすっぽりと収まるようにして自分の鳩尾にめり込んだ時、このままでは命が保たない、はっ倒されてしまうとはっきり思った。そうして、徐々に道場に行かなくなったのであった。
暴力のない世界で
道場から離れた瞬間に、身の回りから暴力がとんとなくなった。
通っていた中学校はそこそこ荒れていたようだが、自分が直接的に暴力を振るわれるようなことはなかったし、もちろん他校との喧嘩に巻き込まれるようなこともなかった。高校に進学するとさらに身近に暴力はなくなった。ここではテスト範囲の話と偏差値の話さえしておけば万事うまく行くようにできている。
告白するけれど、時折、暴力が恋しくなる瞬間があった。正直、今もある。誰かを殴ったり、殴られたり、したい。自分の身体の作用が相手にどう働くかを見たい。相手が腕を上げた瞬間に、脇腹に拳をめり込ませたい。自分が不用意に拳を下げた瞬間に、頰に足の甲を叩きつけてほしい。
もちろん、例えば恋人を暴力を振るったりだとか、酔って人と殴り合いをしたりした経験はない。これからもすることはないと信じたい。きっともう人に身体的に暴力を振るうことはないし、できないだろうと思う。振るわれることはあるかもしれないけれど。
『ディストラクション・ベイビーズ』、外側から至る
『ディストラクション・ベイビーズ』を観たのは2016年の秋だったと記憶している。
終わりの匂いがする港町で誰彼構わず喧嘩を吹っかける泰良(柳楽優弥)、その姿を見て感化され、彼の背後にくっついて回る裕也(菅田将暉)。泰良が暴力を振るい続けて世間の耳目を集め、当てもなくさまよう中で、不幸にもその旅に巻き込まれたキャバ嬢の那奈(小松菜奈)。
主演の柳楽優弥の視線が怖かった。その暴力に目的のようなものを見出せなかったからである。彼の視線が第四の壁を通して自分の眼を捉えた時、その「理解の及ばなさ」に背筋の凍る感覚がした。同時に、抗えない魅力のようなものも感じたのであった。
暴力を描きたかったのはすぐに言葉にできなかったからです。良くないというのは当然答えのひとつとしてあるかもしれませんけど、どうにも血が騒ぐのは否めない。暴力とはこうだと映画として答えを出すのではなく、見た人に疑問を投げかけることで終わりたいと考えていました。わかりやすい説明や辻褄合わせよりも、見た人が何を感じるのか。その余地は与えたかったところでした。
『ディストラクション・ベイビーズ』真利子哲也監督インタヴュー 「暴力を描くこと」
真利子監督はインタビューにこう語っている。そんな「言葉にできなさ」を表す好例として、とても好きな台詞がある。泰良と裕也が共に繁華街を練り歩き、三人の男性に喧嘩をふっかけるシーン。泰良に足を折られた不憫な男性1を見て、男性2が吐く呪詛のような台詞。
「なんでこんなことになるんや」
泰良が振るう暴力には理由がない。誰彼構わず・執拗に・喧嘩を吹っかける理解/ルールの外側に身を置く者(=アウトサイダー)としての泰良、その周りを小惑星のように回る那奈と裕也。一方は引力から逃れられず、不利益を被る人物。一方はその理解の外側に存在する強大な力を自らに取り込んだ気になっている小市民。
「虎の威を借る狐」ならぬ「柳楽優弥の衣を借る菅田将暉」といった風情で、劇中、裕也は泰良の服を着続ける。長きに渡る逃亡生活で身も心もぼろぼろになっても、彼のシャツをまとい続け、「理解できなさ」を「理解している」アティチュードを取る(晦渋な哲学書をファッション的に持つ人々のそれに似ている)。
けれど、それ以上に、泰良の暴力の在り方に人と人との繋がりへの欲求を感じた。序盤、彼は喧嘩相手に殴られ、蹴られ、そして毎回もつれあう。まるで抱き合うような形で。彼が持つ……そして持っているがゆえに世俗に疎まれてしまう……特性が言葉から離れ、唯一、他人と分かち合える地点。それが暴力であるのだと思う。
道場を辞めてから、一度だけPのことを見た。地元の夏祭りで、二の腕にタトゥーが入った外国人たちと一緒に大量の帽子を売りさばいていた。声を掛けようか迷ったが、「cap!アルヨ!カワナイ?ナンデ!?」と通行人に大声をあげる彼を見て、世の中には諦めなければならない何かがあると学んだのであった。
映画『ディストラクション・ベイビーズ』(2016年)

(C)2016「ディストラクション・ベイビーズ」製作委員会
監督:
真利子哲也
出演:
柳楽優弥, 菅田将暉, 小松菜奈, 村上虹郎 ほか
この連載では『溺れるナイフ』に引きつづき、菅田将暉&小松菜奈コンビの出演(たまたまです)。ただし、『溺れるナイフ』とは打って変わって、菅田将暉がなっっっっっっさけないクズ野郎の役でした。ちょんまげヘアーはすてきでしたが。
とにかく、柳楽優弥の怪物性が高く評価されている作品です。台詞は菅田将暉に三分の一、といったところなのですが、ちょっとした呻き声や仕草で「外側の人」感を出せるのがすごい。個人的には人の顔をしこたま殴った後、めくれあがった自分の拳を数秒間だけ見つめるシーンにいちばん「ヤバさ」を感じました。あの目はすごい。ぜひ観てください。

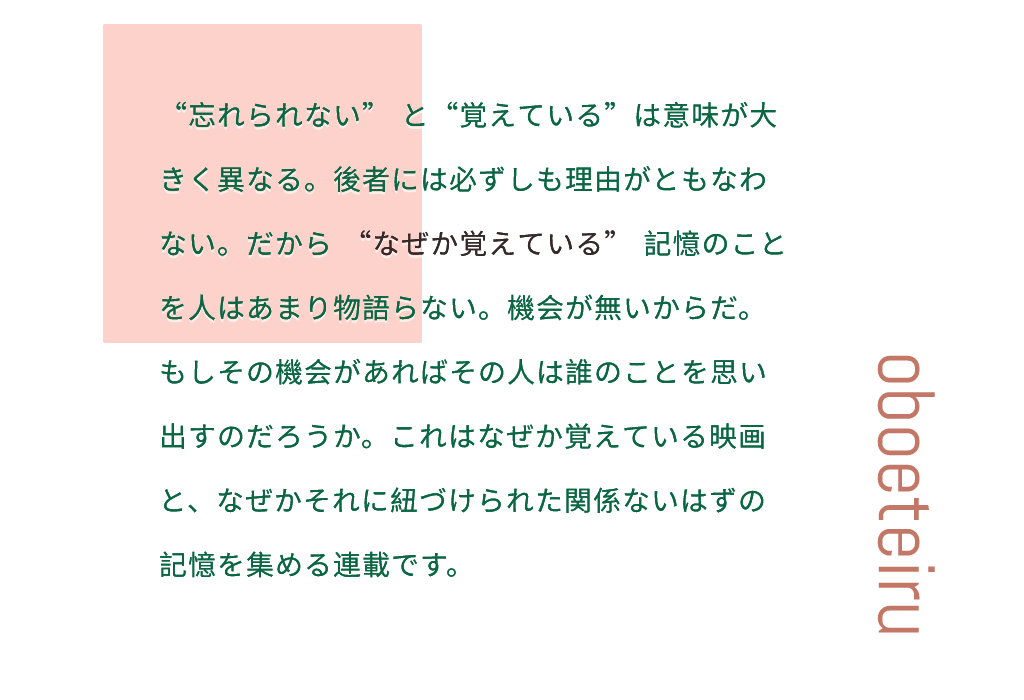
文・渡良瀬ニュータウン
編集・川合裕之(フラスコ飯店 店主)


