(C)2020「私をくいとめて」製作委員会
高校からの友人たちとオンライン飲みをしていたときだった。オンライン飲みあるある:終わり方がわからなくてずるずる長くやってしまう。あのときも床にあぐらをかいて座って腰を痛めながら、盛り上がりのピークも超えたのにゆるゆるとしゃべっていた。
最近見た映画の話になった。ちょうど1回目の緊急事態宣言が解除されて映画館の営業が再開したころで、ずっと期待していた『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』を映画館で見ることができて喜んでいた。
モニターには僕を含め4人の顔が写っている。男女2人ずつ。そのうち女性2人と僕の3人が『若草物語』を見ていた。「どうだった?」と問われた僕は、
「めっちゃおもしろかった。すごいアツかったよね」
と答えた。それを聞いた女性2人がどういう反応をしていたのか、僕はあまり覚えていない。仮想空間には共有できる空気はほとんどない。だから僕が覚えているのは僕の部屋の空気だけで、それは何かを避けて当たり障りのないことを言ったときの空気だった。でもその空気を覚えていることも忘れてしまっていた。

(c) 2020 Sony Pictures Digital Productions Inc.
2回目の緊急事態宣言が出る少し前、2021年の年明け早々に僕は『私をくいとめて』をひとりで見に行った。『勝手にふるえてろ』で綿矢りさ・大九明子タッグの衝撃を味わっていたから楽しみにしていたのだ。そして、やはり最高だった。アツくてグッときた。はあ〜、いい映画を見た。
感想を言語化するのには時間がかかる。あまりに早く言語化しすぎると、形にならない感情に言葉でふたをしてしまう感じがする、というのも聞いたことがあるしわかる。エモい・おいしい・オシャレはどれも、細かいふたで気持ちを固めるのを防ぐための、暫定的な大きいふたなのかもな、と思うことがある。
でも僕が使った大きなふた、「アツい」はどこからきたものだったのだろう。「アツい」という言葉を使うことで、何を避けたのだろう。何を語れなかったのだろう。
映画『私をくいとめて』と『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』を「アツい」物語として見た男性である僕の、〈語れなさ〉についてがんばって語ってみようと思う。
目次
・綿矢りさ×大九明子=
・理念と現実のあいだで叫ぶ
・その叫びを聞いている僕
・僕が語れなかった “何か”
綿矢りさ×大九明子=
映画『私をくいとめて』は主人公・黒田みつ子(のん)が食品サンプル作り体験をするシーンから始まる。みつ子はどうやら、会話をしている。相手は映らないが男性の声が応える。明かりが消えた暗い部屋に帰る。会話は続いている。明かりが点く。そこにはみつ子しかいない。
みつ子は脳内にいる自分の分身〈A〉と会話しているのだ。

(C)2020「私をくいとめて」製作委員会
原作・綿矢りさ×監督・大九明子。『勝手にふるえてろ』に続く2度目のタッグとなる本作は、前作同様、ひとりの女性の内側で渦巻く懊悩とその発露を描いている。綿矢りさの書く饒舌で瑞々しいモノローグが、大九監督の手によって映像的な語りへと変換されていく。
『私をくいとめて』においてその重要な装置となっているのは “音” だ。小説の場合、一人称のモノローグはそのまま、主人公の心情となり視点となる。映画ではそうはいかない。もちろん一人称映像(POV)作品も世の中には存在するが、多くは主人公をスクリーンのなかに映す、三人称的映像である。本作も同様。しかし、みつ子は脳内の〈A〉と会話する。〈A〉の声を観客に聞かせることで、三人称的だった映像を一人称的に見せることができる。映画冒頭のシークエンスは、〈A〉の種明かしと同時に映像の一人称化という機能を果たしているのだ。
〈A〉の声だけではない。テーマソングでもある大滝詠一「君は天然色」が鳴るシーンでは、その音響的な加工によってみつ子の開放感/閉塞感といった心情が表現される。多田くん(林遣都)がご飯をもらいにくるシーンでは「ワンッ」という犬の声が挿入される。非現実の音が、「この映像はみつ子の主観なのですよ」と教えてくれる。観客はそのおかげで、みつ子の内側に潜り込んでいけるのだ。大九監督は映画における音のユーモラスで効果的な使い方を熟知した作家なのだと思わされる。

(C)2020「私をくいとめて」製作委員会
関連記事:映画『劇場』論考_ 目を疑う / 視点 / 映画の2人称
映画における視点の描き方から、映画『劇場』の “あのラストシーン” を考えてみます。
理念と現実のあいだで叫ぶ
みつ子は「おひとりさま」として、自分のやりたいことをひとりで実現していく。食品サンプル作り、焼肉、日帰り温泉旅行。活き活きと楽しんでいる。ように見える。時折、街中で見かけるカップルや家族連れに、自分の不安を刺激される。でも大丈夫、ひとりでも楽しくやれる。私には〈A〉もいる。
大九監督は「おひとりさま」を肯定的に描く。綿矢りさとのダブルインタビューで次のように語った。
みつ子のことを大丈夫だと思いたい、とわたしは強く思いながら撮っていました。だって人はみんな、生まれながらのおひとりさまなんだよ、って考えているからです。ひとりで生まれてきて、ひとりで生きていて、誰かと過ごす時間もあるかもしれないけれど、そもそもひとりでいることは自然のことだし、かならずしも不幸な状態ではない。みつ子自身も、自分を惨めだとは思っていないし、思わないようにもしている。そういう人だと信じてつくっていました。
She is でのインタビューより
監督のこの精神は、みつ子と会社の先輩・ノゾミさん(臼田あさ美)の会話に表れている。
みつ子「でもやっぱりひとり落ち着くんですよー」
ノゾミさん「当たり前じゃん。人間なんてみんな、生まれながらのおひとりさまなんだよ? 誰かといるためには努力が必要なの!」
「誰かといることが、デフォルトじゃない」(インタビューより)。「おひとりさま」は楽しいし、楽だ。それをまずは肯定するのが大九監督なのだ。
ひとりで生きていくこと/生きてきたこと。近いテーマは『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』(以下『若草物語』)でも描かれている。

(c) 2020 Sony Pictures Digital Productions Inc.
主人公・ジョー(シアーシャ・ローナン)は作家になることを夢見ていた。姉のメグ(エマ・ワトソン)は美人で演技の才能があるものの、本人は安定した結婚を求めていたため役者を目指そうとはしなかった。姉のそのような姿勢や、父方の伯母(メリル・ストリープ)の「金持ちと結婚せよ」という声に触れながら、ジョーは女性が結婚なしに経済的に自立していくことが認められない社会に対する反抗的な情熱を高めていく。
男性と同じように女性も才能や野心を持っているのに、女性の生き方には結婚しか想定されないことに強く憤り、だからこそ自分は違う生き方を選びたいと思っている。自分は作家になり経済的に自立する。結婚だけが女性の幸せの形じゃない。だから結婚なんてしない。
みつ子の「おひとりさま」、ジョーの「経済的に自立した未婚女性」。社会に根強く流布する恋愛至上主義的あるいは経済的な、すなわち伝統的な結婚像に対するオルタナティブな理念を、どちらの作品も肯定的に提示している。
しかしそれだけではない。
それだけならば現実離れしたヒーローに見えてしまうかもしれない。この2作が理念だけでなく内側深く、現実の彼女たちの在り方にまで迫ることができているのは、彼女たちの実存的な葛藤を描いているからだ。つまり、理念だけでは乗り越えられない “さびしさ” と、どう折り合いをつけていくか、という問題である。(*)
*当然だが、ひとりでいることにさびしさを感じない人も現実に存在する。そういう人が「現実離れ」していると言いたいのではなく、あくまでもこの2作が理念を持ちながらも必ずしもそれに合致しない自らの実存を問う主人公を描いていることを論じたいのである。
みつ子は飛行機が苦手だ。結婚とともにイタリアに移住した友人・皐月(橋本愛)に誘われ、ひとりでの海外渡航を決行することにしたみつ子だったが、揺れる機内で呼吸ができなくなってしまう。脳内〈A〉と話すことで気を紛らわそうとするけれど、〈A〉は所詮、自分自身なのだ。音楽の力でなんとか乗り切るが、ひとりであることの心細さをひしと感じたことだろう。
ジョーも妹・ベス(エリザ・スカンレン)の死後、自分のなかにあるさびしさに気づく。自身の抱える深いさびしさを母(ローラ・ダーン)に打ち明けるシーンは、作品のひとつのクライマックスであろう。ジョーは理念と現実のあいだで揺れる懊悩を、静かな叫びにして発露する。
その叫びを聞いている僕
そう、叫びである。みつ子もジョーも、叫んでいる。
みつ子は2度叫んだ。1度目は日帰り温泉の際、旅館で催されたお笑いショーを見たあとだった。ピン芸人・吉住に酔っぱらった男性客が執拗に絡む姿を目撃したのだ。そしてそのセクハラ行為に、みつ子は怒りたかったのに怒れなかった。
この出来事が記憶のふたを開け、記憶から飛ばしていたイヤなことをずるずると思い出してしまう。上司からのセクハラ、それをやりすごしたことに対する女性の先輩の嫌味。そのときはノゾミさんが「大丈夫?」と声をかけてくれたから何とかなった。それなのに自分は吉住に何もしてあげられなかった……。
苦しいよ、A。
もう一度はラスト近く。多田くんとお出かけした帰り道、突然の雪のせいでホテルに泊まることになったものの、距離の取り方がわからず取り乱してしまう。好きだけど、不安だし怖くてたまらない。こんなことなら「おひとりさま」のほうが楽だった。
いまはとにかく逃げたい!!!
みつ子にとって「おひとりさま」は自由な自分であると同時に、さびしさを乗り越えるハードルの高さと向き合わないための方便でもあった。
みつ子、ジョーの叫びは苦しくも、熱量を持ったものに僕には聞こえた。現実を生きる女性たちの苦しみや悩みがこもったその叫びの「アツさ」にグッときた。
でもこの「アツさ」、そして僕が「アツく感じること」って何なのか。「すごいアツかったよね」と大きなふたで感想を閉じ込めるとき、言葉にされず気づかれなかった感情はどんなものだったのだろう。ふたを開けなければならないときがきた。
僕が語れなかった “何か”
僕が「すごいアツかったよね」と言ったオンライン飲みの数ヶ月後、あのときの友人のうちのひとりと『若草物語』について再度話すタイミングがあった。彼女は僕にこういった。
あの感想を聞いて、〇〇くんでもやっぱり、当事者として見るわけじゃないんだって思った。
衝撃だった。何がって、本当にそうだと思ったし、そのことに自分で気づいていなかったのだ。僕は自分の知らないうちに〈男性として〉あの映画を見ていたのだ。
当たり前のように聞こえるかもしれない。でも僕はショックだった。僕は自分のことを男性性の強い男性だと認識していない。昔から筋肉がつきにくく華奢で、体毛も濃い方ではない。ホモソーシャルでマッチョな体育会系のノリは苦手だったし、バカにすらしていた。その程度のことだけど、男性のなかでは男性性がそれほど強くないタイプだと自認していたし、そこに少なからずコンプレックスを持っているとも思う。
だからこそ、自分が無自覚に〈男性として〉フィクションを享受していたことにショックを感じたのだ。
僕が先に挙げた2作の叫びのシーン、特にジョーのさびしさに対する叫びとみつ子のイヤな思い出に対する苦しみの叫びは、ともに彼女たちが〈女性として〉発さざるを得なかった叫びだ。だからこそ、僕がそれを聞いて「アツく」感じるのは、僕が〈男性として〉聞いているからだということが浮き彫りになる。
「アツく」感じるということは、それに「外から」触れているということ。同じ温度を僕が持っていれば「アツく」なんて感じない。あくまでも外から、低い温度で。要は「他人事」だと思っているのだ。そのことに無自覚なまま「アツくてグッときた」と言ってのけることの暴力性。感想=感情を押し込めないための暫定的な大きいふたなんかじゃない。彼女たちを自分の側にいないものとして線引きする態度だったのだ。
もちろん映画や小説などのフィクションを、登場人物に感情移入しながら受け取らなければならないなんてことはない。僕自身はむしろ、感情移入とその先にある共感を、フィクションの至上価値だと考えることには反対だ。自分が感情移入しやすい人物が描かれるかどうかがものさしになってしまうからだ。そういう意味では、僕がみつ子とジョーに対して過剰に感情移入せずに見たことは、非難されるべきことではない。これは強調しておくべきことである。
関連記事:簡単に「共感」してくれるな|又吉直樹『劇場』
又吉直樹の小説『劇場』について、小説における視点の問題と、共感至上主義へのアンチテーゼとしての「共感できなさ」から考える書評。フィクションと感情移入についての筆者の捉え方を明確に表した記事です。
だがしかし、僕にとってはそれだけではすまされないタイミングだった、特に『若草物語』の場合は。なぜなら今回のリメイクは、グレタ・ガーウィグという女性監督による現代的な翻案であることが前評判として広く知られていたからだ。もちろんその現代性にはフェミニズム的視点が大いに含まれている。そのことをわかったうえで僕は興味を持ち、作品を受け取った。それなのに、というところがポイントなのだ。
それなのに僕は、男性である自分が〈男性として〉作品を受け取っている/受け取ったということに無自覚だった、ということがショックだったのだ。

(c) 2020 Sony Pictures Digital Productions Inc.
冒頭でも書いたが、僕は「アツくてグッときた」という感想を発したとき、自分が何かを避けて当たり障りのない言い方をした気がしていた。もしかしたらそのときは意識にはっきりと上っていたわけではなかったが、自分が〈男性として〉見たことにうっすら気づいていたのかもしれない。
では何を避けようとしたのだろう。いま振り返って考えてみると、叫びについて当事者として語れない、非当事者の〈語れなさ〉だったのだと思う。
ここには僕の2つの〈語れなさ〉がある。女性の〈女性として〉の語りに対する非当事者性、そして男性の〈男性として〉の語りの貧困さである。
彼女たちの叫びには女性たちの苦しみが明確に描かれている、そのこと自体は痛いほどわかるし、そのうらにある構造についても少しは理解しているつもりだった。でも彼女たちの痛みを自分で感じることはできない。「痛がっている!」とは言えても、「痛い!」と自分で叫ぶことはできない。
じゃあ男性である僕はどう語れるのだろう。この〈語れなさ〉に向き合うには、ひどくエネルギーを要する。僕はそこに僕の〈語れなさ〉があると心の奥のほうではわかっていたが、だからこそ直面することを避けたのだと思う。
これら2つの〈語れなさ〉について、微力ながら検討してみたいと思う。
非当事者としての男性の〈語れなさ〉
まずは1つめ、男性が抱える、フェミニズム=女性の〈女性として〉の語りに対する非当事者としての〈語れなさ〉について。
女性たちはフェミニズムを通して自分たちの経験の語り方を “獲得” していった。「ガラスの天井」や「セクハラ」といった、いまや聞き馴染みのある言葉も、女性が自らの経験を語るために生み出したものだった。男性優位の社会で語る機会すら与えられなかったところから、苦心して語り方を手にしていったのだ。
だから男性にとって、フェミニズムを当事者として語ることには困難が含まれている。女性が自らの経験を語るために獲得した言葉の当事者性を、〈女性として〉の経験の当事者ではない男性が語ることは、当事者性の横領になりかねない。
僕がみつ子やジョーの叫びの痛みを感じながらも、それについて語る言葉を持っていないと感じた理由はここにあった。無自覚であったとはいえ、僕は〈男性として〉彼女たちの叫びを聞いていた。だからこそ叫びの当事者としてその痛みを語ることはできないと感じていたのだ。それはそれでひとまずは必要な感じ方であるようにも思う、安易な横領を避けるために。
でもだからといって、無関係な立場として非当事者であり続けることはもっと許されないだろう。なぜなら「フェミニズム=女性の問題」という図式はそもそも間違っているからだ。
恋バナ収集ユニット「桃田商事」代表で、近年はその経験を踏まえ特に男性ジェンダー問題について文筆活動を精力的に行っている清田隆之は、いわゆる “男性特権” について次のように語っている。
男性が「男性である」だけで与えられている “特権” は確実にあって、それは「考えなくても済む」「なんとなく許されている」「そういうことになっている」といったかたちで我々のまわりに漂っている。だから多くの場合、それが特権であることに気づかない。
『さよなら、俺たち』10頁
“特権” という言葉が強いものであるために、「そんなものを俺たちは持っていないし感じていない」という反応になってしまいがちだが、実際には清田の言うように、「何かをしないことを許されている」という形で現れているのだと思う。
フェミニズムによって発露される女性の〈女性として〉の苦しみを男性が当事者として語ることの難しさはあるし、当事者性を横領するのもいけないことだが、だからといって「フェミニズムは女性のもの、女性が頑張ればいいもので男性には関係ない」という態度は、まさに “男性特権” の顕現である。どうして女性たちが語り方を獲得しなければならなかったのか。そこに男性の責任がないはずがない。ありすぎるほどあるだろう。自分が男性であることを「考えなくても済む」という態度が許されていたというだけでも、無関係なものではありえない。
それならば、「無関係という意味ではない非当事者」、いや、「〈語れなさ〉を抱える当事者」としての関わり方があるはずだ。フェミニズムが男性の問題である限り、男性もフェミニズムについて語れなければならない。
そのための第一歩として、男性が〈男性として〉の経験を語るすべを手に入れていくことについて次節では検討しよう。
〈男性として〉語るために
女性は〈女性として〉の経験を語る言葉を苦心して獲得していった。男性はどうか。男性は〈男性として〉の経験の語り方を獲得しなければならない、という要請を自らのうちに感じとることなく歴史を歩んできた。人間を意味する man という単語が同時に男性を意味するように、男性は〈男性として〉ではなく〈人間として〉語ってきたからだ。
ここにも “男性特権” が現れている。〈男性として〉の経験を語ることの困難とその乗り越えの必要性について「考えなくても済んだ」のだ。わざわざ語り方を獲得せずとも語れたのだ。
もちろんこの問題意識は男性たちのなかにも生まれた。男性学やメンズリブという運動がそうだ。これらは女性学やウーマンリブという運動を受けて、その反応として結実していった。その成果も少しずつ蓄積されつつあるが、まだまだ十分とは言えないし、フェミニズムについて語りたい、語らなければならないと思っても、自分には語れないと感じる男性も多いだろう。
そのような状況のなかで、正反対のリアクションも目につくようになってきている。それは「アンチフェミニズム」と結びつく形でよく現れる「弱者男性論」だ。
Twitter を中心に、フェミニズムをよく思わない人たち=「アンチフェミ」の言葉を目にすることは多いのではないだろうか。そのなかには女性もいるが、男性、特に「弱者男性」を自認する人たちも多く存在するようだ。
批評家の杉田俊介は「弱者男性」について、彼らがどのような意味において「弱者」であるのかの基準ははっきりせず、経済やルッキズム、さらには発達障害などさまざまな問題が絡み合っていることを指摘したうえで、次のように述べる。
女性や性的少数者よりもマジョリティの男性(の中の弱者)の方がいっそう不幸であり、真の被害者は弱者男性であり、国家や社会からの制度的支援が何もない――というように、弱者男性論は個々人の実存の話から制度の話になっていく。
文春オンラインより
“男性特権” なるものの加害性が叫ばれるなかで、マジョリティ男性でありつつもその “特権” に与かることもできずにつらい思いをしている。それが「弱者男性」だ。ある意味では、これも男性が〈男性として〉の経験、そのつらさを語る言葉になっていると言えるだろう。
杉田はつらさを理解して欲しいという根本の願い自体は絶対的に肯定されるべきであると述べるが、しかし同時に、フェミニズムによって男性が「強者」と名指されたことに対する ”リアクション” として「弱者男性」という概念を打ち出してしまうと、その先には「貧しい選択肢しかない、と感じられてしまう」と杉田は問題視している。
ここには、どうしても、いったん、「弱者男性」とは異なる概念が必要なのではないだろうか。「弱者」という言葉が、すでに、アンチフェミニズムやアンチリベラルを強く含意してしまうからである。
文春オンラインより
アンチフェミニズムやアンチリベラルへと向かう欲望を切断して(「あっちが批判してきたから言い返しているだけだ」という被害者意識を断ち切って)、「弱者男性」の問題を再定義できないだろうか。
もちろん「弱者男性」たちが主にネット上で集団的な攻撃性を発揮してきた、という文脈や歴史はすでに消し去ることができないとしても、そうした攻撃性から身を引き剥がそうとする当事者性を帯びた「弱者男性」の概念が再構築されてもいいだろう。
男性が〈男性として〉経験するつらさや戸惑いや取り乱しを、否定するのでも、被害者意識を感じるのでも、そして他者≒女性から承認してもらうのでもなく、自ら語り直すための言葉を手に入れる必要がある。杉田は男性学やメンズリブがフェミニズムやウーマンリブを受けての反応であったことを踏まえ、「弱者男性論もまたリアクションではなく、積極的なアクションとして再設定すべきではないか」と提起を行なっている。
そのためのまず第一歩はおそらく、現時点で男性が〈男性として〉の経験を語るための言葉を十分に手にしていないこと=男性の〈語れなさ〉を認めることなのではないだろうか。僕たち男性は、フェミニズムはおろか男性問題についてもいまだ十分には語れないままなのだ。男性問題の顕著な現れとしての「弱者男性論」について新たな語り方を獲得することは、男性が〈男性として〉フェミニズムを語るための土台となるのではないだろうか。
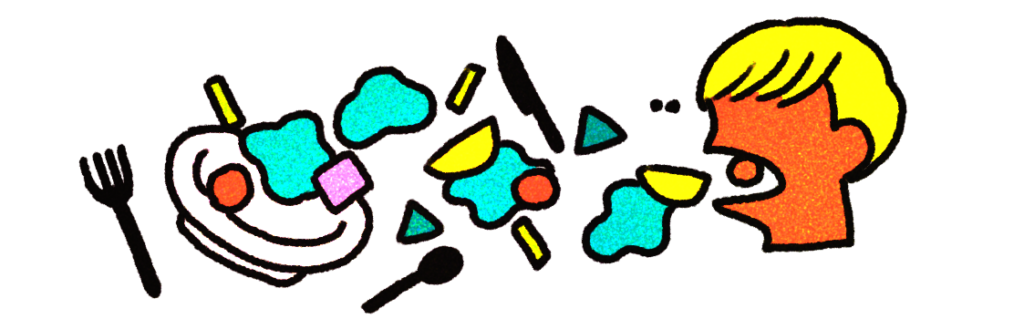
みつ子やジョーの叫びを聞いて僕が「アツく」感じたうらには、僕の抱える〈語れなさ〉があった。フェミニズムは女性の問題ではなく男性の問題でもある。それなのにフェミニズムについて語る権利を自分が持っている気がしない。それは多分に正しいところがあって、なぜならいま流通しているフェミニズムの言葉の多くは、女性たちが自分たちのために獲得してきた言葉だからだ。僕の心には、叫べることへの羨ましさもあったと思う。だから「アツく」感じたのだ。
女性問題とイコールを結ぶものではないフェミニズムについては、男性も語れなければならない。でもまだその語り方は獲得されていないし、その獲得は、男性たちが自ら成し遂げなければならないことである。男性問題について語る言葉すらまだぎこちない僕たちだが、積極的なアクションとして語りを実践する先に、僕たちの叫びを見つけていきたいし、見つけなければならないのだろう。同じ温度を、違う形で手に入れなければならないのだ。
最後に、この記事で男女二元論的にしか議論できていないことも、僕自身の現時点の限界点だと記しておかなければならない。
文・安尾日向
編集・和島咲藍
参考文献
She is 「綿矢りさ×大九明子対談『誰かと生きることはデフォルトじゃない』」
清田隆之『さよなら、俺たち』スタンド・ブックス、2020
杉田俊介「『真の弱者は男性』『女性をあてがえ』…ネットで盛り上がる『弱者男性』論は差別的か?」文春オンライン
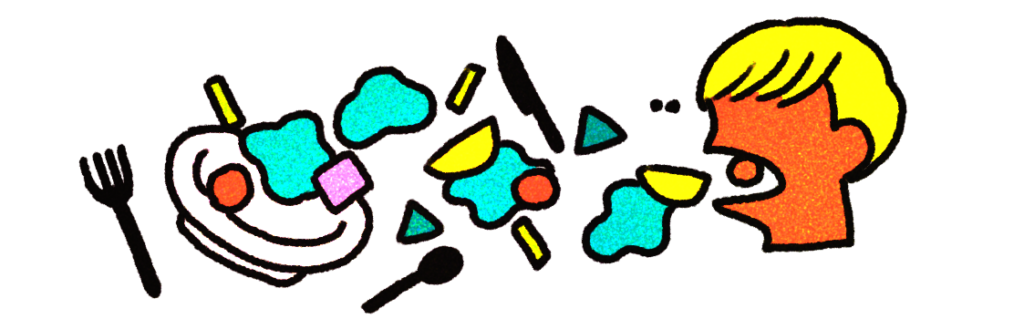
フラスコ飯店の最新の更新をチェックしてみてください!
上のイラストをクリックすると遷移します!
映画『私をくいとめて』(2020)

監督:
大九明子
原作:
綿矢りさ『私をくいとめて』(文春文庫)
出演:
のん、林遣都、橋本愛、臼田あさ美、片桐はいり、前野朋哉、中村倫也など
映画『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』(2020)
監督:
グレタ・ガーウィグ
出演:
シアーシャ・ローナン、エマ・ワトソン、フローレンス・ピュー、エリザ・スカンレン、ローラ・ダーン、ティモシー・シャラメ、メリル・ストリープなど
感情を押し込める男性性
(C)2019 Columbia Pictures Industries, Inc. and Tencent Pictures (USA) LLC.
Don’t Boys Cry?〈対話〉による男性性の克服|映画『幸せへのまわり道』
〈Boys Don’t Cry〉=男の子は泣かない。
映画『幸せへのまわり道』は、この〈Boys Don’t Cry〉という規範に対し、傍らに座ってやさしく目を合わせて〈対話〉を求める作品だ。




