社会学者が「小説」を書いたらどうなるのか。他者との交わりと自己への内省が同居するこの岸政彦の小説を、自身も社会学を学んでいるライターの安尾日向が語ります。
思い出すこと
自分の一番古い記憶ってなんだろう、と考えてみる。
4歳のとき、もうすぐ生まれてくる妹を、わくわくしながら待っていた病院の廊下の景色だろうか。それともそのもう少し前、幼稚園の入園式の日に、制服を着るのが急に嫌になって、押入れの一番上に登って籠城したときの、少し高いところから見下ろした居間の景色だろうか。
どちらのイメージも、思い出した端から綻びていく淡いものだ。これらは記憶と呼べるのだろうか? 自分が本当にこの目で見たものだという自信は少しもない。印象的なこれらのシーンは、あとになってから家族に聞かされた話を、頭のなかで想像し、再現したイメージに過ぎないのかもしれない。

http://sociologbook.net/wp-content/uploads/2018/08/63330010.jpg
岸政彦の新刊『図書室』は、「記憶」についての物語である。ある女性が子どものころを想起する表題小説「図書室」と、著者が出会った大阪という町を書く自伝エッセイ「給水塔」の二編が収められている。どちらも、「いま」から「過去」を振り返り、「そこにいた」人たちや「そこにあった」できごとの存在をたしかめようとしている。「記憶」を呼び起こし、過去を思い出すという営み自体を描いている、とも言えるのではないだろうか。
表題作「図書室」は、子どものころの象徴的な体験を色鮮やかに描いていて、強く胸にせまってくる。
私と少年は、たしかにその図書室にいた
「図書室」の語り手である <私> は、大阪の古い団地でひとりぐらしをしている女性だ。彼女はある雨の日、ぼんやりと子どものころのことを思い出す。猫のこと、母のこと。母と猫と暮らした小さな長屋のこと。ひとりで通った、近所の公民館の図書室のこと。そしてそこで出会ったひとりの少年のこと。
<私> はいま50歳で、そこから推察すれば、記憶の舞台となるのはおそらく1970〜80年代。当時の大阪の町の姿とともに、彼女の記憶が辿られていく。
それにしても、どうして最近はこうも、子どものころのことばかり思い出すんだろう。
22頁
彼女はこれまでの人生で思い出してこなかったことが、いまになって浮かんでくるようになったという。彼女が語る幼少の記憶は鮮明で、においや手触りのような感覚的イメージまでもをありありと呼び起こしている。そして図書室で会った少年との会話も、まるで昨日のことのようにはっきりと思い出している。
「あそこに餃子屋あるやんか。ひなた商店街の入り口のとこ」
(51-52頁)
「あー。うーん、駅のあっち側あんまり知らんねん。僕とこ反対側やから」
「あ、そうか。ほなどこで餃子食べるん?」
「餃子あんまり食べへんな。焼売の方が好きやな。でも焼売もそない食べへんかも」
「ほな何食べてんの」
「何て。ふつう。カレーとか」
「きのうカレーやったわ」
屈託のない大阪弁で話される、なんてことないふつうの会話。どちらかといえば、くだらなくさえある。読者であるわたしたちは、しかし、これらのしょうもない会話を頭のなかで再現することで、 <私> と少年が「そこにいた」ことを感じる。

http://sociologbook.net/wp-content/uploads/2019/05/31200002.jpg
社会学者・岸政彦の「他者理解」への思い
誰かが「そこにいた」ことがとてもリアルに描かれているのが、「図書室」の特筆すべき点だろう。これはたまたまそうだったわけではなく、「小説なんだから当たり前だろう」という話でもないと思う。著者である岸政彦の本業が、社会学者であることにこそ、その理由があるのだ。
社会学者としての岸の専門は沖縄についての研究で、おもに生活史の聞き取りという方法で調査・研究している。現在もっとも精力的に活動している社会学者の一人だ。2019年現在は立命館大学大学院先端総合学術研究科で教授を務めている。
生活史の聞き取りは、ある個人のそれまでの人生(=生活史)を本人に語ってもらう、インタビュー形式で行われる調査だ。対象となる個人はさまざまだが、LGBTQや被差別部落の出身者などの社会問題や歴史的事件の当事者や関係者、いわゆる「マイノリティ」の人々が対象となることが多い。マイノリティは、マジョリティにとって「他者」である。では「他者」を「理解する」ということを、社会学者の岸はどのように考えているのだろうか。以下は、岸が書いた社会調査の教科書からの引用である。
私たちは、他者を「完全に」理解することは絶対にできません。そもそも私たちは、自分自身でさえちゃんと理解できているかどうかもたしかではありません。まして、なんらかの差別や暴力を受けている当事者や、私たちが普段あまり接することのないような人びとのことを、軽々しく理解できると考えてはいけません。
[……]他者を軽々しく理解しようとするのは、暴力です。たとえば、深刻な差別や暴力、あるいは大きな事件や事故の被害にあった人びとが、どれほど辛い思いをしたか、どれほど「しんどい」毎日を送っているか、ということは、私たちマジョリティには計り知ることができません。それを簡単に「わかった」と言ってしまうのは、とても暴力的なことです。
しかし同時にまた、私たちは私たちの隣にいる「他者」の人びとを、なんとかして理解しようとする営みをあきらめてしまってはいけません。
『質的社会調査の方法』序章 32頁
岸は、社会学研究における調査、特に彼自身が行っている生活史の聞き取りという調査を、「他者」を「なんとかして理解しようとする」営みだと捉えている。「完全に」理解することはできないし、できると思っては傲慢だが、理解しようと努める姿勢が求められるのだ。
これはマイノリティに限らず、誰に対してもあてはまることだ。たまたま電車で乗り合わせた隣のおじさんにも、その人の人生があり、あらゆる過去を背負って、いまも生きている。彼の人生を完全に理解することはできない。ましてや、電車に乗り合わせただけの人にいちいち話を聞くなんてことはできない。でもだからといって、理解すべき何かがあることを理解しようとすることを放棄してはいけないのだ。理解を放棄することは、その人の人間としての生を軽視することだ。私たちは、そんな当たり前のことを忘れて生きている。
生活史を調査すること、生活史を読むことは、他者が「そこにいた」ということを教えてくれる。しかし、ただの文字の羅列に、その存在のリアリティは、簡単には込もらない。
生活史の記述は、けっしてキレイにまとまったものではなく、矛盾や文法のねじれもあり、むしろ読みにくくさえある。でもそのちぐはぐさから、徐々に「その人」を感じていく。人の生活は、ねじれのないスッキリまとまったものではありえない。あっちに行ったりこっちに行ったり、矛盾を孕みながら進んでいく。人生はちぐはぐなものだから、その語りも当然ちぐはぐなものになる。でもだからこそ、誰かの人生を感じるのだ。生活史を読むことはそのような営みなのだ。
「図書室」はフィクションの小説だから、生活史のようにちぐはぐではない。スッキリ、キレイにまとまっているようにも見える(それだけではないところもこの作品の魅力なのだが)。しかし小説を読むことも、誰かの「人生の断片」を見せてもらうことには変わりない。「図書室」における<私>の語りには、生活史に似たリアリティがある。
どうしてなのか。それは社会学者でもある著者の、「他者の人生を理解しようとすること」や「他者の実在のリアリティ」への思い入れが、この小説にも表れているからだ。起承転結にまとまることのない、行ったり来たりの人生を、作品のなかで閉じない。彼女の人生は、作品で語られる部分より前があって、その後もいまも続いていく。そういう当たり前の人生を真摯に描き出そうとしている。
だからこそ、彼女がいま「そこにいる」こと、彼女が、猫たちが、少年が、かつて「そこにいた」、いや、「そこにおった」ことを強く感じられるのだ。「記憶」の語りを通して彼女たちの存在を感じていくことが、この小説の醍醐味だろう。

思い出せないこと/思い出さないこと
ここまででブックレビューとしては十分だろう。だけどどうしても書いておきたいことがもう少しだけある。ここからは余談だと思ってください。
「思い出せないこと」と「思い出さないこと」は違う、というお話を最後に。

http://sociologbook.net/wp-content/uploads/2019/05/31200019.jpg
「図書室」の <私> はよくもあれほどまで詳細に、子どものころのできごとを覚えているものだ(もちろんフィクションだからなのだけど)。「あのときの誰々との会話」なんて、僕は思い出そうとしても思い出せない。たくさんのくだらなくも愛おしい会話が、僕の過去にもあったはずだ。だけどそれらは目の前を流れていって、遠くに過ぎ去り、忘れてしまった。
「そこにあった」ものごとは、忘れてしまい、思い出せなくなったら、どうなるのだろう? そもそもなかったのと同じになってしまうのだろうか。それはとても悲しいことのように思う。
……いやちょっと待てよ。思い出そうとするかどうか、その選別が実際の想起に先んじてあるじゃないか。「思い出せないこと」の背後には、思い出せないことにさえ気づかないこと、思い出そうとさえしないことが、もっとたくさん存在していたはずだ。「忘れてしまったな」とさえ思ってもらえないものごとが、そこにはたしかにあったのだ。
私たちはたくさんの「思い出」を抱えながら生きている。その背後にはもっとたくさんの「思い出せないこと」、もっともっとたくさんの「思い出さないこと」がある。それら全ての上に立って、いま「ここにいる」。「いま・ここ」を通り過ぎていくあらゆるものごとも、いつかは忘れてしまうだろう。それでもできるだけ目を向けていかなければ、と思う。「そこにある」への理解を放棄してはならない。その営みの積み重ねが、僕の、あなたの、「存在」を作っていくのだから。
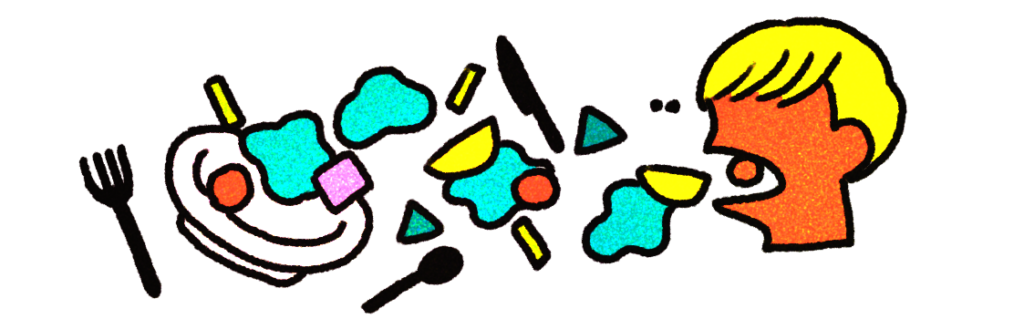
文・安尾日向
編集・川合裕之
なお、記事中の写真は岸政彦さんのブログからお借りしています。ほかにもたくさんの写真が掲載されていますので、ぜひそちらもご覧になってください。
■あわせて読みたい本
外国籍のゲイ、トランスジェンダー、摂食障害、シングルマザーの風俗嬢、元ホームレスのおっちゃんという5人の生活史の語りが収録されている。生活史というもののちぐはぐさとリアリティを感じられる。
調査のなかで出会った、調査には使えないけれど、著者の心を捕らえて離さない断片的なできごとやエピソードについて書かれた本。この本の、かけがえのないものについて書いた「誰にも隠されていないが、誰の目にも触れない」という章は必読。
芥川賞・三島賞の候補になった作品。こちらもいろんな人の「人生の断片」を描いている。『図書室』より曖昧な描かれ方をしているところが面白い。
「変わっていくのなら 全て見ておきたい/居なくなるのなら 居た事を知りたい」 藤くんはいつだって、いつかはいなくなってしまうことを考えずにはいられない。この曲も子どものころの思い出と喪失を当たり前のように並べて歌う。
関連:わたしがグダグダうじうじしていることは大抵すでに藤原基央が曲にしている








