この記事には映画『パラサイト 半地下の家族』についてあらすじ程度のネタバレが含まれています。ご注意ください。
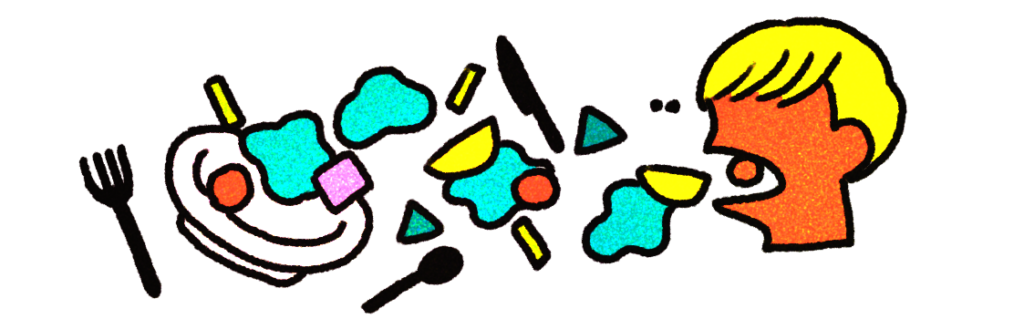
映画『パラサイト 半地下の家族』の後半における激しい滝のような展開と、溺れるような苦しい結末はポン・ジュノ監督作の中でも屈指のものでした。
しかしふと、ある疑惑に直面します。あれはハッピーエンドなのでは?
「騒動のあと、父親は地下室で暮らすことになる」というあの結末は “ある意味での” ハッピーエンドなのではないかと筆者には思えてきたのです。というのも、ソン・ガンホが演じた父親にとってのみ幸福なラストであり、そしてこのこと自体――つまり彼にとって好ましい幕引きであったという事実それそのもの――が悲劇なのだと僕は考えました。
視覚的なアプローチで上下を訴える

(C)2019 CJ ENM CORPORATION, BARUNSON E&A ALL RIGHTS RESERVED
前提として、この映画は「上下が明確な舞台」を使用しているということをお伝えしましょう。すでに古今東西プロアマ問わず誰もが指摘していることですが、やはり皆が指摘するほど露骨に描かれているのにはやはり理由があるのです。結論まで少し回り道になりますが、無駄にはさせません、どうかお付き合いください。
上下関係の可視化
この映画では「上流階級と貧困層」の対立項と、「丘の上の豪邸と半地下の棲家」という対立項とがパラレルになっているのです。同じ家の中で「上流層」と「貧困層」が同時に存在するシーンにおいても、フレーム内で上下が再生産されることがしばしば。
これにより無意識に、視覚的に、そして具体的に階級の差が観客に伝わります。
均された階級を炙りだす
「貧困」と耳にするとボロボロの服を身にまとった垢だらけの姿を想像するかもしれませんが、実際の世界はそうではありません。「普通の」格好をしている可能性の方が高いでしょう。さらにくわえて、今回の「貧乏人が金持ちの家にパラサイトする」という設定ならば、貧乏家族の側だって着る服もある程度は工夫しますよね。実際、汚い部屋着で出勤するわけにはいきません。
あのストーリーでは同じ空間に異なる階級の人が存在していてもストーリー以外のものから見分けるのは困難です。小道具も、そして背景の空間も同じものを共有しているのですから。
こうした隠された貧困を炙りだすのが「上下」の表現。ほかに「匂い」を媒介にする場面もありましたが、2D映画では伝わらないので台詞で伝えるほかありません。
以上のように、この映画では「目に見えない貧富の差が、視覚的に表現されている」のです。ここまでは多くの方が指摘しているのと同じです。
そもそも
なぜ強い者は
高い場所にいるのか
このような「上下」はしばしば映画で用いられる表現ですが、いったい何故なのでしょうか。問いの答えは簡単です。そもそも権力者は古来より高い場所に陣取るものなのです。
権力者は敵に攻められないように、安全な場所を選びます。せっかく観光でお城を見たいのに、坂や階段が多くてなかなかたどり着けないのはこのためです。「あ~あ!お城にエスカレーターがあれば攻め落としやすいのにな!」と思っていたら大阪城にはエスカレーターが本当に付いちゃいましたが。
権力者は安全な場所に。タクシーの「上座」(誰かが決めた阿保らしいマナーです)も助手席ではなく運転席の後ろとされていますが、その理由をご存知ですか? 交通事故の際に安全だからだそうです。阿保ですね。
くどいくらいに繰り返しますが、優位な人間ほど安全なところにいるのです。
「安全ルール」を適用してみる
逆を返せば安全なところに居る人間ほど優位だということです。
さて、話を映画『パラサイト』に戻しましょう。
ソン・ガンホの演じる父親ギテクは、最後には豪邸に隠された秘密の地下室での生活をすることになります。楽しかった生活に終止符が打たれ、殺人までも犯してしまった彼は、孤立したまま社会から姿を消すのです。父を助けるにはあの豪邸を買い取るしかありませんが、そんな希望もありません。
なんとも悲しいラストです。しかし、ここで先述した「安全なところに居る人間ほど優位」という「安全ルール」を適用してみましょう。すると見え方が変わってきます。この状況は父親にとっては紛れもないハッピーエンドなのです。
物理的な安全
「あの秘密の地下室」は、核シェルターとして作られました。理論上、核爆弾が来たとしても安全な場所なのです。物理的にギテクは誰よりも安全なのです。そして彼は今や殺人犯として指名手配されている身です。誰にも存在を知られていない地下室に隠れている限りは捕まる心配もありません。
権力構造からの「イチ抜け」
ギテクは地下室に隠れている限りは生命を保証され、逮捕されることもありません。極めて安全です。安全であるならば、優位でなければいけません。安全なのはともかくとして、彼は安全に見合うほどの「優位」を兼ね備えているのでしょうか。
この視点で考えてみると、たしかに彼は優位なのです。というのも、彼は社会の権力構造から「イチ抜け」しています。社会から隔離された地下空間において、貧富の差は存在しないのです。
それまでのシーケンスでは身分を偽り周囲を騙して仕事をしているので、ギテクらはお金持ちのパク家の人たちを出し抜いているように見えます。しかし実際はパク家に依存している状態であり、富のあり余る者から仕事と対価を与えて貰っているという上下関係が消えることはありませんでした。
どんなに成り上がろうとしても上下関係は消えないし、半地下の「匂い」は身体に染みついて取れない。ギテクにとって、この乗り越えられない階級の差は、衝動的な殺意を抱いてしまうほど屈辱的なものだったのです。この低い階級から逃れる術はありません。韓国社会で生活する限りはずっと付きまとうものなのです。
そんな彼にとって社会を捨てて「イチ抜け」することは極めて幸福な結末だったのではないでしょうか。自分を苦しめてきた階級から解放された場所なのですから。物理的に安全であるあの地下室は、精神的にもおだやかな環境なのです。
望みのない社会
だからあのラストシーンはギテクにとってはきっとある種のハッピーエンドなのです。そして彼が幸福であればあるほど、息子のギウと観客の心境はどんよりと曇ります。いまの社会構造では貧困はどうにもならず、自らの基盤である社会での生活そのものを諦めて捨てることでしか救われないのですから。
貧困から脱出する希望の象徴である山水景石――と思い込んでいたその物体は、皮肉なことに水に浮いています。中身が空洞のレプリカなのです。
過去作に散りばめられた「偽りの問題解決」
ポン・ジュノ監督の過去の作品を見てみると、このような結末は少なくありません。「この人にとってはハッピーエンドだけれど――」というように、それぞれの立場に依存する多義的な解釈を許容する終わらせ方の名手だったのです。
何も解決していないけれど、解決したことにする

(C)2009 CJ ENTERTAINMENT INC. & BARUNSON CO., LTD.
軽度に知的障害を持つ息子を溺愛する母親が、我が子の冤罪を晴らそうと奮闘する『母なる証明』(2009) のラストは「自分で自分の記憶を消すツボを押す」というものでした。事件の真相を放棄し、有罪か無罪か、あるいは悔いるべきか否かといった諸問題から解放される道を選ぶのです。「何も解決していないけれど、解決したことにする」のです。
目の前の問題は解決したけれど、本質的に何も解決していない

(C)Netflix. All Rights Reserved.
Netflix資本で作られた『オクジャ/okja』(2017) という作品は、少女が豚のオクジャを助け出すというお話です。最後には無事にオクジャを救出できるのですが、少女はオクジャを助けに行く道すがらで “オクジャと同じ境遇の豚” を目撃してしまい、この豚たち全てを救うことは叶いませんでした。「目の前の問題は解決したけれど、本質的には何も解決していない」のです。物語は一旦おわったけれども、社会そのものは変わらない。一件落着したのはオクジャたちだけなのです。
あるいは、2003年の『殺人の追憶』もこの型に近いでしょう。いま現在は平和だけれども、殺人犯はまだこの町をうろついているのですから。さしあたりは事件は起きていないし、ソン・ガンホが演じた刑事の生活は安定しているけれども、犯人はまだ野放しなのです。
このように、ポン・ジュノ監督は「偽りの問題解決」とでも呼べよう虚無感に満ちた結末を描くことの多い作家なのです。
この虚無感がパラサイトという映画にも表出していると筆者は考えている、というのは上にも述べた通りです。ギテクにとってのみ幸福なラストであったし、息子のギウだって頭の中だけでは解決を導くことができた。だからこそ、その反動で悲劇性が強まったのです。狭すぎる「自分ルール」の幸福度は数値が高ければ高いほど、そのルールに則っていない第三者からの視点は冷たくなってゆくものです。
想像力の欠如ゆえに図らずも登場人物や観客を不幸にしてしまう映画だって少なくありませんが、ポン・ジュノの映画はそうではありません。慎重に考え抜いたうえで幸せを供給しないのです。
「偽りの問題解決」は救済か、皮肉か。そのどれでもない「祝福」の映画が生まれる社会が実現することを望みます。
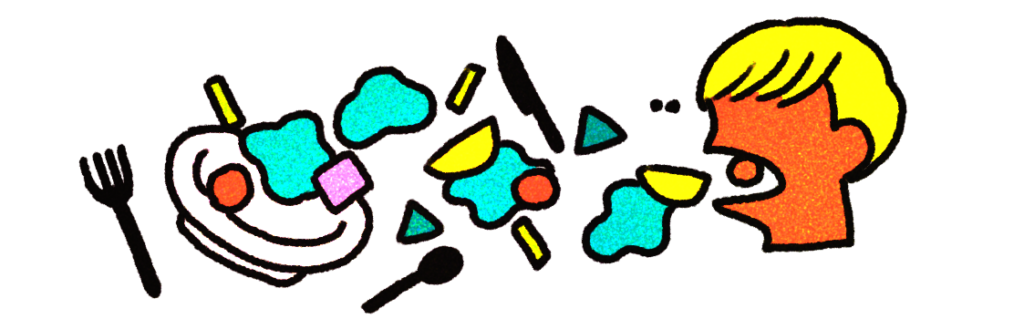
文・川合裕之
編集・和島咲藍
解説『パラサイト 半地下の家族』(2020)
監督:
ポン・ジュノ
出演:
ソン・ガンホ, チェ・ウシク, パク・ソダム, チャン・へジン,イ・ソンギュンほか
第72回カンヌ国際映画祭では韓国映画初となるパルム・ドールの受賞。第92回アカデミー賞では作品賞を含む6部門にノミネートされ、作品賞、監督賞、脚本賞、国際長編映画賞の最多4部門を受賞しました。『JOKER』、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』といったビッグタイトルがノミネートされていたにもかかわらず、それらに打ち勝って作品賞を受賞したというのは驚きです。
きょうびもはや「アカデミー賞」にどれほどの権威と信頼があるのか? という話も避けては通れませんが、そうは言ってもアカデミー賞。まだまだ食べれる腐っていない鯛!おめでたいですね。ポン・ジュノとソン・ガンホのタッグが、まさかここまで到達するなんて。
映画製作における労働環境もかなりクリーンだったことが報じられており、そうしたこぼれ話も含めて説得力のある作品に仕上がったと思います。さらに余談ですが、「半地下」という居住環境は世界的にそこまでスタンダードではなく、英語翻訳などの際にはかなり苦労したのだそうです。

—- sponsored (Amazon) —-

別冊映画秘宝 決定版 韓国映画究極ガイド (双葉社スーパームック)

韓国映画・ドラマ――わたしたちのおしゃべりの記録2014~2020

ユリイカ 2020年5月号 特集=韓国映画の最前線 ―イ・チャンドン、ポン・ジュノからキム・ボラまで―
このライターのほかの記事

きのこ帝国とベイビー・ドライバーと私 白いイヤホンで音楽を聴く日常は、いつか過去の文化になる。
「クロノスタシス」を、「きみと」ではなく「ひとりで」散歩しながら聴いた夜はないか。少なくとも僕にはある。夜、徒歩、コンビニ、そして音楽。僕たちの(というか僕の)モラトリアムの夜は、大抵この4つのエレメントに因数分解される。
そんな夜を象徴する曲をつくったバンドが活動休止した。あの頃はもう終わったのだといわんばかりの寂しさがぐっと押し寄せる。
〈続きを読む〉


