(C)2020「劇場」製作委員会
この記事には映画『劇場』の重要なネタバレが書かれています。
アタマからいきなりラストシーンに触れています。ご注意ください。
まだ映画を見ていない方はすぐにこのページを閉じてください。
本当に素晴らしい映画ですから、前情報なしに鑑賞していただければ幸いです。
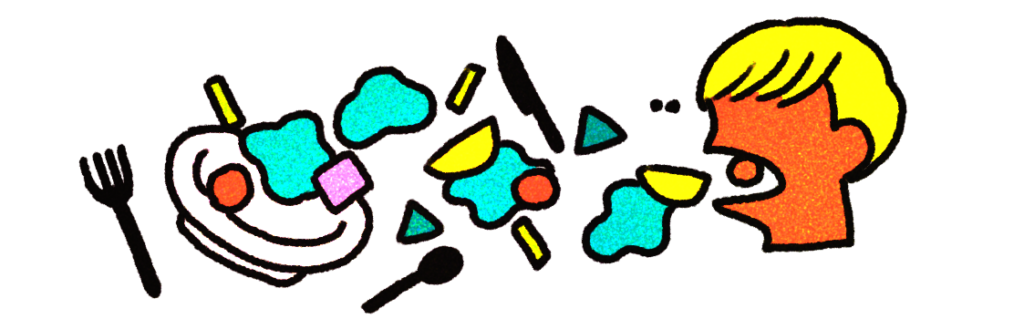
耳を疑うとはまさにこのこと。
その時、嘘みたいにゴテゴテした劇伴音楽が流れたことに僕は本当にがっかりした。
永田(演・山崎賢人)が贖罪する。「これは演劇なのだ」という皮をかぶってこれまでの罪をすすぎ沙希ちゃん(演・松岡茉優)への愛を不器用に語る。彼女もまたそれを正面から受け止め、そして返す。
観客の僕は涙を必死で我慢する。
まさにその時、仰々しいほどの劇伴が流れたのです。ありえない。信じられない。その時、僕は行定勲を見損なった。まさか最後の最後、こんな作り物みたいな音楽を挿入するなんて。この掛け合いは絶対に演出しちゃいけないのに。
と、その瞬間。
狭い狭いアパートの壁がパタリパタリと展開し、そこに望むは黒い空間。そこは劇場でした。舞台に見立てられたあのアパートが、喩えではなく “本当に” 劇場の舞台になったのです。
そして観客席には松岡茉優の姿。筆者、落涙。
これまで僕たちが映画だと思って見ていたものは実は演劇の舞台だったのだ、という原作にはない仕掛けです。僕は涙と鼻水で濡れてしまった手のひらを返して行定勲を称賛する。さっきは本当に失礼な大口を叩いてしまいました。「演出しちゃいけない」なんてのは素人の叩き出した大きな大きな早とちり。いま書いたようにこれが正解です。
「演出されていたものだと示す演出が必要」だったわけです。
舞台は終演し、カーテンコール。客電が灯され、ぞろぞろと観客は劇場をあとにするけれども、沙希は微動だにせず。最後の一人になってようやく彼女は静かに席を立ち、物語の幕が閉じます。
とんでもない映画を見た。
耳の次は自分の目を疑う。もちろん、これ以上になく良い意味で。
この記事では本作のラストに筆者が流した(というより流してしまった)の涙の理由を探していきます。
ほかでもなく屋台崩しが引き金となったわけですが、どこをどう撃たれたのか掘り下げて考えてみます。
「憑依」を許容しない救いのなさ
又吉直樹氏が言うように、及び編集部の安尾氏が指摘するように、原作である『劇場』という小説は「共感」というものからは何万マイルもの距離をとっています。一人称視点で語られるこの物語に「憑依」する読者はほとんど居ないでしょう。
これは僕の主観ですが、小説版のラストシーンもこの上なく救えない。もう笑うしかないというくらいに。
(僕は猿のお面をして「ばあああああ」と)何度も何度も言った。開演前のブザーのように「ばあああああ」と言った。しつこく何度も何度も繰り返した。
沙希は観念したように、ようやく泣きながら笑った。
(『劇場』p.207より。括弧内筆者加筆)
最後の別れの場面。永田が転がり込んでいた沙希のアパートを「劇場」に、自分たちのやり取りを「演劇」に見立てて舞台化することでようやく永田が本音で過去を清算することができた。裏を返せばそうでもしないと罪を自分で洗い流すことさえできない。自分が立っている現実というレイヤーの平面から外れて、演劇という別レイヤーを用意しないと本音を露出することができないのです。最後にはあろうことか猿の「仮面」を付ける。そうしないと彼は彼女に対峙できないのです。
読者はそれを鳥瞰します。「泣きながら笑う」のは沙希だけ。少なくとも僕はむしろこの微笑ましさすら不気味に感じました。
視点の妙

(C)2020「劇場」製作委員会
小説版は永田の1人称視点。しかし、映画版の『劇場』は少し形式が違います。一見すると同じなのですが、「映像」である以上、一般的には3人称であることが推奨されます。本作も例外ではなく形式上は3人称です。
たしかに永田だけをずっと追いかけてシーンが展開しており、永田を中心に話が進みますが、「映像の視点」という観点から見るとこれは3人称なのです。主人公は永田ですが、「永田の1人称視点」でのPOVになっているわけではないのです。
関連:ヒト畜生の映画評 | POV映画をdigる(note)
そしてこの3人称は、あくまでも3人称という形式の枠の中で段階的に1人称らしさを強めていきます。
たとえば時折挿入される彼の心の声。最初は現在形が中心だったのに、いつしか過去形が中心になってきます。「ボイスオーバー」が「独白」になるのです。時制が過去に変化することで、「物語性」が強くなります。「物語」とは「物語られる」ものであり、一度完結して閉じられたストーリーを伝文することが物語の古来よりのルーツなのですから。
聴覚からの情報の角度を工夫することで知らず知らずのうちに「聞き手」になる。「眼」で世界を追う傍観者だった観客は、「耳」で過去を聞かされる永田の当事者に変質するのです。
このように過去形での語りを挿入することで、映画の観客は世界を傍観する立場から主人公の永田に介入的な立場を選択しやすくなる。段階的に浸食してくるのです。安尾氏は「共感」なんて、というのだけれど、この映画には共感を実現しようとする逞しい筋力がありました。
そして最後の「屋台崩し」と、その直後にクロースアップされる松岡茉優。「今までの映像は舞台を見ながら回想していた沙希の脳内映像だ」という解釈では1人称の内容になるし、「沙希に宛てたメッセージだ」という解釈からは2人称の内容にもなります。
この映画の視点は、映像の形式上は一貫して3人称ですが、実質の内容での人称は1人称から3人称まで全ての視点が揃っているのです。
関連:特集・映画『her』① | 「声」に「触れる」ことで確信する、サマンサの実在:メディア論的考察
処理落ちする脳
きっとこの複雑な仕組みが涙の原因だと筆者は分析します。
永田はどうしようもないが、沙希には同情できる。そんな沙希と視点を同じくすることで、一瞬共感してしまう。視点を共にしていることで感情を共にしていると錯覚する。強引に、かつ急激に距離を縮められることにともなう共感です。
そして「これは舞台だったのだ」というサプライズの後、この映画は「沙希が主人公の3人称視点の映画」となる。沙希のことを3人称で鳥瞰します。
映画の観客は、今度は沙希に焦点を当てます。あんな仕打ちをされて、なのにまだ彼の舞台を見る彼女のことを。冷静になって考えると理解ができません。僕らには理解できないほど意味不明の存在である永田を、好きになってしまったのです。その自然災害のようなやるせない生理現象の悲劇。悲喜交々とはまさにこのこと。彼女は永田の成功が嬉しい。一方で決して互いに順風満帆とは言い難い。
なるほど。だから僕は泣いたんだ。
永田の内省、永田の沙希への悔恨。沙希の喜び。その隅にある悲嘆。映画の観客である自分視点での永田に対する怒り、沙希に対するある種の同情。あるいは、恥ずかしながら映画の余白に勝手に投影してしまった筆者自身の過去の背景。
様々な立場の、様々な感情が脳をジャックする。頭の処理が追い付かずに、その結果として煙ではなく涙が出たのだ。抱えきれないほどの感情を保持してバケツが溢れ出す。
僕は観念したように、ようやく泣きながら納得した。

文・川合裕之(フラスコ飯店 店主)
編集・安尾日向
解説『劇場』(2019)

(C)2020「劇場」製作委員会
監督:
行定勲
脚本:
蓬莱竜太
原作:
又吉直樹「劇場」
出演:
山﨑賢人, 松岡茉優, 寛一郎, 伊藤沙莉, 上川周作, 大友律, 井口理 (King Gnu), 三浦誠己, 浅香航大 ほか
新型感染症の影響で公開延期になっていましたが、絶対に埋もれさせてはいけない名品です。原作は他でもない又吉直樹氏、そして監督は『GO』をはじめ数々の「邦画!」というべき作品を手掛けてきた行定勲。
「あのアパート」はロケとスタジオの両方で撮影されたそう。つまり実際のアパートの分身のようなセットをあとから作っているということ。傾斜から電気の配電盤などの細かいディティールの隅々までが再現されているといいます。これは何度でも言いますが、松岡茉優さんの生年月日は1995年2月16日。僕とまったく同じです。まったく同じなのですよ。



