Last updated on 2023.04.22
(C)2014 Warner Bros. Entertainment, Inc. and Paramount Pictures. All Rights Reserved.
もし筆者が平安時代の歌人ならば、『インターステラー』に捧げる和歌を「袖ひちて」という5音で始めることでしょう——それくらい涙を拭う羽目になります。
クリストファー・ノーラン最新作『TENET テネット』の公開に合わせ、彼の過去作が IMAX 上映でリバイバルされました。その最後の作品として、『TENET』へとバトンを渡したのが2014年公開作品の『インターステラー』でした。
地球環境が荒廃した近未来、人類を救うべく移住先となる新しい星を探しに宇宙へと旅立つ宇宙飛行士たちと、重力の謎を解明すべく奮闘する地球に残された飛行士の家族たちを描いた作品であり、特撮を駆使した圧倒的かつ美しい映像と、最新の物理学に基づいた科学的に非常に正確なワームホール、ブラックホール描写が目を引きます。さらにノーラン作品らしく「時間」を大きなテーマにしたプロットもファンにはたまりません。
前作『ダンケルク』から3年、新型感染症による映画産業の危機のなか公開された『TENET』は、奇しくも6年前の作品である『インターステラー』と似た構造を持っていました——「時間」を描写・ストーリー双方の大きなテーマとし、「世界を救う」という命題を主人公たちが背負っているという点で。
『TENET』についてはいまもたくさんの考察や解説が出回っています。我々フラスコ飯店もその一翼として、巷で噂の “あの説” を真剣に考える論考を公開しました。『TENET』を既にご覧になった方はぜひそちらも!
さて、この記事では『TENET』が公開されたいまの時点から逆照射する形で、類似した構造を持つ『インターステラー』についてもう一度考えてみようと思います。「大迫力の映像!&ギミックたっぷりのプロット!」はノーラン節としてもはや当たり前として(なんと贅沢な当たり前……)、うねったりねじれたりする時間のなかで地球を救うという大枠が類似しているこの2作品。だけれどなんだか手触りが違う……あ、『インターステラー』は大号泣しちゃうけど、『TENET』はそんなことなかったかも?(筆者談)
もちろん『TENET』にも心揺さぶられるシーンはあるのですが、それを遥かに超える『インターステラー』の感情的起伏の豊かさよ! 少々あからさま過ぎるくらい、涙腺をもろに刺激してきます。その感じが好きになれない人もいるでしょうし、何より「泣ける映画」こそ良い映画だなんて微塵も思っていません。が、良い機会ですので『インターステラー』が私たちの胸に迫ってくる理由を、あくまでも冷静な目で、振り返ってみましょう。
結論を簡潔に先取りしちゃいます。
『インターステラー』は宇宙航路という極端な「移動」をモチーフとすることで、人と人とのコミュニケーションや孤独という普遍的なテーマを新たな形で描いているのです。
目次
・宇宙航路がもたらす新しい “距離”
・コミュニケーションによる癒しと絶望
・人は孤独を覚悟できるのか?
・マーフとの再会
宇宙航路がもたらす新しい “距離”
『インターステラー』のストーリーの大きな軸は宇宙航路にあります。元宇宙飛行士のクーパー(マシュー・マコノヒー)が秘密裏に活動する NASA を発見し、あれよあれよという間に宇宙へと飛び立つ。娘であるマーフとの約束を果たすため、宇宙航路の目的を果たしつつ地球への帰還を目指しますが、相対性理論と重力が邪魔をする。船員にとっての10分が、地球上では数年になってしまうのです。時間は資源。もたもたしていられない! 果たしてクーパーはマーフとの再会を果たせるのか——これが物語の軸となります。
映画にとって「移動」は大きなテーマとなってきました。人間が動くところに物語が生まれます。犬も歩けば棒に当たるではないですが、事件が起きないわけがない。動きを捉えるメディアである映画との相性もいい。ロードムービーというカテゴリーが成り立っていることもひとつの証拠ですね。名作と称されることの多い『マッドマックス 怒りのデス・ロード』も実は「行って、帰ってくる」だけのシンプルな「移動」を物語の軸としています。でもそうとは思えない豊かな物語が湛えられています。人間の「移動」はストーリーを生み出すのです。
しかし現代社会に生きる人びとに対して「移動」が果たす役割はかつてに比べて小さくなりました。「移動」して直接会わなくても画面上でなら顔を見ることができる。手紙が届くのを何日も何日も待つ必要がない。電話、ラジオ、インターネットと電信技術が発達し、車、電車、新幹線と移動手段が高速化していくなかで、私たちの時空間の捉え方は変化しました。現代において夏目漱石『こころ』のような時間的すれちがいは切実さに欠けたものとなってしまうのです。
芸術史において未来派と呼ばれる潮流がありました。技術発展による高速化を称揚しており、未来派の絵画は運動やその速さを捉えようとします。また技術による高速化の先にある戦争を賛美するような危険な思想も持っていました。その創始者マリネッティによる「未来派宣言」(1909)には次のような言葉があります。
時間と空間は昨日すでに死んだ。
Erich Fromm、鈴木重吉訳 (1965)『悪について』紀伊國屋書店、pp. 70–71
筆者は芸術史に明るいわけでも未来派にシンパシーを感じているわけでもありませんが、この言葉は妙に記憶のなかに残っていました。
未来派宣言から1世紀が経ち、インターネットの普及により時間と空間の逝去はすでに「一昨日」のものとなりました。あらゆる「距離」が小さくなった時代において「移動」による大きな物語を描くことは簡単ではありません。だからこそノーランは、宇宙航路という新しい「移動」によって新しい「距離」を描いたのです。
宇宙航路という新しい「移動」と、それによって生まれる新しい「距離」。そして「距離」が生まれるところに「コミュニケーション」が生まれます。

(C)2014 Warner Bros. Entertainment, Inc. and Paramount Pictures. All Rights Reserved.
コミュニケーションによる癒しと絶望
そもそも communication という語は語義として「交通」という意味を持ち、17世紀頃まで transportation とほぼ同義で使われていたそうです(*1)。現在では人と人との会話や情報のやりとりをイメージする語ですが、人や物資、情報の輸送=「移動」を指す語でもあったのです。
『インターステラー』におけるコミュニケーションは2つの特徴的な形で描かれています。1つがロボットとのコミュニケーション、もう1つが地球から宇宙船への一方向コミュニケーションです。それぞれについて見ていきましょう。
TARS との正直レベル90%のやさしい会話
金属製の直方体形の AI ロボットが3体登場します。それぞれ TARS、CASE、KIPP という名前を持ち、性格もさまざまです。のっぺりとした直方体形は『2001年宇宙の旅』のモノリスを想起させますが、モノリスや同じく『2001年宇宙の旅』に登場するコンピュータ HAL9000 とは異なり、非常に「人間らしい」ユーモアや性格を持っています。
なかでも TARS とクーパーの会話は印象的です。宇宙到達直後、会話を避けようとするアメリア(アン・ハサウェイ)とのやりとりのあとクーパーは TARS に問いかけます。
TARS、お前の正直レベルは?
『インターステラー』より
90%だ
90%?
完ぺきな正直さは時として感情を持つ相手を傷つける
なるほど。我々も90%でいこう
この TARS の言葉は彼らがただの無機的なロボットではなく有機的な「友人」であることを観客に示しています。さらにこの言葉は、映画のクライマックスにも非常に効いてくるという点でも重要なセリフとなっています。
ユーモアレベル、正直レベルを設定されたロボットとの会話はとてもやさしく、船員たちの孤独を癒すものとなっています。水の星のシークエンスでロミリー(デヴィット・ジャーシー)はひとり、宇宙に残りますが、その間約23年(!)を彼ひとりでは耐えられなかったでしょう。TARS が宇宙船に残っていたからこそ、彼は眠らずに待っていられたのです。
友人としてのロボットたち。彼らとのコミュニケーションによる癒しはとてつもなく大きな意味を持っています。だからこそ、マン博士(マット・デイモン)の「罪」が強く映し出されるのですが、これについては後述します。
もう1つのコミュニケーション、それは地球から届くビデオレターです。

>映画ポスター 『インターステラー』 US版 hi3 [並行輸入品]
応答のないコミュニケーションと絶望
地球に家族を残し宇宙へと旅立った飛行士たち。家族とはビデオレターでコミュニケーションを取り続ける——はずでした。ブラックホールへの接近のせいか、宇宙船からの送信ができなくなってしまいます。地球からの受信はかろうじて可能で、このコミュニケーションの一方向性が地球・宇宙双方の人々を苦しめていきます。
水の星との往復により、地球時間で約23年を費やしてしまったクーパーたち。その間のビデオレターを一気に再生するシーンは、感情的なクライマックスのひとつです。
息子トム(ティモシー・シャラメ)の高校卒業の報告を聞き、喜ばしく思うと同時にそれがすでに20年以上の前のことであることを思い知る。次にスクリーンに映るビデオではトムはもうすっかり中年になっており(役者もケイシー・アフレックに)、孫が生まれ、そして死んでしまったことを知る。トムはクーパーの生存を諦め、ビデオを送るのもやめるという。トムの放つ「さよなら」にクーパーは手を伸ばすが、それも虚しく画面は暗くなる——と思いきや、また画面は灯り、自分と同じ歳になったマーフ(ジェシカ・チャステイン)が現れる。23年という月日はそれほどまでに長いのです。
恐ろしいのは、重力の時間への影響によりクーパーにとってはたったの数時間しか経っていないこと、そして長すぎる23年を伝えるのも数時間にも満たないであろうビデオであるということ。宇宙航路という「移動」によって、時間は無慈悲に圧縮される。子どもたちの成長=老化がそれを伝えます。
地球にいる家族たちにとっても、この一方向コミュニケーションは別の恐ろしさを持っています。それはまさに「応答がない」ということ。送っても送っても返事がない。地球と宇宙の距離を埋める楽しい会話はおろか、元気にしているのか、いやそれどころか生きているのか死んでいるのかを知ることすら叶わない。
また、英語において「応答すること responsibility」はすなわち「責任 responsibility」でもあります。ということは「応答がないこと」は「無責任」であるということです。だからトムは父がビデオを見ていることに懐疑的になるし、マーフはビデオの一言目で「ひどい人よね」と言うのです。地球に残された者たちにとってクーパーは無責任に自分たちのもとを去った人となってしまう。どちらにとってもつらいことです。
宇宙航路という新しい「移動」によって、コミュニケーションの問題が中心化することを論じてきました。コミュニケーションが可能であること/不可能であることによって癒し/絶望が生まれます。何が癒され、何が絶望的になるのか。それは「孤独」です。

(C)2014 Warner Bros. Entertainment, Inc. and Paramount Pictures. All Rights Reserved.
人は孤独を覚悟できるのか?
『インターステラー』におけるクーパーの宇宙航路は、そもそも NASA による「ラザロ計画」の一端です。マン博士ら先行する飛行士たちは、可能性のある星々へとひとりで降り立ち、人間が居住可能かを調査する任を受けています。その際、自らの命は保証されません。居住可能性があれば地球へと信号を送り、後続するクーパーたちが迎えにいくことになっていました。
つまり、地球に信号を送れば後続の飛行士たちによって救出される希望があるいっぽう、送らなければ居住不可能な星でひとり死んでいくことを受け入れなければなりません。そもそもこの任務は文字通り命を懸けることを覚悟しなければならないものです。降り立った星が居住不可能であれば死を受け入れなければならない。でなければ無駄な信号を受け取らせることになるから。参加者はそれをわかっていたはずです。
嘘の信号を送った人物、それがマン博士でした。彼はコミュニケーションによる癒しを与えてくれる友人であるはずのロボット KIPP を破壊します。KIPP はその星が居住不可能であることを知っていたから。マン博士が嘘の信号を送ることを許さなかったから。マン博士は自らの孤独を KIPP という目の前にある癒しではなく、嘘の信号による救出によって癒そうとしたのです。偉大な科学者と称され、マン MANN =人間 MAN という名前を冠した人物が、まったく孤独を覚悟できていなかったのです。ここにはノーランの「人間は真に孤独を覚悟することはできない」というメッセージを感じます。
この映画では、あらゆる人をあらゆる孤独が襲います。
アメリアの孤独
アメリアはクーパーの正直レベル90%の発言によって、ひとり「クーパーの犠牲の上で」最後の星へ向かいます。命を助けられた者として任務を達成させなければならないという状況にひとりで立ち向かう必要があります。降り立った恋人の星に、もう恋人は生きていませんでした。しかし居住可能な星が見つかったこともわかっています。クーパーは死んだものだと思っているため、いつ来るのか、いや、いつか来るのかもわからない助けを信じて眠らなければなりません。クーパーへの感謝、恋人の喪失、任務達成の喜び、救出への不安——彼女の孤独には複雑な色がいくつも差しています。
トムの孤独
作品では後景に押しやられている人物の孤独にも目線を配ってみましょう。息子・トムです。彼はクーパーの出発時にはすでに高校生で、クーパーにもかなり「大人」として扱われています。本人もそのことをわかっているのでしょう、父の出発にもマーフのように取り乱したりしません。だからクーパーもトムのことをあまり心配していませんでした。
でも本当に、彼はすでに「大人」だったのでしょうか。もしかしたらクーパーは、トムを過剰に大人扱いしていたのかもしれません。トムの父への思いは表に表れることが許されないまま、内側で蓄積していったことでしょう。それはあるいは、父への自らの感情に折り合いをつけられていないということかもしれません。結果、彼は自分が育った場所への執着、そしてそこに家族と一緒に住み続けることへの執着という形で、折り合いのつかない感情を顕現させてしまいます。
幼いマーフの影で「大人」にされてしまった少年の、自分でも気づいていなかった孤独がここにはあります。作品中で最も地味で、最も悲哀に満ちた孤独かもしれません。
関連記事:Don’t Boys Cry?〈対話〉による男性性の克服|映画『幸せへのまわり道』
父を宇宙に失ったトムは、父に対する自らの感情に蓋をしたまま、大人になり、夫になり、そして父になった。感情を抑圧してしまう悲しい男性性と向き合う誠実さを、僕たちは持てるだろうか——。この問いについて、今年公開された映画『幸せへのまわり道』(マシュー・リス、トム・ハンクス主演)に宛てて考えた記事です。
マーフとの再会
真の主人公マーフも孤独と対峙したことでしょう。自分の必死の懇願も虚しく父は旅立ってしまった。マーフの思いであり、幽霊(=クーパー自身)の思いでもある「STAY」というメッセージを、どうして聞き入れてくれなかったのか。そのことへの怒りで父からのビデオも見なかったと言います。
とはいえ、優秀なマーフはブランド教授(マイケル・ケイン)の研究に参加します。そこには父・クーパーを信じたい気持ちがあったことでしょう。しかし約束の時である誕生日を迎え、父の年齢に追いついてしまったマーフは、クーパーへの不信を募らせます。父を信じたい、父を信じている、父を信じられない。彼女の父への思いは揺れ動きます。
さらには師であり、父の代理という側面もあったであろうブランド教授によっても、大きな喪失をもたらされます。それは彼自身の死であるとともに、彼が地球上の人類を諦めていたという裏切りです。
それでも諦めなかった彼女は、ブラックホール内に自らを犠牲にしたはずのクーパーと、時空を超えたコミュニケーションを果たします。その媒体となるのは、人々の思考の記憶を時間を超えて伝えるものである本(*2)と、時間の象徴である時計でした。それによって人類は地球を脱出し、クーパーも救出されます。
ついにマーフとの再会を果たしますが、彼女はもう死の床についていました。たくさんの家族に囲まれた彼女がクーパーの姿を捉えます。父は出発した時からさほど年老いていないように見えます。宇宙航路の「移動」によってねじれた時間が2人の姿にありありと表れています。それでも再会できた喜び、信じてよかったという安堵に包まれた2人を見て、筆者は涙が止まりません。
『インターステラー』は宇宙航路という極端な「移動」を物語に組み込むことで、現代の人々が見失っているかもしれない人と人との「距離による隔絶」と、それに伴うコミュニケーションの不完全化、そして孤独という普遍的なテーマを描きなおすことに成功した映画であると言えるでしょう。まさに inter – stellar =星と星との間の、移動・コミュニケーション・孤独を描いた作品なのです。
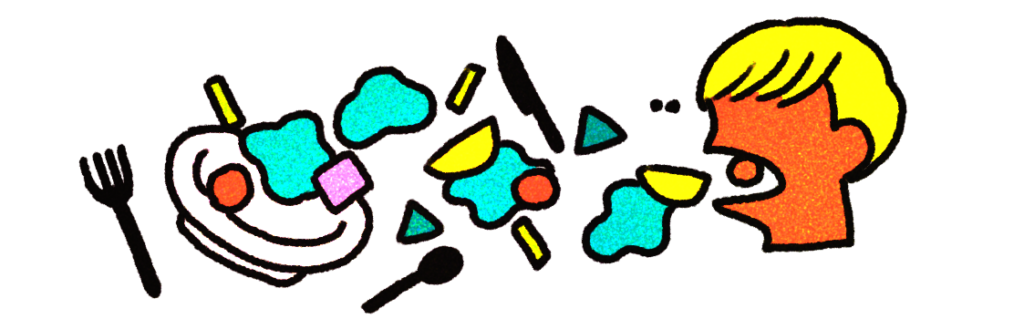
フラスコ飯店の最新の更新をチェックしてみてください!
上のイラストをクリックすると遷移します!
参考文献
(*1)佐藤卓己(1998)『現代メディア史』岩波書店
(*2)北村紗衣(2014)「時を超える愛のためのメディアとしての「本」について〜『インターステラー』(ネタバレあり)」
文・安尾日向
編集・川合裕之(フラスコ飯店 店主)
解説『インターステラー』(2014)

監督:
クリストファー・ノーラン
脚本:
ジョナサン・ノーラン
出演:
マシュー・マコノヒー、アン・ハサウェイ、ジェシカ・チャステイン、マイケル・ケイン、ティモシー・シャラメ、ケイシー・アフレックなど
この作品の企画は、『コンタクト』(1997)などを手掛けた映画プロデューサー、リンダ・オブストと、ノーベル物理学賞を受賞している理論物理学者、キップ・ソーンの2人によって始められ、監督にはスティーブン・スピルバーグがつく予定だったそう。スピルバーグが降りたあと、脚本を務めるジョナサン・ノーランの兄であるクリストファーに白羽の矢が立ち、結果『インターステラー』が完成したようです。キップ・ソーンは最新作『TENET』にも関わっている模様。ガチの物理学者がとことん考え抜いた “SF” って、それだけでも興奮しますよね。

あとはのちの大スターであるティモシー・シャラメが出演しているのもいまから考えるとなかなかにアツい。ティモシーはクリストファー・ノーランと並び立つ現代 SF 映画作家となったドゥニ・ヴィルヌーヴの最新作『DUNE』の主演も務めており、そちらもめちゃくちゃ楽しみですね。『TENET』見にいったら予告流れているはず!

時間を逆行して、
世界を救おう
(C)2020 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved
なぜ TENET という回文なのか。〈回文的因果律〉から導き出される〇〇の正体|『TENET テネット』評
ニールは実は〇〇なのではないか――という説があります。パンフレットで山崎貴が自身の妄想だと前置きしたうえでそう語っているのに加えて、国内外の考察ファンがこぞって声を挙げているお話です。
え、本当に?
にわかに信じがたい仮説ですが、もしそうだとすればこんなに楽しいことはありません。きょうはこの説を考えて一緒に頭を悩ませてみましょう。
〈続きを読む〉
編集部の感想
「もし筆者が平安時代の歌人ならば」からはじまるSF超大作の映画評って何?どういうこと?大丈夫? 最初は面食らいましたが、客観性の高い良記事でした。おれ? いま? 泣いてるよ!(編集長より)
執筆後記
僕はそもそもノーラン作品なら『インセプション』派だったんですよね。それこそ『インターステラー』のあまりにも “泣けてしまう” 感じがクールじゃないと思っていたというか。でもやっぱりストーリーの圧倒的なエネルギーを、大きなスクリーンで、大きな音で、目の当たりにして泣いてしまうという体験の持つ悦楽には替えがたいものがあるのも事実だ、と改めて思わされました。
書けないかも、と思ったりもしながらの執筆でしたが、今では名刺代わりにしたい記事になりました。長いし固くて読みにくかったかもしれませんが、読んでくださったみなさま、ありがとうございます。(筆者)



