©BUENA VISTA PICTURES
中学3年生以来、ヒールのある靴を履いたことがない。持っていないから、デートでも大学の入学式でも履かなかったし、就職活動はスーツ一式を揃える前に辞めてしまった。
特に何かの主義主張があるわけではない。わたしの好きな服の系統にはヒールのある靴はそぐわないし、24.5cmで甲高幅広の足に合わないから履かない。ただそれだけ。
でも、世の中にはわたしの「ただそれだけ」を渇望する人がいる。
青い靄がかかった桟橋の上で真っ赤なハイヒールを履いた少年は、まるで自分の魂を解放するように、うれしそうに踊る。
靴を鳴らせば世界が始まる
目元の柔らかい皺をぎゅっと縮めて、その紳士は靴を「世界で一番美しいものだ」と言う。どこかふてぶてしい顔をした少年と並んでベンチに座り、靴を鳴らせば一斉に鳥が飛び立って、世界が始まる。
舞台はイギリスの田舎町・ノーサンプトン。かつて息子に靴作りへの矜持を語っていた父の急死後、主人公のチャーリー(ジョエル・エドガートン)は、伝統ある紳士靴工場「プライス社」を継ぐことになる。婚約者のニコラ(ジェミマ・ルーパー)と始めるはずだったロンドンでの都会暮らしを諦めて帰郷した先にあったのは、大量生産で寿命の短い安価な製品に圧されて負債だらけの工場だった。

©Kobal/TOUCHSTONE/BUENA VISTA PICTURES/The Kobal Collection/WireImage.com
もともと気が弱く、誰かの上に立つような役回りが苦手なチャーリーは、心を痛めながらも従業員の解雇をすすめてゆく。そんな中、靴職人のローレン(サラ=ジェーン・ポッツ)からの「ニッチ市場を狙うのよ!」という喝によって一念発起したチャーリーは、ロンドンで出会ったドラァグ・クイーンのローラ(キウェテル・イジョフォー)の存在を思い出す。
※ドラァグ・クィーン:諸説あるが、一般的には性的指向を超えるために、ドレスやハイヒール、厚い化粧や大胆な態度で「女性性」を過剰に演出したパフォーマンスを行う男性同性愛者・またはパフォーマーのこと。
それまで無理やり女性用の窮屈なブーツを履くしか選択肢のなかったドラァグ・クイーン用のブーツを「ニッチ市場」に定め、チャーリーとローラは新たな製品の開発に挑むーー。
ここまでが実話を基に制作された映画『キンキーブーツ』の大まかなあらすじだ。わかりやすいストーリーだし、この映画の魅力を表すキーワードはきっと無数に存在する。崖っぷちの主人公の起死回生、きらびやかでウィットに富んだドラァグの世界、ヘタレな主人公に勝気な相棒、などなど。
しかしわたしが炙り出したいのはそのどれでもなく、この映画に通底する「合理性の魔力」である。
先に結論から言おう。映画『キンキーブーツ』は、 “合理性” から脱却する物語でありながら、同時に “合理性” を未来に温存する物語だ。
この記事では映画『キンキーブーツ』が打破した呪縛と、それでもとらわれているものについて、ひとつずつ見てゆきます。
-目次-
・靴を鳴らせば世界が始まる
・ “合理性” とは一体何なのか
・ “合理性” に苦しめられる主人公たち
・「ニッチ市場」のその中身は
・ “合理性” の一歩先の物語
・それでも再生産される “合理性”
・2021年の『キンキーブーツ』
合理性とは一体何なのか
この映画に横たわる「合理性」について考えるために、まずは「合理性」という言葉を紐解いてゆこう。
辞書を引いてみると、以下のような意味が出てくる。
合理的:
大辞林 第三版
目的に合っていて無駄がないこと。
論理にかなっていること。
因習や迷信にとらわれないこと。
合理:
新明解国語辞典 第八版
その考えが論理的に正しいと判断されること。
理屈には合っていること。
なるほど、この言葉は、きっと今わたしたちが生きているこの社会と、とても相性がいい。
効率良く生産して多くを売り、経済的に豊かになる。世迷いごとは無視して進学し、就職する。その先には人類の本能と論理に適った生殖が待っている。
資本主義の、猛スピードの、 “豊かな” 国の、最先端のわたしたちは「合理的であること」を求められている。「合理的」という言葉はもはや「常識」になりかわりつつあるらしい。
明確で同一な目的意識、効率、論理、常識。これらが『キンキーブーツ』を貫く “合理性” の内訳だ。
“合理性” に苦しめられる主人公たち
「合理性」や「常識」は、とても強くて、すごく便利だ。
いちいち確認しなくたって前提が共有されていれば、それこそ “合理的” で話が早い。さらには、頭を空っぽにすることだって可能だ。自分の選択の理由を訊かれたら「その方が合理的だから」、「それが常識だから」と答えておけば、自分も相手も簡単に納得することができる。迷ったら合理的で常識的な方を選んでおけば、たとえ失敗したって誰もあなたを責めないだろう。
では、その「合理性」や「常識」からどうしてもはみ出してしまう者たちは?
映画『キンキーブーツ』に戻ろう。
気弱でリーダーシップのない社長と、ドラァグ・クイーン。彼らは、世の中が掲げる「合理性」や「常識」からはみ出している人間たちだ。
- 資本主義経済ではより多くのお金を稼がなければならないので、一生ものの靴を売るよりすぐに買い換えなければならない靴の方が都合がいい。
- 体格の良い黒人男性に生まれたならば、それを活かしてボクサーになるのが成功への近道だ。
- 負債だらけの工場ならば、早いとこ売ってしまった方がいくらかは手元に残すことができる。
- 男女でしか生殖できないのだから、交際は男女間で行うものだ。
- 高いヒールは「女性」が「男性」に性的にアプローチするためのものなのだから、男性が履いても意味がない。
- 男性ならば、リーダーシップと仕事への誇りを持って部下たちを率い、素早く正しい決断を下さなければならない。
書いているだけで視界がぎゅっと狭まるような、怖気の立つ文字列だけれど、これらは彼らを苦しめる “合理性” のほんの一部に過ぎない。

©cinema.de
さらにややこしいのは、同じ “はみ出し者” のチャーリーとローラでも、その「はみ出し方」は全く異なるということだ。
チャーリーは男性として生まれ、異性愛者として生き、婚約者もいる。彼が受ける苦しみは、「男性」というカテゴリーの中での、会社と家庭を背負う重圧だ。反面、同性愛者でドラァグ・クイーンのローラは「そもそもカテゴリーに入れない」という苦しみを抱えている。
この映画の舞台は保守的な雰囲気が色濃く残るイギリスの田舎町。ローラは初対面で服装倒錯者呼ばわりされ、工場の男性たちのホモ・ソサエティからは激しい侮辱を受ける。
※ホモ・ソサエティ:「ホモ」とは「同一の」という意味で、恋愛または性的な意味を持たない、同性間の結びつきや関係性を意味する社会学の用語。男性間のホモ・ソサエティでは女性蔑視と同性愛嫌悪によって絆を深める働きが強いとされている。
ロンドンからローラを呼び寄せたチャーリーも、自分が所属するカテゴリー(=男性)が掲げる合理性によってローラを理解できず、人目や立場を気にして決して彼女(彼)をかばってはくれない。それどころか、ウィットに富んだ返答で侮辱をいなすローラを「ここは田舎町なんだ」とたしなめさえする。
物語はまず、2人がお互いの苦しみをそれぞれ紐解き、理解し合おうとするところから始まるのだ。
「ニッチ市場」のその中身は
物語の序盤、チャーリーが認識するローラは、ドラァグ・クイーンという「ニッチ市場」の代表者でしかなかった。
「長持ちするちゃんとした靴、女性デザインで、男性の体重にも耐えられるもの」という目標を掲げたチャーリーだが、出来上がった靴はバーガンディ色の、太いヒールがついた作業靴めいた野暮ったいものだった。
ローラは激怒し、工場の女性たちに「外出するときにこれを履きたいと思う?」と尋ねる。答えは満場一致のNO。ローラはチャーリーを「ニッチ市場に敬意を払って」と看破する。

©cinema.de
ローラが履きたいのは、真っ赤で細いヒールがついた、セックスそのものを表現する靴。実現可能性という名の “合理性” を優先し、「これぐらいでいいだろう」という妥協にまみれたおこぼれの靴ではないのだ。
1枚のデザイン画を残してロンドンに帰ろうとするローラを引き止めるときになって初めて、チャーリーは他の誰でもない “ローラそのもの” と向き合おうとする。一人の人間として、あるいはクリエーターとして真摯に意見を聞こうとし、施しではなく対等に、あるいは教えを請う者として真正面からローラと話すのだ。
ニッチ市場はローラのような/ローラとは違う様々な個人が集まってできたものである、と認識を改めてやっと、チャーリーとローラは「相棒」になるのである。
翌日、勇気を出して男性装で工場に現れたローラに対する侮蔑をチャーリーはもう黙殺しない。2人は男性用トイレで互いの苦しみを吐露して励ましあい、ローラは「サイモン」と本名で名乗る。
“合理性” の一歩先の物語
「私たち、堂々と振るまわなきゃ」というローラの言葉を道標に、2人は相棒として靴作りに取り組み始める。
彼らの靴作りを助けるのは、経験豊富で熟達した技を持つ、現代では “合理的ではない” 職人たちだ。「成人男性の体重でも支えられる細いヒール」という非合理的な難題に、彼らの表情は輝く。
靴作りについて隅から隅まで熟知しているからこそ生まれるクリエイティブな案に、それを実現するだけの腕と矜持。それらが揃って初めて実現した ”75センチの筒状のセックス” を手にした時のローラの顔と言ったら!
甘くとろけそうな笑顔で誇らしげにブーツを掲げるローラは、 “合理性” の壁を超えて、まさに「自分のための世界」を手に入れた解放感に満ち溢れている。
一方チャーリーにも転機が訪れていた。婚約者から工場を売却して2人の新居を購入することを持ちかけられていたのだ。
実はずっと前から工場の経営はガタガタで、生前の父も工場の売却話を進めていたことを知らされ、チャーリーは「一家の歴史を守る」という大義名分を失う。さらに、今すぐに工場を売れば損失を最小限に抑えて何ランクも上の新居を手に入れることができるとくれば、工場を売らない “合理的” な理由はどこにもない。
それでも、通行人の靴に目がいく自分がいる。相棒との新たな挑戦に胸を躍らせる自分がいる。覚悟の時だった。
かつて父と並んだのベンチに座っているのは、今度はひとりだ。だけどいつでも、靴を鳴らせば一斉に鳥が飛び立って、世界が始まる。
チャーリーが自分だけの決断を通して、他でもない「自分のための世界」を手に入れた瞬間だった。
映画『キンキーブーツ』は、世間からのはみ出し者2人が相棒となり、それぞれが ”合理性” の一歩先を掴み取る物語だ。彼らはもがき、汗をかき、自分の手を動かして、何度でも勇敢に立ち上がる。ああ、本当は泥臭いはずなのだ、あなたも、わたしも。

©cinema.de
それでも再生産される “合理性”
2人の想いが周囲を動かし、物語は一致団結大団円のハッピーエンドへと動き始める。このままエンドロールを迎えれば、この映画はめでたく「はみ出し者2人が相棒になって “合理性” から脱却した物語」になっただろう。しかし、そうはならなかった。
晴れてミラノコレクションに “キンキーブーツ” を出品する前日、婚約者が他の男性と食事をしているところを目撃したチャーリーは、ローラに暴言をぶつける。
「君はドレスを着た男だ。ドレスを着た間抜けだ。自分の性別がどっちか決めたくないわけか。神秘的でどっちの性でも最高って気取るのか。違うぞサイモン。ドレスなんか着て、どっちも最低さ。隠れるな。勇気を出せ。どっちか決めろ」
婚約者の姿を目撃して自分が男として無用な存在に思えた、と後から本人が振り返っている通り、この発言は何ら非のないローラに、チャーリーが八つ当たりをしているものだ。

©cinema.de
なぜチャーリーは、一度は心を通わせたはずのローラに矛先を向けたのだろう?
もちろん「ショックを受けてから最初に会ったのがローラだったから」という可能性も考えられるだろうが、やはり男性間のホモ・ソサエティの存在は無視できない。
振り返ってみれば、この映画ではローラへの風当たりは一貫して女性からよりも男性からの方が激しく描かれている。伝統的に、男性の間には女性蔑視と同性愛嫌悪によって「男性性(=男らしさ)」を担保し、男性間の絆を深める構造があると指摘されている。男は女遊びが上手くて裸の付き合いができて一人前、といった具合だ。
こうした構造の中ではローラのような男性は「格下」なのであり、「男らしさ」に敗れたチャーリーが唯一矛先を向けて溜飲を下げることのできる、都合の良い存在だったのだ。
反省と後悔の末、チャーリーは「半端な男と言われたっていいじゃないか。半端な男って何だ。そもそも男って?」という根源的な疑問にたどり着く。それでもローラに「ごめんなさい」、または「悪かった」とは言わない。チャーリーが誰かに糾弾されることはおろか、直接的な謝罪や、ローラに頭を下げるようなシーンは描かれていないのだ。
ローラはチャーリーの誠心誠意の謝罪ではなく、自らの寛大な心と俯瞰的な眼、粋でしなやかな逞しさによって彼を赦す。両者の決定的な和解を見ないまま、ミラノコレクションでのショーは大成功、物語は大団円のハッピーエンドを迎える。
「男らしさ」に悩み、そこから脱却したはずのチャーリーが、今度は男性間のホモ・ソサエティという新たな合理性・常識の構造に絡め取られ、自尊心を満たすためだけに他人を侮辱する。これを機に徹底的に反省したり開眼するのかと思いきや、解決の方法はドラァグ・クイーンやLGBTQsのステレオタイプ的 ”強さ” だ。
映画『キンキーブーツ』は、確かに資本主義やものづくりにおける “合理性” を打破した物語だ。しかし同時に、男性性やドラァグ・クイーンの描き方において、また別の “合理性” を未来に温存している。
『キンキーブーツ』は、世の常識や “合理性” から逃げ切ることができなかった。合理性の魔力は、どこまでもわたしたちを追いかけて離さないのだ。
2021年の『キンキーブーツ』
この映画が公開されたのは2005年。LGBTQs やホモ・ソーシャルの弊害、フェミニズムについての議論が活発になったのは2015年頃からだ。そういう状況を無視して2021年の感覚でこの映画を裁こうとするのは全くもってフェアではないし、この映画が駄作だと言いたいわけでも決してない。
ローラに関しても、ステレオタイプ的な強さだけではなく、心の痛みを忘れるために酒に頼る姿や、人前に出る恐怖から部屋のドアの前に立ちすくんでいる姿も克明に描かれている。
また、確かに、先ほどの項で述べたチャーリーの発言は擁護のしようがない暴言だ。「今までの物語は一体何だったの?」となってしまうような罵詈雑言で、とても看過できない。
だけど、これが現実なのだと思う。一朝一夕で自分が生きてきた世界を動かす「理」が変わるわけじゃない。動揺もすれば、間違いも犯す。物事を深く考えれば考えるほど何も断言できなくなってゆくように、しがらみをひとつ解けば新たなしがらみに捕まってしまう。
そりゃあフィクションでくらい正真正銘のハッピーエンドが観たい。だけど、それでも、これがリアルなのだ。そういう意味では、この映画は正真正銘の “実話を基にした” 傑作だと言えるだろう。

©cinema.de
2021年は2005年と地続きで、わたしたちはいつでも、現実と理想の間の苦しくて長い一歩をどうにか進んでいる途中にある。
女性が履くハイヒールに心底憧れ、それによって魂を解放する男性がいる一方で、「ヒールのある靴を履かなければならない」というマナーに苦しむ女性がいる。
「これで全部解決!」なんていう特効薬はどこにもないし、一律で「合理性=悪」というわけでもない。「合理性」や「常識」で作られた世界を丸ごと否定するには、わたしたちはその恩恵を受けすぎている。
ただ、自分の外側にあるその「理」で自分が苦しんでいないか、誰かを苦しめてはいないか、それはどんな時も優先して守らねばならない絶対的なものなのかを、検分することを忘れてはならないのだと思う。
わたしたちが歩く現実と理想の間に、道標は存在しない。それでも、もしあなたが何かに迷ったり自分の「正しさ」に自信を持てないでいるのなら、それこそがきっと、他の誰かを導く栞になる。
2005年を生きた、2021年を生きるわたしたちへ。
現実と理想の間の苦しくて長い一歩をどうにか進むその足には、どうか自分が一番心地よいデザインの、履きやすくて丈夫な靴が輝いていますように。

文・和島咲藍
編集・川合裕之
解説『キンキーブーツ』(2005)

監督:
ジュリアン・ジャロルド
脚本:
ティム・ファース
ジェフ・ディーン
出演:
ジョエル・エドガートン, キウェテル・イジョフォー, サラ=ジェーン・ポッツ, ユアン・フーバー ほか
2005年にアメリカとイギリスが合同で制作したコメディ映画。日本では2006年に公開されました。2016年に日本で三浦春馬と小池徹平によって舞台化されたことでご存知の方も多いのではないでしょうか?
前述の通り、この映画は実話に基づいて制作されており、舞台である靴工場「プライス社」は、イギリスに実在するW・Jブルックス社をモデルにしています。
公開当初は賛否両論だったものの、2013年にブロードウェイで舞台化される際にはシンディ・ローパーが作詞作曲をつとめ、トニー賞を受賞するなど、世界中で大ヒットを果たしました。2021年3月にはブロードウェイ版が映画化。こちらも見逃せませんね。
また、2020年10月には三浦春馬版ミュージカルの特別映像「Kinky Boots Haruma Miura Tribute movie」が公開。公式YouTubeには「皆さまの心に、三浦春馬のローラの輝きがいつまでも残りますように。」との言葉が記されています。
この映画が舞台としてリメイクされ、才能と熱意あふれる俳優の熱演によって2021年のわたしたちに「合理性の魔力」を突きつける機会があるのは、とても幸運なことだと、しみじみ感じます。
“自分” を取り戻すための定食はいかが?
「ひとりでカラオケに行く」というのは、何か特別な行為のように思います。友達や家族とではなく、一人で、誰にも気を遣わず、歌う曲の順番も知名度もおかまいなし。好きな曲を、好きなように、好きな顔で、好きなアレンジで、声に出して歌う。下手くそな歌だって、自分が気持ちよければそれで100点です。
歌っているのは自分のはずなのに、ひとりでにリズムを刻みだす手や足に苦笑してみたり、「わたしってこんなにはっちゃけられる人間なんだ」と気付いたり、普段は聴きながす歌詞が妙に刺さってしまって涙ぐんだり。一人でカラオケに行くと、社会で真っ当に生きていくための武装をぜんぶ取り払った、無防備な、だからこそ愛おしいひとつの生命体としての “自分” と出会えるような気がするのです。
「ひとりカラオケ」のように、社会に着せられたいろいろを一旦脱いで、たった一人の、愛おしい生命体としての「自分」を取り戻す勇気を与えてくれる作品をご紹介します。
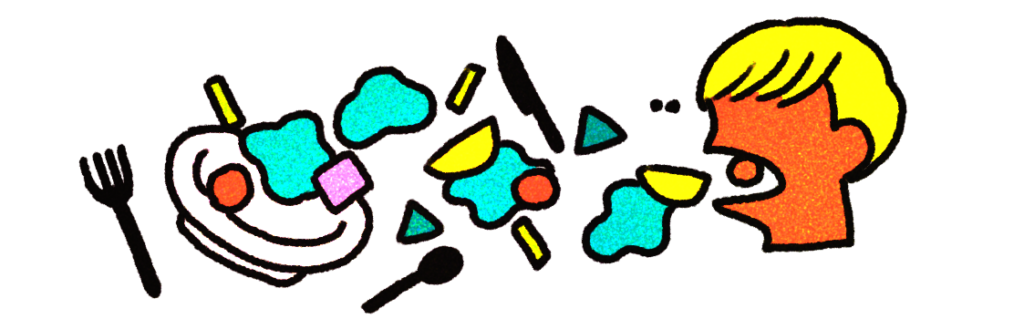
—sponsored—



