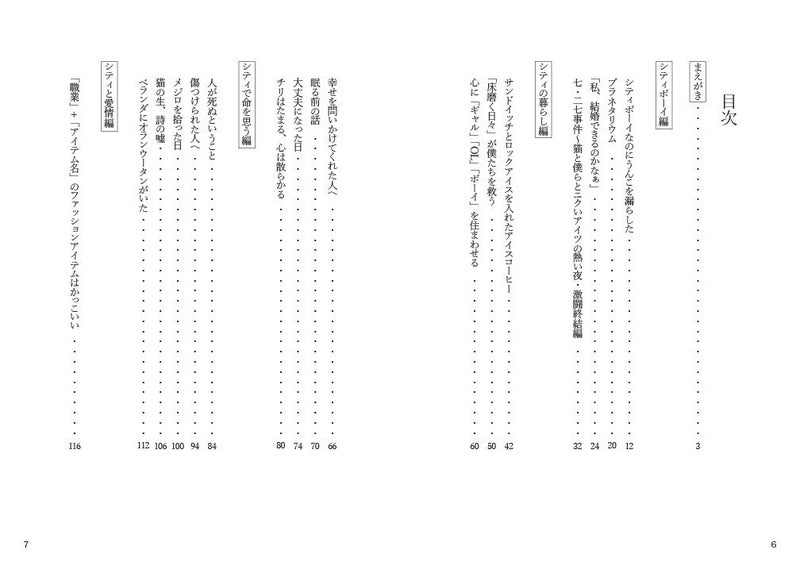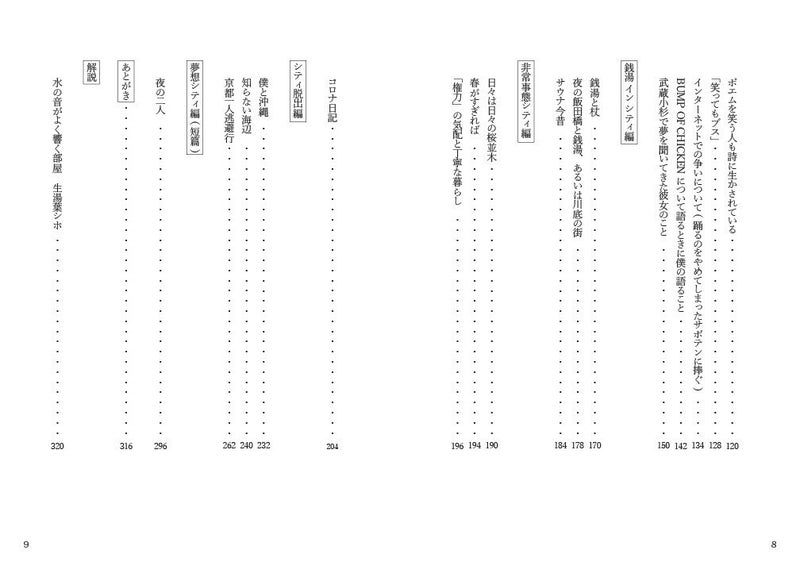(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会
言葉とは何だろう。言葉が通じるとは、話をするとは、どういうことだろう。言葉を使うことは否応なく、言葉を使わなければ出会うことのなかった深い深い孤独と対面することでもある。同時に、言葉がなければ見ることのできない祝福の光を浴びることでもある。そのような孤独の暗闇と、トンネルの先にある朝の海のような眩しい光とのあわいを、一台の赤い車が走ってゆく。
『ドライブ・マイ・カー』という映画について語る時、まず僕はこういった抽象的なイメージを語らなければならない。すぐさま細部を語るには、あまりにこの映画の引力が強すぎる。
文・すなば
1991年生まれ。会社員として働く傍ら文筆家として活動。海とシティが好き。2021年10月に初の単著『さよならシティボーイ』(トーキョーブンミャク)刊行。
本当は誰も、同じ言語を使ってなどいない
主人公の家福悠介(西島秀俊、以下家福)は、舞台俳優でもあり舞台演出家でもある。映画の主要な舞台は、国際演劇祭を控える広島。そこで公演される戯曲『ワーニャ伯父さん』を成功させるために、演出家の家福は稽古に力を尽くす。
家福の演出する舞台は、多言語が入り乱れる独特のスタイルだ。ワーニャを演じる若手俳優の高槻(岡田将生)には、エレーナを演じるジャニス・チャン(ソニア・ユアン)の北京語が分からない。同じように、その二人はソーニャを演じるイ・ユナ(パク・ユリム)の韓国手話が分からない。分からないが、『ワーニャ伯父さん』の台本という共通のテキストを通して、それぞれの言語の表象と意味を徐々に結びつけながら、チェーホフの描く苦悩する人間たちを演じていく。

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会
スクリーンに映る彼ら、彼女らの姿を見て、僕は思い知らされる。言葉は頼りなく、あてにならない。それでも僕らは不完全な言葉を尽くし、その伝わらなさに煩悶としながら、言葉によって分かり合おうとしなければならないのだと。
人と人が分かり合う “よすが” としての言葉の不便さ、不完全さは、この映画の至る所で象徴的に表されている。それは、家福の妻である音(霧島れいか)がベッドで語る謎めいた物語であったり、異なる言語が飛び交う舞台『ワーニャ伯父さん』や『ゴドーを待ちながら』であったりする。
たとえ同じ日本語の話者であっても、言葉によって、相手が伝えたいもの全てを汲み取ることはできない。換言すればそれは、言葉によって意味を伝え合い、コミュニケーションが成り立っているように見えている者同士でも、その実、使っている言語は一人ひとり違うということだ。僕たちは実のところ、同じ「日本語」という言語を話しているわけではない。「日本語」というコードのもとに自分だけのテキストを創り出し、相手に対していわばそのテキストを押しつけている。全てのコミュニケーションは異言語コミュニケーションなのである。
オルガスムの中で、自分の記憶に残らない物語を喘ぎながら紡ぐ音は、どうしようもない言葉の属人性――いわば言葉や、言葉を使う人間が持つ宿命的な孤独を体現する。彼女が物語を通して本当に伝えたかったことは、家福には伝わらない。一方で、その物語の最も身近な聞き手である家福は、異なる言語を使う者同士が共通のテキストに身を投じる「舞台」を演出することで、一人ひとりの言語が成す壁を曖昧にする試みに身命を賭ける。それはまるで、妻の聞き難い言葉に夜ごと晒される家福の、「言葉は違う。言葉は分からない。それでも分かり合いたい」という飢渇を伴った祈りのようだ。

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会
しかし家福は、そんな自分の「分かり合いたい」という飢えにすら自覚的ではない。原作である村上春樹作品にしばしば見られる、理性的すぎ、優しすぎる男性の性質を、彼もしっかりと持っている。そして夫婦は愛し合ったまま、互いを分かり合えず、伝えたいことは伝わらないままに、二度と会えなくなってしまう。
二組の夫婦から見えるもの
家福は、音を深く愛しながらも、彼女の心の奥底にある「どす黒い渦のようなもの」に最後まで触れることができないでいたのだという。それは、二人が夫婦としてはあまりにも大きな悲しみを背負っていたからだ。しかし、二人で背負うべき悲しみは、家福の態度――妻を愛し、できる限りの平静さで二人の生活を悲しみから守ろうとする、どこまでも理性的で優しい態度によって、かえって取り返しのつかないほど、音の深いところに刻み込まれてしまった(そしてその悲しみは、音の無意識から「物語」の形を借りて夜ごと家福にぶつけられる)。

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会
そんな二人と、明確な対比関係に置かれた夫婦がいる。発話ができず、韓国手話を操る女優のユナと、演劇祭の運営幹部であるコン・ユンス(ジン・デヨン)の二人である。この夫婦もまた家福夫妻と似た悲しみを背負っているが、その関係性はほのぼのと温かい。家福が運転手のみさき(三浦透子)と共に彼らとの食卓を囲むシーンは、僕がこの映画で最も好きな場面だ(そういう人は多いのではないかと思う)。
日本では、ユナの唯一の言語である韓国手話はほぼ通じない。そんな妻が寂しく不安な思いをしないか、心配はなかったのかを問われてユンスは、「代わりに私が百人分、彼女の話を聞こうと思いました」と言い切る。
なんて優しく、重心の据わった言葉なのだろう。夫婦が乗り越えてきた悲しみの大きさ、そのために交わされた対話の数々と、話すたび二人の心につく傷、その一つひとつを労りあってきたであろう温かで痛切な日々が、スクリーンの向こうに見える気がした(たった一言でそこまでの姿を想起させるジン・デヨンは恐ろしい役者だと思う)。
「話を聞く」とは、この夫婦にとっては言葉通りの意味ではない。表情、手の動き、目の動き、それらを注意深く正確に捉えないと、ユンスはユナの使う「手話」という言葉を「聞く」ことができない。彼にとって手話は当然に第一言語ではないから、「話を聞く」にはそれなりの努力が必要なはずだ。そのような行為を百人分、妻に捧げようと思ったとユンスは言っているのである。自分の慣れ親しんだ言語でさえ、人はコミュニケーションに難儀するというのに。
家福が演出する『ワーニャ伯父さん』でも、稽古中に最初の化学反応が起きたのはユナ演じるソーニャが絡むシーンだった。家福曰く「自分自身が引きずり出される」というチェーホフのテキストの魔力を最初に手中に収めたのは、誰よりも言葉の通じなさを味わい、それを乗り越えてきたユナなのである。しかしユナも、ユンスという聞き手がいなければ、この境地に辿り着くことはできなかったはずだ。

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会
聞き手がいない孤独、聞き手になれない孤独
きっと人は、生涯にたった一人でも、自分の言葉に本当に耳を傾けてくれる人がいれば、それだけで生きていけるのだろう。そう思いながら『ドライブ・マイ・カー』の群像劇を追うとき、僕は、家福や音やみさきや高槻の、一人ひとりが抱える孤独の暗闇に思いを寄せざるを得ない。
彼らがさまよう孤独とは、自身の聞き手がいないことの寂しさがもたらす暗闇だ。どんなに声を発しても、誰の耳にも本当の意味で自分の声が届くことはない。そうしてむなしく反響する自身の声が、心に少しずつ暗がりを作っていく。
同時に、孤独とは自身が聞き手になれないことでもある。自分自身の中に、誰にも聞き取ってもらえない声がわだかまっているから、相手の中にあるそのような声を聞くことを恐れてしまう。そうして孤独と孤独は交わらずに、ただそこに存在し続ける。

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会
広島で家福の運転手を務めるみさきについて話そう。彼女は、言葉のプロフェッショナルが多数登場する劇中の人物の中にあってなお、言葉に対する最も鋭い感受性を持っている。その感受性を獲得するまでの間、彼女は北海道の小さな村で生まれ暮らし、不安定な母の言葉に耳を傾けてきた。優れた聞き手であるみさきはしかし、自身の言葉を誰かに聞かれることはない(誰よりも言葉を聞いていた母にさえも)。その孤独は、彼女が北海道を出るきっかけとなった出来事によって一線を超える。
みさきが運転する家福の愛車、真っ赤な「サーブ 900」は、家福にとって慣れ親しんだ移動手段以上の意味を持っている。テープに吹き込んだ妻の声が流れる車で一人移動することは、敬虔な宗教者が日ごと捧げる祈りのように、彼が生きていく上で欠かすことのできない習慣だった。演劇祭の規定とはいえ、みさきに愛車を預けることを家福は躊躇するが、その運転技術の巧みさから渋々了承する。しかし愛車を任せる動機はきっとそれだけではない。家福はテストドライブの時点で、寡黙なみさきが誰よりも優れた聞き手であることを無意識に感じ取っていたはずだ。

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会
毎日の往復の中で、二人はぽつぽつと会話を交わすようになる。やがて家福は、みさきの中に自分が喪ったものの面影を見出す。妻にできなかったことを、彼は少しずつ、みさきに対しては試みてゆく。人の話を聞く。たったこれだけの、どこまでもシンプルで、どこまでも難しい営みだ。
この物語の最終盤、家福とみさきは、赤いサーブで長い長いドライブに出かける。夜を徹し、長いトンネルを抜け、海を渡り、音もない真っ白な雪の原野に至り(このシーンでは文字通り “音が消える” )、みさきの故郷にたどり着く。二人はそこで、それぞれが失くしてしまったものの前で、初めて本当の会話をするのだ。家福は音への思いを、恐らくは彼の生涯で初めて激しく吐露する。子どものような顔で泣きじゃくりながら、悲しみや、怒りや、大きな愛情を、今はもういない音に伝えようとする。そして僕たちは、人が救われる瞬間、というものを、スクリーンの中に見ることになる。
その先にある光
なにゆえに、本当の意味で人の話を聞くことは、これほどまでに難しいのか。家福とみさきが旅立つ少し前、車の中で高槻が家福に対して語ったことが、その本質を突いている。同時にこの言葉は、聞き手がいない孤独、聞き手になれない孤独から脱するための唯一の方法を語ったものだ。ここでその言葉を書き起こすことはしないけれど、きっと本当は、誰もが気づいていることなのだと思う。だがそれゆえに、行うのは難しい。
人はきっと、傷つくべきときに傷つき、悲しむべきときに悲しみ、それをぶつけるべき相手にぶつけないといけない。そうして自分自身も、大切な他人にとって、そのような相手でないといけない。悲しみの先の光を見るためには、言葉の不完全さがもたらす深い断絶の闇を乗り越えなければいけない。光もまた、言葉がもたらすのだから。
この映画のラストシーンは、その光を見せてくれた。

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会
そして、その光を目の当たりにした僕が言えることは少ない。照らされたことのない深みを照らされると、人は言葉を失うのだと知った。だから、ほんの少し角度を変えて、今度は原作について語り、この映画を観た後の僕自身の変化について少し語って、終わろうと思う。
村上春樹は原作『女のいない男たち』で、大切な人を喪ってしまった(あるいは何の予兆もなく去られてしまった)後の、主観的な世界を指してこう書いている。
その世界では音の響きが違う、喉の乾き方が違う。髭の伸び方も違う。スターバックスの店員の応対も違う。クリフォード・ブラウンのソロも違うものに聞こえる。地下鉄のドアの閉まり方も違う。表参道から青山一丁目まで歩く距離だって相当に違ってくる。たとえそのあとで新たな女性に巡り会えたとしても、彼女がたとえどんなに素晴らしい女性であったとしても(いや、素晴らしい女性であればあるほど)、あなたはその瞬間から既に彼女たちを失うことを考え始めている。
(中略)
なぜならあなたは、女のいない男たちになるのがどういうことなのかを、既に知ってしまっているからだ。あなたは淡い色合いのペルシャ絨毯であり、孤独とは落ちることのないボルドー・ワインの染みなのだ。そのように孤独はフランスから運ばれ、傷の痛みは中東からもたらされる。女のいない男たちにとって、世界は広大で痛切な混合であり、そっくりそのまま月の裏側なのだ。
この映画の原作の短編集は、表題作『女のいない男たち』のこの結びの文章をもって完結する。つまり、村上春樹が原作で語ったのは「ここまで」なのだ。かけがえのないたった一人を喪った男が、その後の世界を生きることの耐え難い孤独。自分が今まで住んでいた世界とよく似た別の世界に迷い込んでしまったような、拭い難い違和感。
人生では、理不尽な別れはいつだって唐突に訪れる。そこには何の法則も信念も教訓もない。意思や意図さえもない。村上春樹が一貫して読者に投げかけてきたのは、その理不尽な世界で「君はどう生きるか」ということだ。「その先」は作品では語られないし、おそらくこの先語られることもないだろう。誰もが目を背けたい世界の本質的な空虚さを彼の作品から投げかけられた時、僕たちは思わず立ち止まって自分の両手をじっと見つめてしまう。
でも、抗うすべはあった。ちゃんと自分の手元にあったのだ。濱口監督は過たずそのすべを察知し、『ドライブ・マイ・カー』という映画を作ることで、村上春樹の問いに彼なりの回答をしたように思う。

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会
世界を作り変えてしまうほどの、深い孤独と断絶の闇。その暗闇の底を抜け出て、「その先にある光」に向かって走る、一台の赤い車。この映画がくれたイメージは、この先も僕の中でずっと消えずに残り続けるだろう。これから先、幾度の別れや裏切りや喪失があろうとも、そのたびに言葉を尽くし、悲しみと相対することができるだろう。この映画の光について直接語ることはできない。でも僕は本当に、この映画を観ることができてよかったと思う。
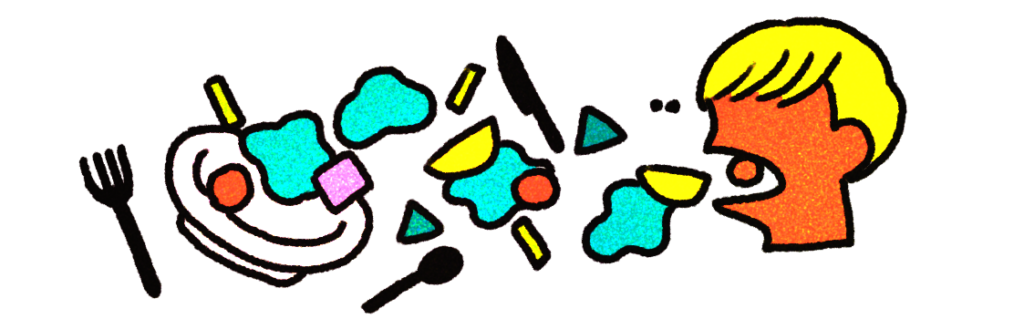
文・すなば
編集・和島咲藍

実際あると正直すごい嬉しいです(店主より)
【すなば、上洛】

1月16日の文学フリマ京都に、トーキョーブンミャクが出店します。すなばさんに会えるチャンスです。『さよならシティボーイ』はもうお持ちですかな? まだの方はぜひ京都で! フラスコ店主も居るかもしれませんよ。(店主より)
▼『さよならシティボーイ』の目次です!