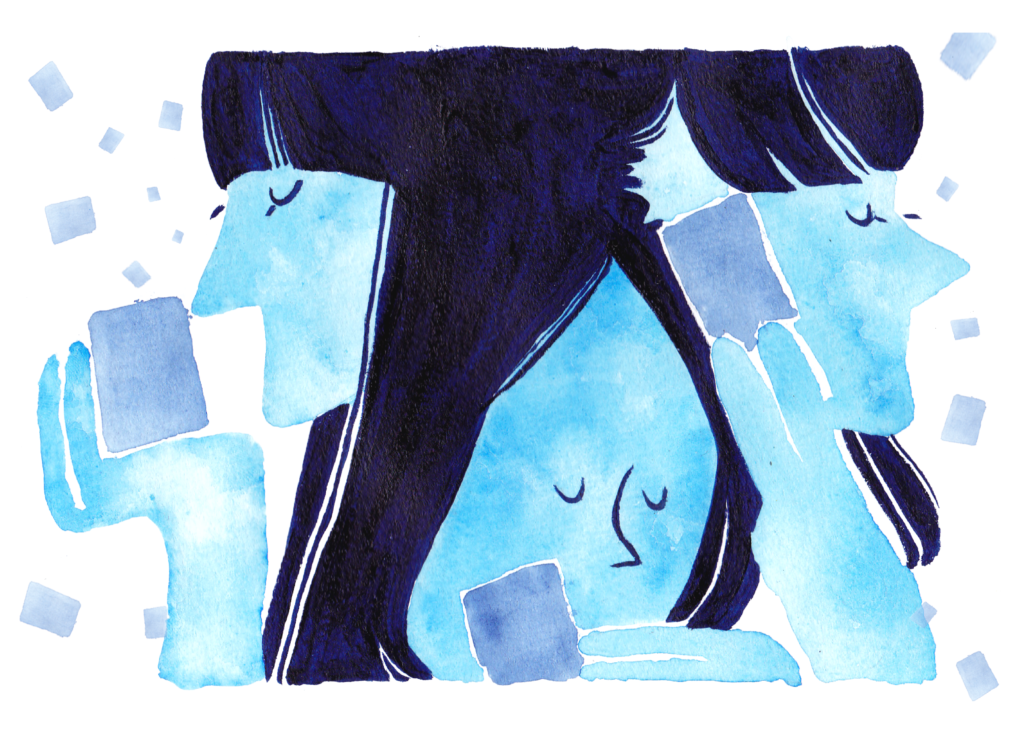平成の遺産。映画「ちはやふる」三部作をそんな大仰に表現することだって僕はもうためらいません。
しかしながら、残念なことにこの映画には旬がない。夏に甘酸っぱい日本のアニメ映画を見る。またはクリスマスに『ホーム・アローン』(または『ダイ・ハード]』でも構いませんが……)というような季節性を帯びた作品ではありません。あのSF映画のアノ技術が実現した? そういやどんな話だったっけ。という機会にも到底恵まれないでしょう。
じゃあなぜいま?そんな声も聞こえてきそうですが、僕たちの答えはこうです。旬がない。だったらいつでも。
そんなわけで今月の特集では、小泉徳宏氏が監督する「ちはやふる」シリーズの魅力をお伝えしましょう。
丁寧に積みあがった「上の句」から「結び」まで

(C)2018 映画「ちはやふる」製作委員会 (C)末次由紀/講談社
今回お伝えしたいのは、「ちはやふる」が三部作として非常に優れており、まとまりと拡がりを兼ね備えるシリーズだったということです。
「上の句」、「下の句」、「結び」がそれぞれしっかりと意味を持って機能しているのです。それぞれの作品ごとに意味があり、前作のエッセンスに立脚したメッセージを唱えています。同じことはしていません。無論、間違っても「ゴメン!やっぱり今までのことは全部なかったことに!」という茶番タイムトラベルでうやむやにしてしまうこともありません。
むべなるかなシリーズものは前作を踏まえて鑑賞した方が楽しめます。プロットは知っておくにこしたことはないし、キャラクターへの愛着も増すのですから。しかし「ちはやふる」のシリーズ構成の妙はそうした次元のその先の景色を臨むのです。
筆者の考える各作品のエッセンスはこうです。
上の句:千早によるチーム編成
下の句:チームの成長とは?
結び:無形の文化を残すということ
それぞれ順番に見ていきましょう。
「上の句」では主人公・ちはやが部活の成立条件であり、公式の団体戦の定員である「5人の部員」を集め・名実ともにチームを結束させるまでを描きます。「下の句」の要は、國村隼の演じる原田秀雄の「個人戦こそが団体戦だよ、メガネくん」という言葉にすべて集約されているようです。手垢のついた表現で大変恐縮ですが一言で一般化するなら “One for All, All for One ” といった具合です。そして「結び」では、チームあるいは組織という単位で切磋琢磨する営みそのものへの賛歌を送ります。これまで描いてきたキャラクターたちだけではなく、それ以降の世代の、いまだ世に知れない者たちにはしごを掛けて手招くのです。
ここで特筆すべきは、どの作品も一貫して人と人との関係性に目を向けられているということ。繋がることでひとりでは成し遂げられない困難に打ち勝つのです。かるたの試合の結果を知ってしまったとて問題なし。何度鑑賞しても胸に刺さる所以はきっとここにあります。結果の形ではなく過程の手触りを大切にするからこそ、何度鑑賞しても僕たちの涙腺は閉まらないのです。
なお、これらは恋愛の物語ではないと筆者は声を大にして訴えます。時折そのようなスパイスも香りますが、どうにも主題とは言い難いように思えてしかたがないのです。閑話休題。それに関してさらに詳しくは別の記事に譲りましょう。
とにかく、「ちはやふる」は嘘いつわりのない正真正銘のトリロジーとして成立しているのです。「上の句」があるから「下の句」があり、「下の句」なくして「結び」はありえない。「上の句」から「結び」までの3作品が綺麗に積み重なって構成されており、すべて鑑賞することで人間の繋がり・関係性といったテーマが結実します。
実際の制作事情を覗いてみると映画「ちはやふる」は当初より二部作として制作され、「結び」の正式な制作発表は「上の句」の公開とほぼ同時期 [*] でした。しかし、「結び」は決して蛇足にならず、着実に積み上げた上の句・下の句を崩すことなくより大きな視点を僕たちに与えてくれたのです。
[*]オトナアンサーによる小泉徳宏監督インタビューより
では、その “大きな視点” とは何だったのでしょう。「結び」が描く着地点に迫ります。
最後に示される千早の進路
最後の場面を思い出してみてください。上の句、下の句、そして結び。すべての戦いを終え、場面は切り替わり数年後の近江神宮。そこには晴れ舞台に立つ高校生選手に檄を飛ばす大人になった千早の姿がいます。彼女は教職を修め母校へ凱旋し、かるた部の顧問となったのです。
教諭の本分はあくまでも教科指導であり、部活指導にばかり熱を入れるのは不誠実だという議論は一旦忘れましょう。千早とてもう17歳ではないので、日々やるべき仕事にも精を出していることでしょう。
自らが創設して以来、続いてきた部活の指導者となり、より多くの人間にかるたの技と魅力を伝える立場になる。このオリジナルの展開を前に僕ははっと胸を突かれかたまりました。きっとこの瞬間のために3つの映画があったのだ。この一瞬を目指して作られてきたのだ、と。
「結び」では、意思を伝承してチームやルール、営みそのものを永続させることの素晴らしさを示し、その可能性を僕たちに開いてくれました。
きっと1000年残る映画だ

(C)2018 映画「ちはやふる」製作委員会 (C)末次由紀/講談社
あのエピローグですべての点が繋がり線になります。それまでも時折顔を出していた、かるたの札に刻まれた「和歌」が時代を超越して現在まで伝わっていることへの畏敬の念。これが「脈々と続くであろう部活」とぴたりと相似関係を結ぶのです。
ふたつの無形物がパラレルに描かれています。いいえ、よく考えると “伝承される目に見えない文化” はこれだけではありません。かるたという遊戯もまた無形文化のひとつでしょう。
そしてさらに踏み込んで考えれば、「映画」だって同じではないでしょうか。記録物として時間を飛び越え未来へジャンプできるフォーマットの「映画」という存在も、1000年残り続ける可能性を秘めています。彼らは普段は目に見えない営みを、形にして僕たちに見せてくれたのです。
前評判の大きさに負けず劣らず実際の評価もまた高かった本作への監督の意気込みや情熱は引用しはじめるときりがありませんが、たとえば代表してこんな言葉を引いてみましょう。
原作における『情熱』『青春』は(原作者である)末次さんの大きなテーマだと思いました。『運命』『絆』はどちらかと言うと(原作では)サブ(の扱いのテーマ)で、僕が勝手に膨らませたものです。
トレンドニュースから引用
(括弧内編集部加筆)
原作に飲まれず、貪欲に新しい作品を世に残そうという姿勢が伝わってきます。もちろんこうした意欲的な言葉は枚挙にいとまありません。ここまでくれば無論言わずもがなではございますが、やはり彼は確固たる意志をもって、原作漫画を媒介に新たな表現を目指しています。まちがっても業界に蔓延する「実写やっつけ仕事」などではないはず。血の通った作品なのです。
また忘れてはならないのが、映画は監督ひとりでは作れないということ。多くの人たちが共鳴しながら制作されるものです。“チームで” つくりあげる「映画」という媒体に関わるスタッフたちだからこそ、この「ちはやふる」を実現できたのではないでしょうか。こんなにもエンドロールに身を焦がした映画に、僕は出会ったことはありません。きっと1000年後も愛される映画になるはずです。

文・川合裕之
編集・和島咲藍
紙になりました!
この記事のシリーズが紙のZINEになりました。base で販売しています。
詳しくは下記URL からご確認ください!
https://frascohtn.base.shop/items/38592671
【参考】
「「ちはやふる」シリーズ完結へ! 小泉徳宏監督が語る、その魅力と公開前の思い」
2018.03.10 オトナアンサー
https://otonanswer.jp/post/12009/2/
「フィリピン日本映画祭 小泉徳宏監督インタビュー」2018.7.26 JAPANESE FILM FESTIVAL MAGAZINE
https://www.japanesefilmfest.org/ja/all/news/2047/
「小泉徳宏監督&北島直明プロデューサー、『ちはやふる』は実写化ではなく映画化した作品」2018.3.15 トレンドニュース
https://trendnews.yahoo.co.jp/archives/542069/