「あのときこんな会話したよな」
思い出話をしている途中、相手がこんなふうに言ったりする。
「そうやったっけ? そう言われたらなんかそうやった気するな〜」
みたいに返してしまう。自分のあまりの覚えてなさに愕然とする。恥ずかしくなるし、申し訳なくもなる。 “あのとき” を共有したはずなのに、自分のせいでその共有の度合いが弱くなる感じがする。相手とのつながりを、こちらが軽んじているように思えて、薄情なやつだと悲しくなる。
自分の過去の記憶を語ること、相手の記憶の語りを聞くこと、記憶を共有すること。ひとりずつで生きる私たちはそうやってつながりを作る。もちろん記憶だけがその材料ではないと思うけれど、記憶が果たしてくれる役割もやはり大きいだろう。でも記憶はままならないものだし、ままならないものを材料に作られるつながりも、きっとままならないものだ。
岸政彦の新作小説集『リリアン』は、記憶とつながりについて記した物語を収めている。表題作「リリアン」を、記憶・会話・アナロジーという3つのキーワードから読んでみようと思う。
「リリアン」のあらすじ
街外れで暮らすジャズベーシストの男と、場末の飲み屋で知り合った年上の女。スティービー・ワンダーの名曲に導かれた二人の会話が重なりあい、大阪の片隅で生きる陰影に満ちた人生を淡く映し出す。表題作の他、女性のひとり語りの短篇「大阪の西は全部海」を収めた、話題の社会学者による哀感あふれる都市小説集。(新潮社ウェブサイトより)
記憶——忘れていくな。
こんな大事なことやけどな。
記憶とはままならないものだ。あまりに断片的で、脆い。思い出せないことがたくさんある一方で、なぜかずっと覚えていることがあり、覚えている自覚すらなかったことをふと思い出すこともある。
筆者の私は現在、就職活動をしている。まずは企業にエントリーシートを提出しなければならない。業界や職種によって回答すべき設問の内容には傾向があるが、ほぼ必ず「あなたの人生で最大の失敗は何ですか?」というような、過去の経験を問う箇所がある。
このような設問に出会うたび、自分がいかに過去のエピソードを覚えていないかを突きつけられる。生きていれば、大小に差はあれど「失敗」や「挫折」、「後悔」といった経験をしてきているはずで、それらに対してどのように行動したかをもってその人の人間性を見よう、という意図は理解できる。理解できるだけに、即座に適切なエピソードを語ることができないことで心にうっすらと陰が差す。つい「即座に」と書いたが、時間をかけてもあまり変わらない。差した陰は居残る。
その陰の内訳は、経験したはずの「失敗」に対するそのときの感情を、すぐに忘れてしまっている自分の味気なさのようなものだと思う。たとえ嫉妬のようなネガティブに捉えられがちな感情でも、それを保持して原動力にしている人を見ると、なんだか魅力的に感じる。
あったはずの経験や感情を思い出せないとき、特に記憶のままならなさを感じる。失われてしまったものに対する惜別の念がそうさせるのだろう。思い出せないことはなかったことと同じになってしまうことに対する恐怖もある。あったことを自分でなかったことにしてしまうのは、悲しい。だから覚えていたいのに、忘れてしまう。記憶とはままならないものである。

「リリアン」はそうしたままならない記憶を少しずつ縒り合わせてできた一本のひものような小説だ。出来上がった小説のひもは決してきれいな一色だけではないし、突然色が変わったり、また戻ったりと、記憶と同じくらいはっきりしないものにも見える。断片的な記憶を、きれいに整えすぎないように、生のままで縒り合わせていく。岸政彦はそのような作家であるし、「リリアン」はそのような作品だ。
作品中の語りは一貫して、語り手の〈俺〉の回想として書かれている。しかしそれがどの時点から想起されているのかは定かではないように思われる。語られる記憶も時系列がはっきりとはしておらず、順不同で連想的だ。
たとえば作品の序盤、「マクド」で美沙さんと美沙さんの子どもについて話すその会話の語りは、店内にいる小学生や中学生へ向けられた視線から、自分の幼少期の回想へとシームレスに接続し、そのまま〈俺〉の部屋の場面へと移っていく。それが同じ日の、後続する場面なのかは示されない。ふつうに読んだらそうだと言われるだろう。たしかにそうかもしれないし、でもそうじゃないかもしれない。どちらにせよ、それらの場面が縒り合わされて語られている、それがこの作品の語りなのだ。
忘れていくな。こんな大事なことやけどな。
『リリアン』62頁
作品の語りの構造だけではない。〈俺〉も美沙さんも自分の記憶について会話をしている。引用したのは美沙さんの発した言葉だ。美沙さんも〈俺〉も自らのままならない記憶をお互いに話しながら、そのままならなさと対面していく。
めんどくさい言い方をすれば、「リリアン」は記憶についての語りと、 “記憶についての語り” についての語りという二重構造になっていると言えるだろう。それによって記憶の断片性が生のまま保存されているのではないだろうか。
関連記事:岸政彦『図書室』—思い出すこと/思い出せないこと/思い出さないこと—
岸政彦は「生活史」という調査方法を用いて研究を重ねてきた社会学者である。前作『図書室』に響く、人々の記憶の語りに対する彼の態度を考えた記事。
会話——あのな、
うん、
もっかいリリアンの話して。
「リリアン」の語りの大きな要素に「会話」がある。取るに足りない、小さなやりとりを一つひとつ重ねていく小説のスタイルは前作「図書室」から引き継がれている。
「あそこに餃子屋あるやんか。ひなた商店街の入り口のとこ」
『図書室』51-52頁
「あー。うーん、駅のあっち側あんまり知らんねん。僕とこ反対側やから」
「あ、そうか。ほなどこで餃子食べるん?」
「餃子あんまり食べへんな。焼売の方が好きやな。でも焼売もそない食べへんかも」
「ほな何食べてんの」
「何て。ふつう。カレーとか」
「きのうカレーやったわ」
このようななんてこともない会話を読むと、それがなんてこともないがために、かえってかれらが「そこにいた」ことを感じる、ということを以前『図書室』の書評で書いた。些細で、そのぶん現実味のある会話は、断片的な記憶と密接に結びついている。ままならない記憶のなかになぜか居座り続けている会話の断片。小さな断片でも、反芻されれば大きく見えてくる。なぜかそれを忘れられないということ自体にリアリティが宿ってくる。岸の小説のなかの会話は、そのような存在であるように思う。
「リリアン」でも会話、特に〈俺〉と美沙さんの会話は重要なピースである。しかし、前作「図書室」からの変化として、その記述の仕方の区別が生まれている。それは「かぎかっこ」のつかない会話だ。
あのな、
『リリアン』54頁
うん。
もっかいリリアンの話して。
なんで
ええから。
なんでよ
ええから。
〈俺〉と美沙さんは、それぞれの記憶について会話することで、お互いのことを知っていく。その際に二人は「かぎかっこ」のつかない会話をする。だいたいは段落ごとにそれぞれの発話が表され(終盤はそうではないが)、そのそれぞれも句点ではなく読点で終わったり、なんなら何もつかずに次の発話に移ることもある。
この「かぎかっこ」のつかない会話は、〈俺〉と美沙さんの会話にしか適用されない。〈俺〉の周りの音楽周りとの会話はふつうに「かぎかっこ」つきで記述される。それだけでなく、作品後半、ジャズクラブでの美沙さんとの二人の会話にも「かぎかっこ」はついている。
「かぎかっこ」のつかない会話が表すのは何か。紋切り型の表現しかできなくて恥ずかしいが、筆者は “世界に二人しかいないような感覚” なのではないかと感じる。先述したように、そもそもこの作品は回想のように語られている。会話が「かぎかっこ」無しで記されることで、どちらの発話なのか判然とは区別ができないような、互いに溶け合ったような記憶のなかの会話として読むことができる。
語り手である〈俺〉は、この「かぎかっこ」のつかない会話の途中で次のように吐露している。
一瞬だけ、ふたりの脳がつながって、美沙さんのまぶたの裏側に映る風景が見えたような気がした。
『リリアン』79頁
私たちは誰かとつながりを持ちたいと願うが、ひとりずつでしか生きていけないという事実に時おり圧倒される。ままならない記憶を少し共有したくらいでは、相手の過去を背負うことはできない。でもだからこそ、つながれたと感じる瞬間に喜びが生まれる。「かぎかっこ」のつかない会話は、そのつながった感覚を表しているのではないだろうか。
——————————————————————–
——————————————————————–
アナロジー——あれと同じやな。
みんななんか似てる。
ままならない記憶について語り合うことで、「かぎかっこ」で区切られずに溶け合っているように感じることができる、いや、できた。その溶け合いの記憶についての語りがこの作品なのかもしれない。
〈俺〉と美沙さんの会話に何度も登場したもうひとつの特徴、それは物事をアナロジーで直感的に捉える仕方だ。アナロジー(類推)とは異なった物事のあいだに似ているところや共通点を見出す捉え方のことである。
作品冒頭からしてそうだ。
ひとりで家を出て飲みにいくとき、誰もいない浜辺でシュノーケルをつけて、ゆっくりと海に入っていくときの感じに似てるといつも思う。
『リリアン』7頁
そして玄関先で、右にいくのか左にいくのかいつも一瞬迷う。いつも、シュノーケルをつけて生ぬるい海のなかに体ごと入っていく、あの感じに似てるなと思う。脇腹や太股を、冷たくて温かい海水がゆっくりと撫でていく。息を止めて深く潜ると、音が消えていく。方向も時間も、自分の名前も忘れていく。あの感じ。
『リリアン』11頁
この夜の街と海のアナロジーは、作品を通して流れ続ける。〈俺〉がコントラバスの練習をしている音を聞いた美沙さんは、「鯨の歌みたいやな」(36頁)と呟く。鯨の歌を聞いたことがないのに。
二人とも、こうした「似てる」という直感で物事を把握していくような語りを頻繁に行なっている。認知言語学という学問分野では、人間の物事の捉え方の根底にそうした比喩=メタファーがあるという指摘がなされている(*1)。時間のような目に見えないものを捉えるとき、それを水のような流体をメタファーにして、「時間が流れる」と言ったりする。あれとこれが「似てる」という直感は、人間が世界をなんとか理解しようとする、その大切な道具なのだ。
繰り返しになるが、「リリアン」における〈俺〉と美沙さんの記憶とその語りは連想的に広がっていく。「似てる」という感覚からつながりを作っていって、そのつながりを使って理解していこうとする。そのつながりは必ずしも過去から未来へと直線的に進んではいかないし、出発点へと戻ってこないこともある。直感的なアナロジーで作ったつながりを通して世界を見る。
つながってると思うねん全部。
『リリアン』167頁
そのつながりを、美沙さんと〈俺〉のあいだに作ることで、二人自身もつながることができる。記憶というままならないあやふやなものを材料にして、会話によってそれを共有し溶け合って、直感的なつながりを作る。つながることができた、という、その記憶についての語り。あやふやな語りが連想的につながってできたひとつのひも、それが「リリアン」という小説なのだと筆者は思う。
(*1 たとえば次のような解説を参照。「概念メタファーとは何か」)
文・安尾日向
編集・川合裕之(フラスコ飯店 店主)
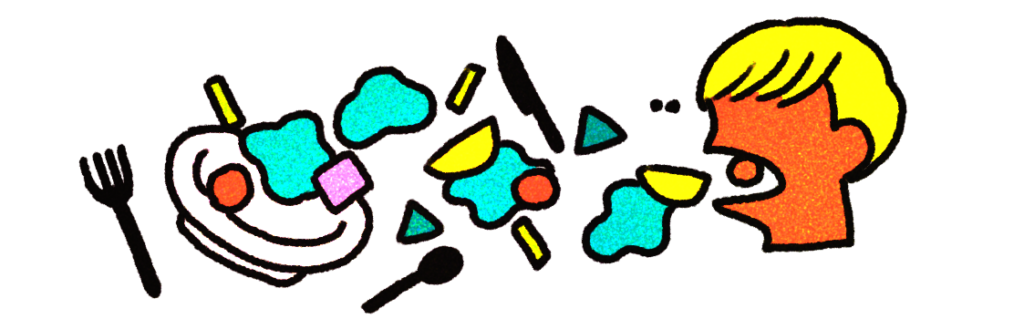
フラスコ飯店の最新の更新をチェックしてみてください!
上のイラストをクリックすると遷移します!
解説:岸政彦『リリアン』(2021、新潮社)

文芸誌「新潮」に掲載された「リリアン」(2020年5月号)、「大阪の西は全部海」(2021年2月号)が収録されています。
芥川賞にノミネートされた第1作『ビニール傘』から、『図書室』『リリアン』と一貫して大阪を舞台にしています。そんな岸政彦と、小説家の柴崎友香の共著エッセイも『リリアン』と同時期に発売されています。その名も『大阪』(河出書房新社)。柴崎友香といえば『百年と一日』(2020、筑摩書房)もすごい小説だったな……。短い時間と長い時間が等価で表現されているような小説で、「リリアン」中の言葉でいうところの「人間要らん」感じもあり、こんなふうな世界の見方もあるのかと衝撃を受けました。あ、またしても連想的にここまで来てしまいましたね。
前作『図書室』の書評もどうぞ
岸政彦『図書室』—思い出すこと/思い出せないこと/思い出さないこと—
岸政彦の新刊『図書室』は、「記憶」についての物語である。ある女性が子どものころを想起する表題小説「図書室」と、著者が出会った大阪という町を書く自伝エッセイ「給水塔」の二編が収められている。どちらも、「いま」から「過去」を振り返り、「そこにいた」人たちや「そこにあった」できごとの存在をたしかめようとしている。「記憶」を呼び起こし、過去を思い出すという営み自体を描いている、とも言えるのではないだろうか。
誰かが「そこにいた」ことがとてもリアルに描かれているのが、「図書室」の特筆すべき点だろう。これはたまたまそうだったわけではなく、「小説なんだから当たり前だろう」という話でもないと思う。著者である岸政彦の本業が、社会学者であることにこそ、その理由があるのだ。
〈続きを読む〉
又吉直樹『劇場』書評もあります
小説『劇場』レビュー簡単に「共感」してくれるな|小説『劇場』レビュー
僕は「劇場」の永田に「共感」できなかった。でも彼の視点で描かれる世界を見て、彼を「理解」しようとした。「理解」できたかはわからない。でも確実に言える。「劇場」という小説は、おもしろい。
〈続きを読む〉




