異様な速さで出世した天才・デイミアン・チャゼルの新作ときいて、見逃さないわけにはいきませんが、今回もまた変な映画を作ったものだなと感心します。
『ラ・ラ・ランド』は好きだったけど、『セッション』は痛々しくて見ていられない。あるいは逆に『セッション』は何度も何度も見返してきたけど、『ラ・ラ・ランド』の甘ったるさが耐えられない——というような人は少なくないのではないでしょうか。
僕もそのひとりでした。この記事は、3時間もかけてハリウッドの栄枯盛衰を描いてそれが結局何なの? という核心を捉えるために書いたものですが、『バビロン』の真の主題がはなんだったのか、を考えるにつれてデイミアン・チャゼルの本性がようやく見えてきた気がします。
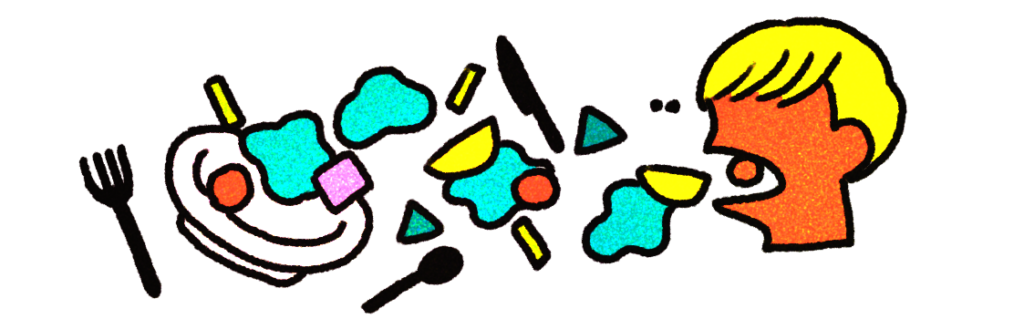
この記事はネタバレを含みますが、ネタバレ無し解説+ネタバレあり考察の2部構成となっています。前半では1920年代のアメリカとハリウッドについての史実を解説します。『バビロン』をさらにもっと細やかに読むための準備運動です。
後半では映画『バビロン』のラストシーンの謎——というには大袈裟ですが——に迫り、その真意を考察することで、この映画の根幹やデイミアン・チャゼルという作家のクセを見抜きます。
mokuji
- 【解説】9つのキーワードで読み解く1920年代のアメリカ
- 「ハリウッド」の起源って?
- 「狂騒の20年代」
- 「ヘンリー・フォードのモデルT」で拡大した自由
- 「禁酒法の時代」
- 「移民」が集まるハリウッド
- 「ジャズ」の黎明期
- 「サイレント」と「トーキー」
- 『雨に唄えば』
- 「夢」の工場とその衰退
- 【総評】バランスの良い優等生的な完成度(ただし……)
- マーゴットロビーは誰をどう演技したのか
- バビロンのあのラストシーンは結局何だったのか?
- 主題は「黄金期」の儚さ:過去に存在する夢
- 『バビロン』でようやく浮かび上がるデイミアン・チャゼルの作家性
- おまけ:【解釈】 “バビロン” というタイトルが象徴するのは?
【解説】9つのキーワードで読み解く1920年代のアメリカ
まずは前知識のおさらいです。未鑑賞の人や、映画序盤に付いていけなかったという人のために簡単にまとめました。
ラストシーンを筆頭に「結局この映画どういうこと?」という疑問をもっと早く知りたい人はサッとスクロールしてください。
というのも、60sや80sに制作されたアメリカ映画(または当時を舞台にした映画)は、ちょっとした映画ファンなら1本や2本は知っているものですが、「1920年代モノ」はあまり数が豊富でないからです。

(C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.
けたたましいエンジン音を鳴らす旧式の車が、荒野をノロノロと走って、かなり無理しながら象を運ぶ——。そんなシーンから始まるこの映画ですが、とくに日本の観客にとってはシンクロするまでには少しだけ時間がかかります。「1924年」と字幕が出ますがこれだけではイメージが掴みづらいかもしれません。
まずは「1920年代のアメリカ」という舞台設定が示す当時の背景についておさらいしましょう。9つのキーワードに分けて紹介します。
「ハリウッド」の起源って? / 「狂騒の20年代」 / 「ヘンリー・フォードのモデルT」で拡大した自由 / 「禁酒法の時代」 / 「移民」が集まるハリウッド / 「ジャズ」の黎明期 / 「サイレント」と「トーキー」 / 『雨に唄えば』/ 「夢」の工場とその衰退
「ハリウッド」の起源って?
日本に住んでいると(少なくとも僕の世代では)物心つくころには「ハリウッド」という言葉がなんとなく映画という言葉の隣に座っていたような気がします。でも冷静に考えるとそもそもハリウッドって? ——そんな素朴な疑問を最初に潰しておきましょう。

(C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.
いわゆるハリウッドの始まりは20年代よりも少し前、1908年ごろです。アメリカ東部——つまりニューヨークなど——が東部が映画の中心地であった当時に、一部の映画会社が西部の地での制作を始めました。その西の新たな本場こそがカリフォルニア州のハリウッド。ロスのすぐ近くです。
東の映画会社との熾烈な競争を避けるためでもあり、なおかつ雨が少ない西海岸は映画を作るのに適した土地でもあったのです。森もあれば海もあり、砂漠も広がっていてロケーションにも困りません。あとは皆さんご存じの通りです。
「狂騒の20年代」
1920年代を日本の元号で示すなら大正9年から昭和元年まで。第一次世界大戦を終えたあとの小康状態です。「狂騒の20年代」と表現されることもあり、工業化により生活様式が大きく変わりました。
消費社会の最先端が過剰なまでに豪華絢爛なハリウッドセレブリティたちの暮らしぶりというわけです。また、映画文化の大衆への浸透も消費社会の成長の延長線上といえるでしょう。
「ヘンリー・フォードのモデルT」で拡大した自由
何の気なしに幾度となく登場人物を次のシーンの舞台まで運んでいる「自動車」も1920年代らしさといえるでしょう。

(C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.
この時期のアメリカでは自動車の低価格化が進み、クルマは富裕層だけの特権的な乗り物ではなくなります。稼ぎのないマニーやネリー・ラロイでさえ(持ってはいないようですが)運転できたことからも、いかに普及していたかが分かりますね。
行動範囲が格段に広がり、かつ移動中も私的な空間に閉じこもることができるという意味で、自動車はまさに自由の象徴です。
その立役者はヘンリー・フォード。部品の均一化と生産工程の流れ作業化で自動車の大量生産に成功し、低価格で市場に供給しました。安くて丈夫な「モデルT」は圧倒的な販売シェアを誇っており、発売開始は1908年にもかかわらず、20年代初頭まで異例のロングヒット。累計販売台数は1,000万台以上です。時間の経過とともに販売価格も積極的に下げられ、1908年に850ドルだったモデルTは1916年には360ドルに。最初の荒野のシーンなどでマニーが乗っていたのは恐らくこの庶民の味方であるモデルでしょう。(日本では「T型フォード」の名称で旧車ファンに親しまれています)
20年代からは同じくアメリカ国内の自動車メーカーであるゼネラルモーターズが頭角を表し、安価なモデルTに一筋なフォードに対して「高級車」路線での戦略で反撃に出ます。『バビロン』でもキャデラックのような重厚感のある高級車が逞しい音を立てて走ります。
あるひとりの技術者によって1903年に設立されたフォード社がモデルTで爆発的な成功を納め、気づけば他社に追い抜かれて衰退の一途を辿ったことにも注目したいです。タイムラインは少しズレますが、フォードの趨勢もまた『バビロン』に似た郷愁を感じさせます。
「禁酒法の時代」
毎晩のような乱痴気騒ぎのガソリンであったアルコールですが、1920年から1933年までアメリカは「禁酒法」の時代。禁止されているのは製造と流通だったので、飲むこと自体は違法ではありませんし、些細な信号無視のような感覚で誰もがお構いなしに飲酒していたことはたしかですが、政府の命で禁酒運動が広まっていたこともまた事実です。
禁酒の主な目的は道徳的退廃の是正と治安維持。
「俺がコーラ10杯飲んだ次の日に記憶を失くしてたとしたら、そんな液体飲むのやめろって言うやろ?」
かまいたちの山内健司の言葉です。

(C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.
要するにそんな訳のわからんもんを飲むなと。『バビロン』の冒頭のパーティーのように、あんなに無茶苦茶になる元凶を絶ってしまおうということです。酒類を提供するナイトクラブは犯罪や売春の温床にもなっていたので、それらを封じ込めたかったという意図も。(結局のところ酒場という存在がグレーゾーンになることでかえって “濃い闇社会” が醸造されることになるのですが ……)
戦争を終え、景気も良く、いつしか政府が介入しなければいけないほど開放的な雰囲気に。当時はハリウッドだけでなくアメリカ全体が騒がしかったようです。
「移民」が集まるハリウッド
ブラッド・ピットの演じるジャック・コンラッドはドイツ系であり、 ディエゴ・カルバの演じるマニー(マヌエル・トレス)がメキシコ系であることも、この時代のハリウッドらしさと言えるでしょう。
かつて第一次世界大戦の亡命先として、 “おもしろければなんでもあり” のハリウッドに世界の才覚が集まりました。困ったのはその2世世代です。
ウェルカム根性抜群の移民の国アメリカ、腕っぷし歓迎実力主義の国アメリカとはいえやはり少数派が安住するにはハードな環境であることは間違いありません。しかし映画産業は才能のある俳優だけで成り立っているわけではありません。安価な労働力として多くの移民労働者が動員されていました。「ハリウッドにいる移民」は大きく二極化していたのです。

(C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.
だからこそ移民2世(彼は映画人2世ではないようですが)というどん底からハリウッド界の頂上付近にまで一気に急騰したマニーのトントン拍子のサクセスストーリーに意味があります。
「ジャズ」の黎明期
『セッション』(2014)や『ラ・ラ・ランド』(2016)に続き『バビロン』(2022)でもデイミアンチャゼルのジャズへの偏愛が垣間見えますが、これには大きな理由があります。
というのも、セレブ揃いのパーティーのバックミュージックに、サイレント映画の現場の雰囲気作りに、そしてトーキー映画の頼もしい片腕としてムードを支配していた華々しい音楽はジャズは1920年代のアメリカの重要な構成要素のひとつなのです。

(C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.
他国に比べて歴史の浅いアメリカにとって数少ない独自文化のひとつであるジャズはこの時代に生まれました。都市で発達を遂げた黒人による新しい音楽です。その小さなうねりは発明されて間もないラジオやレコードを通してすぐに広まりたちまち大流行。教科書的に言えば「ジャズ・エイジ」と呼ばれる時代。(ちなみにそう名付けたのはフィッツジェラルド)
ジャズはいかにもアメリカらしく、1920年代らしい芸術ということです。
この映画ではあまり触れられてはいませんでしたが、酒のあるところにジャズがあり、当時のジャズ奏者は十中八九アフリカン・アメリカン、つまり社会的に弱いマイノリティーであることから、ジャズを含むショービジネスの社会は闇社会と隣接しやすい傾向にあることにも注目です。
「サイレント」と「トーキー」
ご承知の通り、無声映画がサイレントで、それに声が付いたのが「トーキー」です。「トーキー映画」が発明されたことをきっかけに、前者と区別すべく「サイレント映画」という言葉が生まれました。いわば「サイレント映画」は「アナログ時計」や「生わさび」などと同じレトロニムの一種なのです。(正統派漫才もね!!)

(C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.
すべてのセリフを録音するか否かで解釈は別れますが、史上初のトーキーとされているのはワーナー・ブラザースにより制作された『ジャズシンガー』です。いま見ても結構面白いので、当時は本当に革命的だったと思います。
最初に伴奏音楽と効果音をくわえた『ドン・ファン』(1926)年が公開され、伴奏および俳優の歌と同期した『ジャズ・シンガー』(1927)は『バビロン』劇中にも登場した革命的な作品です。
「動く写真」に音声が追加されることで、映画はより写実的になります。かつての字幕のようなこってりとした脚本はむず痒くて恥ずかしく聞こえてしまいますし、大袈裟なマイムも不要なため淘汰されていきます。
さらに、クルマのエンジンや銃声などを聴覚的に再現できることから、新たなジャンルが開拓されることにもつながります。これぞまさしくテクノロジーがもたらした映画の進化ですね。もちろんミュージカル映画の誕生もその一部です。
『雨に唄えば』
トーキーの流行によりハリウッドの無声映画はピンチの危機! という本作『バビロン』と似た舞台設定のミュージカル映画。原題は『Singin’ in the Rain』, 公開は1952年です。タイトルの通り、土砂降りの雨の中で歌い踊るシーンは有名で、全世界で愛されている作品です。

Everett Collection/アフロ
デイミアン・チャゼルも例外でなく、代表作である『ラ・ラ・ランド』の頃からデイミアン・チャゼル『雨に唄えば』に対する偏愛が指摘されており、本人も好きだ好きだと方々で語っています。
「夢」の工場とその衰退
セット、セット、またセット。ネリー・ラロイの初めての撮影現場は、西武の荒地でセットがいくつも立ち並びます。スタジオでの大量生産方式を整え、次から次へと映画を世に放つハリウッド。とくに当時の映画鑑賞は浮世を離れるための気晴らしだったことから、映画を「夢」に見立ててハリウッドは「夢の工場」(dream factory) などと呼ばれていました。
トーキーの登場で変化を迫られた黄金時代は一時的に終焉。いつかは覚めてしまうという意味でも、この時期の映画は「夢」だったのです。
そしてこの「夢」というキーワードはこの映画、ひいてはデイミアン・チャゼルという作家を語る上で非常に重要になってきます。
総評:バランスの良い優等生的な完成度(ただし……)

(C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.
まさに多幸感の塊。こだわり抜いた映像と音楽のマリアージュはデイミアン・チャゼルという作家の真骨頂のひとつと言えるでしょうが、今回もしっかりとお祭り騒ぎの夢を見せてくれました。衣装やセットにも妥協しない写実的な撮影主義の説得力も素晴らしいです。
映画と芸術、そしてそれらを築き上げてきた人たちすべてに対するラブレターでした。
絶景を見せて、そのあと崖から突き落とすのもデイミアン・チャゼルの得意技です。そんなことを得意技にしてくれるなという気もしますが、我が子に厳しく当たるライオンのような彼なりの愛なのでしょう。後半の気が滅入りそうな展開もそうですが、個人的に注目したいのは初のトーキー撮影シーンや社交界での食事シーンです。そこにいる全員がそれぞれの立場や役割を守るために無理矢理にでも抑え込んだ怒りや不満が、人間の許容量を超過して部屋全体に充満してしまう——そんな「緊迫した空気の悪さ」は過去最高だったのではないでしょうか。
ミロの栄養バランスくらい整ってます。ある1点——あのラストシーンのケレン味——を除いて、バランスの良い優等生作品といえるでしょう。
マーゴットロビーは誰をどう演技したのか

(C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.
この映画で素晴らしいのは、まずはなんといってもマーゴット・ロビーの怪演です。自由でアナーキーなネリー・ラロイという人物を見せてくれました。映画女優として売れればそれでいいし、そのためには何をしても構わないし、女優業以外の時間で何をしようが関係ない。ネリー・ラロイはある意味で「無敵のひと」なわけですが、 “無敵の気持ちよさ” と “無敵の痛々しさ” をうまく使い分けていたと思います。

(C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.
「天才的な役者の役」(しかも演技シーンあり!)という難しい役を見事な説得力で演じていました。もし万が一にでも僕のところに「文章の書き方について解説する記事を書いて欲しい」という依頼が来たとして、僕は受ける自信がありません。マーゴット・ロビーはすごい。すごいし偉い。
it girl の代名詞:名優・クララ・ボウを下敷きに
「この手の役」をもう少し具体的に書くとすれば、 “it girl” が相応しいでしょう。カリスマ的な魅力を持ち、かつ破滅的な切れ味をもったセレブリティのこと。
“it girl” の語源は映画『It』 (1927年, 邦題:あれ)への出演がきっかけで爆発的に人気を博したクララ・ボウから。厳密には少し違いますが “ボンドガール” と似たようなシステムという理解でOKです。

(C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.
実際にデイミアン・チャゼルとマーゴット・ロビーはクララ・ボウを下敷きにしてネリー・ラロイを作り上げたそうです。過去に演じてきたシャロン・テートも純粋無垢なスターという点では共通しますし、ハーレイ・クイン*の開放的で破滅的な面も it girl 的と言えるでしょう。
※The Suicide Squadのジェームズ・ガン監督版。端的に言うと「おもしろい方」です。
マーゴット・ロビーの十八番になりつつもありますが、それでいて金太郎飴にならず深い差異を表現しているのが凄いですね。職人です。
Caution !!
ここからはネタバレになります
バビロンのあのラストシーンは結局何だったのか?
やはり気になるのはラストシーンの抽象的な映像と引用を織り交ぜた刺激的な映像と音声です。明らかに異質でアクが強すぎる。別スタジオで千鳥の2人が見ていたら確実にボタンを押して一時停止するでしょう。
これまでの劇映画の範疇を超えたメタ構造を観客にぶつけてきていることも気になりますし、これまでの監督の毛色からは予想だにもしなかった展開。あれ、デイミアン・チャゼルってこんなんだっけ?と困惑した人も多いのではないでしょうか。
ある意味では「台無しになるリスク」を冒してまで、デイミアン・チャゼルがやりたかったことはなんだったのでしょうか?
直接的に語られたものとは?
一見すると抽象的な表現のようですが、映画あるいは映画史への異常なまでの監督の愛情が説明的に表現されています。それはそれで良い気もしますが、竜頭蛇尾だと批判する声も。たしかにアクの強さとは釣り合わないほど直接的です。
この映画は、録画や録音といった記録技術の発明・発展から突如として生まれた「アーカイブされる芸術」の可能性の美しさを語りました。本来は瞬間的に消えてしまう音楽あるいはダンスのような表現による刹那な芸術は、録音・録画のテクノロジーによって永久保存されます。
しかし、どうやら芸術は永久保存されたからといって、その価値がずっと維持されるわけではありません。名作とされていたサイレント映画も、いつのまにか古びた技法の少し退屈なものになっていきます。長期的な視点でみればやはり芸術はナマモノなのでした。さらなる技術革新により以前の芸術が一瞬にして陳腐化してしまう儚さがあるのです。
しかし、その儚さを、彼は悲観すべき事実として捉えていないようです。むしろそれも含めて美しいと前向きに認識しているように思えます。
(直接的すぎるという反論をデイミアン・チャゼルは想定していたがごとく「映画なんて高尚なものではない」というセリフが劇中に挿入されているので、「わかりやすすぎてつまらない」と観客が目くじらを立てられる隙は実はどこにもないのですが)
映画人が映画を語る照れ隠し
僕が思うに、きっとあの一見すると前衛的である怒涛のラストシーンは、デイミアン・チャゼルの単なる「照れ隠し」や「開き直り」に過ぎず、そこまでの意味は無かったのかもしれません。
映画を題材にした映画をする以上は必ず「だったらお前はどうなんだ」という観客からの指摘が付いてまわります。そうした指摘や反論を想定して、分かり易く取り急ぎの答えを配膳していたのかなと僕は推測しています。”I just want to be part of something bigger “ (なんとなく何か大きなものの一部になりたいんだ) “というセリフをリフレインさせてまで。

(C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.
たとえるなら、本来は四六時中お笑いが好きでたまらないお笑い芸人が、その愛ゆえにステージ上でお笑い論を語ることを嫌がる(またはどうしても語らざるを得ない状況下において、声に空気を含んだ半笑いで自分を客体化しながら言葉を発する)のと同じです。
「いや、これまで連綿しながら進化してきた映画そのものが偉大ってだけの話で、この『バビロン』という映画はそれに比べると些細なことなんですよ」という自嘲気味な苦笑いのように感じます。
映画への愛を、映画監督という立場から作品を通して自己開示した本作。その自己開示っぷりはフィルモグラフィーの中でも突出しています。だからこそ気恥ずかしさも大きく、覆い隠したり開き直ったりする必要があったのではないでしょうか。
ラストシーンのあの演出には、おそらく “そこまでの” 意味はない。だとすれば、『バビロン』のさらに奥底にある主題はなんだったのでしょうか。
主題は「黄金期」の儚さ:過去に存在する夢
手法の良し悪しは別にして、これは「映画の映画」なわけですが、デイミアン・チャゼルが当時のハリウッド界を題材にして真に描きたかったものはなんなのでしょうか。
それはきっと、アナーキーで狂気的な世界とその没落です。失われてしまったからこそ、希少価値が高騰してその愛おしさが記憶や憶測の中で何倍にも何倍にも増幅されていく。
まだ産業化が今より幾分未発達ゆえにヘイズコードなどの制限もなく刺激的な芸術が数多く誕生し、ならずものであっても実力さえあれば評価されていた当時の映画業界。今では少し考え難いですね。ハリウッドスターも公共の場では行儀の良い振る舞いや発言が求められる時代になりました。
そしてなによりトーキーの登場です。新しい技術により映画は革新的な進化を遂げますが、その陰で進化に対応できず淘汰されてしまった俳優や、字幕作成など失われた雇用も少なくありません。腰を抜かすほどのお祭り騒ぎが、嘘みたいに前時代の遺物になっていく。
消えてしまう喜びを、記録して閉じ込めること
このように、失われた一瞬の輝きを再現することこそがデイミアン・チャゼルの本意ではないでしょうか。花火は終わるから美しいし、桜は散るから風情がある。彼がそんな和風の言語化をしたかどうかは別にしておおむねはこのような想いが込められていたのではないかと思います。察するに鍵となるのは失われてしまった瞬間的な喜びと、それを記録媒体の中で再現することにあります。
なるほど、そう考えると合点がいくデイミアン・チャゼルの根幹には「夢の美しさ」があるのかもしれない。いつか冷めるかもしれない夢であっても夢の中でだけは得られる永遠の享楽、あるいは冷めるからこそ尊ばれる儚さです。
『バビロン』でようやく浮かび上がるデイミアン・チャゼルの作家性
監督の興味は、そうした刹那的な瞬間に向けられている。だとすれば過去のフィルモグラフィーにも一貫性が浮かび上がります。『バビロン』の意表をつくようなラストシーンに困惑して「あれ、デイミアン・チャゼルってこんな映画監督だっけ」という人(僕もそうですが)も、これなら納得してもらえるでしょう。
『ラ・ラ・ランド』と『セッション』の共通点
『ラ・ラ・ランド』は好きだけど、『セッション』は受け入れられない。またはその逆。という二極化した意見が僕の周りには多く、筆者自身もラ・ラ・ランド至上主義者でかつセッション排斥主義者だったわけですが、こうやって整理すると腑に落ちる。どうやら最初から彼の狙いはこれだったらしい。『ラ・ラ・ランド』も『セッション』——そして『バビロン』も——題材はどれも異なるが、繰り返し同じテーマと向き合っている。
『ラ・ラ・ランド』で描かれるのはこれ以上になく甘い甘い恋愛劇と、ラストスパートは「可能性としてあったかもしれない幸せ」です。いずれも実現はしませんが、だからこそその慈しみが観客の許容量を上回って涙腺を決壊させます。

(C)2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.
『セッション』も同様です。血まみれになってまともに腕が上がらなくてもステージでドラムを演奏しようとするアンドリュー・ニーマンの狂気は、まさに刹那的な瞬間への愛です。憎しみ合っていると表現しても過言ではない二人——最終的には音楽家としてのキャリアを潰し合おうと破滅的な行動に出る——が、最高の演奏の最中だけはノンバーバルなコミュニケーションで通じ合うラストシーンはそのピークといえるでしょう。おそらくはあれが最後の演奏になるのですから。それでも、いま・ここにある音楽が大切なのです。
今日現在を最高値で通過する
そもそも「音楽は記録される」という前提はレコードなどが発達した1920年代以降の人間の思い込みであり、本来は「音が鳴ったら消えてしまう」ような瞬間的な芸術でした。音とはつまり空気の振動運動ですから、必ず静止して消失します。
さらに言えば、再現性のない音楽の最たるものが即興性の高いジャズという様式です。言わずもがな、デイミアン。チャゼルの大好きな音楽ですね。
美しいのに消えてしまう、あるいは美しいからこそ消えてしまう刹那的な事象に対する執着。本来は消えてしまう美の瞬間を、近代以降の記録技術で真空パックできてしまうという「新世紀のバグ」に彼は魅了されてしまったのです。
これはジャズや音楽に限定されません。身体表現や物語も、アーカイブで生きながらえることができます。そして本作『バビロン』では、今は無き黄金期のハリウッドの美しさ / 今は無いからこそ美しい黄金期のハリウッドを映画にしました。
アーカイブという行為で最高の瞬間を永続させること。おそらくこれこそがデイミアン・チャゼルの真髄なのではないでしょうか。
文・川合裕之(店主)
/ 編集・意外にもサイドスローの蟹
参考
映画『BABYLON』日本版劇場公式パンフレット(東宝ステラ, 2023)
紀平英作 編『アメリカ史』(山川出版, 2018)
日比野啓『アメリカン・ミュージカルとその時代』(青土社, 2020)日比野啓
村山匡一郎 編『映画史を学ぶ クリティカル・ワーズ』(フィルムアート社, 2022)
Harper R. Oreck and Jaden S. Thompson “Damien Chazelle ’07 on His New Movie ‘Babylon’ and His Experience Studying Film at Harvard”
【解釈】 “バビロン” というタイトルが象徴するのは?
最後に、補足的に『バビロン』というタイトルの意味ついても留意しておきたいです。バビロンとは今で言えばバグダード付近で繁栄していたメソポタミア地方の古代都市のことですが、本作は1920年代のアメリカが舞台ですので、当然これを直接的に指し示すものではないでしょう。
となると、 “かつての栄光” と同義の……

