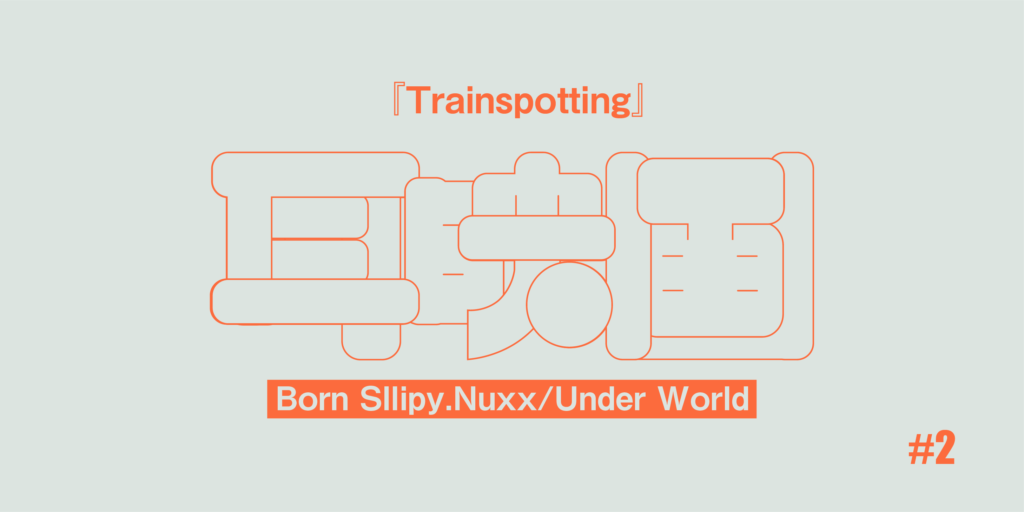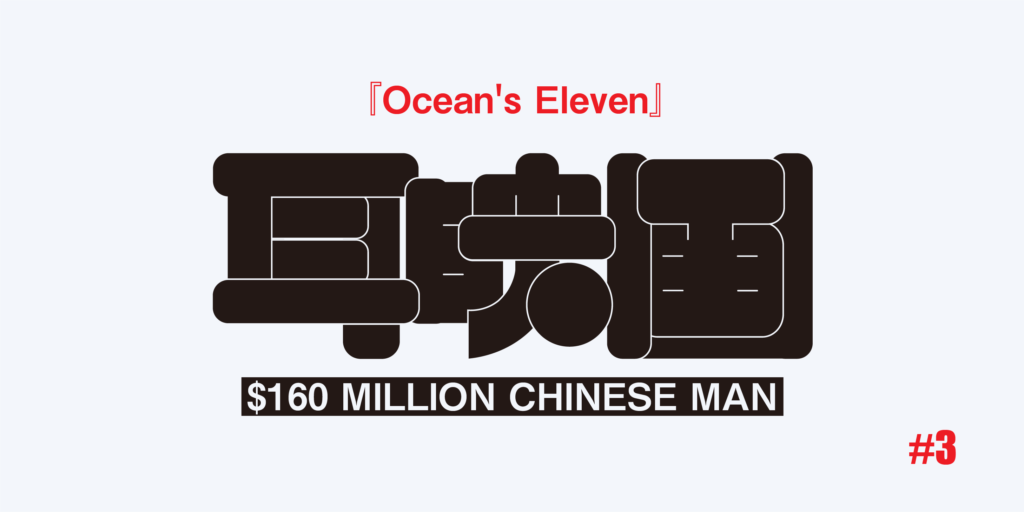音楽を聴いていて涙が出てしまったことがあるだろうか。
この場合の音楽というのは “歌” ではなくあくまで “音楽” を聴いて涙が出てしまったことを指していると考えて欲しい。
それは、歌詞に共感して泣けるものとは違い、サウンドや旋律を聴いている間になぜか心がざわついてきて涙がこぼれるという感覚だ。
ぼくは映画『Stand by me』(1986)を観るとほとんどの確率でエンドロール中に涙がこぼれてしまう。それはメインテーマであるBen E. Kingの『Stand by me』(1961)が流れるからだ。感情が昂っている時に聴くあの曲にはぼくの涙腺は太刀打ちできない。
“歌” ではなくあくまで “音楽” を聴いてとはいうもののあの楽曲にだって歌詞はあるし、メッセージだって泣けるようなものではないか!と思うかもしれないが、ぼくには英語を聞き取る能力がなく、英詩の曲を聴いている時にリアルタイムでメッセージを感じとる力がない。「Stand by me 和訳」などと検索しない限り理解できないほどぼくの英語力は貧弱である。
なのになぜあの楽曲を聴くとぼくの心がざわついてしまうのだろうか。「悲しい」わけでもなければ、「寂しい」わけでもない。なんだか「懐かしい」ような「切ない」あのサウンドがぼくの涙腺を緩めてしまう理由はきっと言葉に表すことはできないのだろう。
だけど、知りたい!なぜ『Stand by me/Ben E. King』があんなにも懐かしくて切ないのか!あの楽曲のミックスやアレンジの構成が一体どのように作られているのか!楽曲を解体して部分ごとにその仕組みの謎をといてみようと思う!
今一度、Ben E. Kingの名曲『Stand by me』を聴いてみましょう!
シンプルだからこそ唯一無二のイントロ
まず、この曲の冒頭に流れ始めるベースラインとパーカッション。全世界共通のあまりに有名なイントロ部分だ。シンプルに構成されるこのビートは安心感があって、ある意味機械的にも聴こえるパターンが繰り返される。
実はこのベースラインとパーカッションのビートは最初から最後までずっと同じフレーズを繰り返し続けている。楽器初心者でも奏でることができそうな本当にシンプルなこのフレーズは「これ以上削ぎ落とす部分のない、なにひとつとして無駄のない完璧なビートとベースライン」だ。だからこそ演奏するのは難しいと考えることもできる。
ちなみに映画『Stand By Me』(1986)は映画監督ロブ・ライナーが、スティーブン・キングの短編集『恐怖の四季』の中に収められた秋の物語『ザ・ボディ』(1982)を映画化するにあたり、このタイトルのままでは観客がホラー映画だと思って見に来てしまうという理由でタイトルにBen E. Kingの曲名を採用した。というのも、ホラー作家で有名なスティーブン・キング原作で『ザ・ボディ』というタイトルで、あらすじは少年たちが「ボディ」つまり「死体」を探しにいく旅を描いている。にもかかわらず、ご存知の通り『Stand by me』という作品はホラーとはかけ離れたシナリオである。監督のロブ・ライナーはこの映画から原作のホラー性を排除したのだ。そしてさらに、この楽曲を映画のテーマ曲として採用することになった。

IMdbより
つまり、原作小説と楽曲は全く別の作品であり、本来そこに親和性は存在しない。双方にここまで親和性を持たせることができるのは映画『Stand By Me』(1986)という作品が存在するからこそなのだ!映画『Stand By Me』を観るとわかるように、この原作小説と楽曲は驚くほどマッチしている。映画『Stand By Me』は原作と楽曲の奇跡のような出会いを導き出した作品なのだ!
そんな奇跡のような出会いが生んだ親和性から、ぼくの脳内ではこの楽曲に強いイメージがこべりついている。
それは、イントロから始まり、最後まで同じフレーズが繰り返されるビートとベースを、まるで主人公の少年たちが延々と歩いた線路を彷彿させるということ。
「線路」という「何度も繰り返されるパターン」をイメージしたかのようなビートとベースライン。原作や映像からインスピレーションを受けて作られた楽曲なのではないかと感じてしまうほど、このフレーズには映像との親和性が感じられる。

IMdbより
さらに、楽曲のBPM(曲のテンポを表す数値)は120前後で、どこまでも続く線路の上を少年たちの短い足でトコトコと歩いていくようなリズムを感じることができる。
映像を “思い出させる” サウンドの秘密
イントロ:線路、青空、子どもたち
足下には同じパターンを繰り返す線路が続いている。少年たちの歩幅でゆっくりと前に進めば、周りの景色はドンドン変わっていく。曲が進行していくにつれて楽曲にバイオリンなどのストリングスやコーラスの旋律がドンドン足されていくことで少年たちの見ている景色が変わっていくことが表されているように感じる。

IMdbより
もう一度確認しておくが、この楽曲は映画のために書き起こしたものではない。そして、原作である小説との関係性も存在しない。なのにこんなにも音楽と映画がマッチしているのだから本当に奇跡のような出会いを体験しているように思えるのだ。
さりげなく入るウワモノが歌とベースを馴染ませる
そして「ウワモノ」と呼ばれるギターやストリングス、コーラスワークたちの構成がまた素晴らしい!
「When the night」と歌が入ってくる0:16あたりでスピーカー(またはイヤホンヘッドホン)の左側に耳をすませて欲しい。うっすらとアコースティックギターとストリングスがinする。ここでこの二つの楽器がinすることで歌とベースをうまく馴染ませる効果がある。このタイミングでさりげなく入ってくるウワモノたちがなければきっと楽曲全体がスカスカした印象になることが予想できる。
そして、0:48あたりのみんな大好き「ダーリンダーリン!」の直後、右側のスピーカーに耳をすませて欲しい!ここでinしてくるのが左側のストリングスの1オクターブ上のユニゾンストリングス。なんだか一気に気持ちが高揚しませんか!
サビの高揚感をストリングスが演出
「ダーリン!ダーリン!」という「今からサビを歌いますよ〜」という準備のメロディを効かせた後に、さっきまで静かで寂しかった右側に入ってくる1オクターブ上のストリングス!このタイミングでスピーカーの両サイドが初めて綺麗なバランスで鳴り始めるのである!「ここがサビですよ〜」と言わんばかりのこの構成。何度聴いても本当に素晴らしい!しかし、この段階でこの楽曲のポテンシャルはまだ半分も発揮していない!まだまだ高揚の伸びしろを残しているのだから驚きだ!
2番でのコーラスワークは思い出の幻影?
歌は2番へ。1:04のタイミングで更にコーラスが in してくる!この辺りでぼくが感じるのは、この映画が大人になった主人公ゴーディの回想録であること。これは本当にぼくの主観的な感じ方なので捉え方は自由なのだけど、このコーラスはなんだか脳内に描くビジョンにモヤがかかっているような、漫画のキャラクターのモクモクとした形状の吹き出しのような、そんなイメージがある。なんだか切ない、だけど悲しいわけではない旋律のコーラスが「子どもの頃の思い出」にマッチするサウンドだ。

IMdbより
もう一度サビへ!ストリングスがのポテンシャルを存分に発揮させる!
そして!二度目の「ダーリン!ダーリン!」の直後、もう一度右側のストリングスに注目です!一番のサビのさらに1オクターブ上で奏でられるフレーズ。二段階のオクターブ上昇によりついにバイオリンストリングスの一番得意とする音域にまでたどり着いたこのフレーズはまさに大サビといった印象だ。線路の上を歩く少年たちの姿を思い浮かべている大人になった自分自身がもう一度、心からあの頃の友達に会いたいと叫んでいるようなサウンドが聴き手の心をざわつかせる。
それでもまだ線路は続いていく!なんて綺麗な間奏なのだろうか!この間奏のタイミング(1:52)でストリングスが自然にこの音域で奏でているという楽曲構成の無駄の無さに感動する!そして最後のサビのパートへ!
こうして曲が終わっていくのだが、最後の最後まで無駄のないアレンジが施されているから要注意!
フェードアウトは人生の長さを演出する
2:40のタイミングでBen E. Kingが「Whenever you’re in trouble won’t you〜」と叫ぶ。その裏で既に二段階上昇した右側のストリングスが更に1オクターブ上昇する!もはやここまで高い音は高揚を超えて涙まじりの安定しない声のようにも聴こえる!映画『Stand By Me』(1986)を観終えた後の心のざわつきにマッチしていて本当に涙がこぼれそうになるサウンドだ。そしてフェードアウト。曲が終わる。

IMdbより
楽曲の終わり方をフェードアウトで終えることで線路が途切れることなく続いていくような感覚が残る!そしてさらに、このフェードアウトの演出は映画の主人公たちのその先の未来までもを奏でているようにも聞こえてくる!楽曲がはっきりと「ここで終わります」というアレンジになっているわけではなくあくまでフェードアウト。それは映画『Stand by me』のエンディングによく似ている。
改めて、この『Stand by me』(1961)という楽曲のサウンドメイクの素晴らしさ、そして映画との親和性の高さには驚かされる。2分57秒という短い時間の中で、シンプルでキャッチーなフレーズでありながら、緻密な構成を聴かせてくれる。
世界中で愛されている名曲を、こんな風に文字に起こして解説するなんてはっきり言って野暮であることはわかっている。なぜなら音楽というのは本来言葉では表すことのできない人間の感覚を表現するツールであるのだから。
だけど!だからこそこうして言葉にすることが「音楽を聴く」ということの更なる楽しみ方の一つであるということを提案したい!そして、最後にもう一度、こんな野暮で無駄な考えを全て取っ払って音楽に没頭することがまた新たな発見へと繋がるのではないだろうか!
そして、こうしてBen E. Kingの「Stand by me」を掘り下げてみたことで、ぼくはさらにあの映画のことを愛せるようになったのだ。きっと、次にもう一度『Stand by me』(1986)を観たとしても前回と同じようにぼくはエンドロールで涙をこぼすだろう。

文・金城昌秀
編集・川合裕之
解説:Ben E King『Stand by me』(1961)

リリース:
1961年11月
作詞作曲:
ベン・E・キング,ジェリー・リーバー,マイク・ストーラー
チャート最高順位:
4位(アメリカ・Billboard Hot 100)
ここまでサウンド面に重点をおいて記事を書いてきたが、最後に、やっぱり『Stand By Me』という楽曲の持つ力はそのメッセージとBen E. Kingの歌声がなければ成立しない。
サウンド面はあくまでそのメッセージをよりよく伝えるための手段であり、表現であることはジョン・レノンによるカバーバージョンなどを聴くことでその可能性の広さを感じることができる。
ジョン・レノンの他にもあらゆる時代において世界中の数多くのミュージシャンたちがこの楽曲をカバーする理由はそのメッセージの多様性にある。
「Stand by me」を直訳すると「私のそばに立って」となるが、和訳される際によく使われるのは「そばにいて欲しい」といったものが多い。言語の違いによるニュアンスの微妙な違いはあるにせよ、「stand」「by」「me」という子どもでも話せるような言葉だけで構成されたこの言葉たちには無限の解釈が存在する。
ジョン・レノンが歌えばオノヨーコに向けた言葉、つまり恋人や家族に向けた歌に聴こえることもあれば、映画『Stand By Me』のエンドロールで流れる場合は友達に向けた歌であったり、子どもの頃の自分自身に歌っているようにも聴こえる。もっと可能性を広げるならペットや愛用品に向けて歌うこともできるし、はたまた死んでしまった先祖様に向けて歌うことだってできる。
イントロ部分のベースラインがシンプルで無駄を極限まで省くことで究極のフレーズとなっているのと同じように、ここまで無駄を省いた言葉というものはもはや無限の解釈を与える言葉に変化するのだ。
だけど、やっぱりこの歌を朗読されてもぼくは泣けない。言葉以上に押し寄せるあのサウンドたちにぼくの心はざわつくのである。
言葉にできない感情。それが音楽の持つ最大の魅力なのだとまた、気づかされる。
解説 映画『Stand by me』(1986)
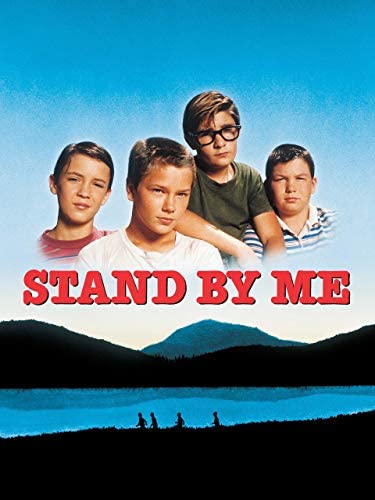
IMdbより
監督:
ロブ・ライナー
出演:
ウィル・ウィートン,リヴァー・フェニックス,コリー・フェルドマン,ジェリー・オコンネル,キーファー・サザーランド
元々、本作は『ナインハーフ』(1986)や『フラッシュダンス』(1983)などで知られるエイドリアン・ラインが監督を務める予定だった。
しかし、エイドリアン・ラインがバケーション中で撮影スケジュールに遅れが出る恐れがあったため、のちに『恋人たちの予感』(1989)や『ミザリー』(1990)を手掛けることとなるロブ・ライナーがメガホンをとることになった。
作中で悪ガキ大将を演じたリヴァー・フェニックスは私生活でも悪ガキだったと言われている。
監督ロブ・ライナーはクリス役のリヴァー・フェニックスが意味ありげな笑みを浮かべて撮影現場に現れた日のことを覚えていると語っており、リヴァー・フェニックスは本作撮影中に童貞を捨てたともいわれている。
また、テディ役のコリー・フェルドマンは、リヴァー・フェニックスが楽屋でマリファナを吸ってハイになっているところを目撃したとも証言しており、証言している本人、フェルドマンも当時マリファナを嗜んでいた。
連載『耳映画』をおかわりしよう!