毎日闘ってる。自分だけがとかではないと思うけど毎日かなり闘っている。
だいたいにして眠りから目覚めると同時にどこか痛いし、たびたび根拠もわからないまま死にたくなったりする。
自分の生活の中に困難が数多あってそれらと日々闘っていることへの実感がある。
けれど「闘っている」「困難」そういう言葉を虫眼鏡で見てみればその言葉はどこか解像度が粗く、いろいろな要素を取りこぼしているかもしれないとも思う。
もちろん苦しんでいる自分だけが自分なわけではない。一時の苦しみにとらわれて未来まで見えなくなることもあれば、穏やかな時間に差し込んだ陽の光の明るさを信じられるような一瞬もある。握った手に励まされて心が溶けるように泣いた日もあった。
「困難と闘う」は自分の周りだけじゃない、どこにでもあふれている。
けどそれって実のところ、どういうこと?
自分自身の苦しさすらも、思えば拾い上げて真正面から見つめたことがあっただろうか。

「黒い雲と白い雲との境目にグレーではない光が見える」という本は、いわゆる 「がんサバイバー」 の中でもAYA世代と呼ばれる若年世代の女性26人が詠んだ短歌が収められている。「がんサバイバー」、聞き慣れない言葉かもしれない。この歌集の題名にはなぜ「がんサバイバー」という言葉が用いられているか。
たとえば「がんサバイバー」ではなく「がん患者」「闘病」といった言葉を耳にした時、こぼれ落ちてゆくひとりひとりの小さな物語を想像してみる。
病気と共にある日常を丁寧な手つきで拾い集め卓上に並べてゆくような美しい歌たちを読んでいると、その答えはひとつでなくいくつも、きっと詠むひとと読むひとの分だけ無限に立ち上がってくるような気がする。
文・む
ねこと犬と人と暮らしている。芸術と生きもの全般が好き。

物心ついたころから自分に違和感があった
自分のことを話すと、わかりやすい「困難」の看板としては発達障害という障害?との付き合いがある。(付き合いがあるという表現はおかしいかもしれないがそれが最適なように思う)
発達障害とひと口に括ってもそれによる個人の困りごとは、基本的な傾向はあれど当事者の生活スタイルや置かれた環境、年齢、個々人の性質、それぞれの分だけあると言っていい。
また発達障害そのものによって起こる困りごとのほかにも、発達障害への偏見、差別や、当事者の発達特性への周囲の関心や理解のなさから起こる対人面での悩みやトラブルなども当事者の生活を困難なものにしうるだろう。
物心ついたころから集団の中の自分に違和感があった。
なんだかみんなと比べておかしいところ、おかしい時がある。明確な言語化が出来なくてもそういった感覚自体は自分の記憶を遡れるまで遡ったところから始まって、常に生活の中、他者との関わりと共にあった。
発達障害を説明する言葉として能力の凹凸が激しいというようなことを聞いたことはないだろうか。自分でもそこのところは日頃から痛感する。なんでできないの、なんでやらないの。幾度となく周りから言われるまでもなく、自分で自分に問いかけ続けてきた言葉だ。
やればできるよ、と励まされることもある。おそらくその言葉の根拠は自分が見せた能力の凹凸の凸の部分なのではないかと思う。
確かに、できることはできるよ。人よりも秀でていると思えること、たとえば手先が器用だとか、学校の勉強、そういった部分を見て「やればできる」が出てきたのだと思う。ならばできないことは単に「やらないからできない」のか。そう見えていたのかもしれないがそうじゃない。できることができる分、自分でも異様なまでに「できない」ことがあるという事実にずっと違和感を抱えていた。
そういったどうしてもできないことの一つとして、自分は決まった時間に決まった場所に通い続けることができない。決められた日時に自分のバイオリズムを合わせるのが苦手だ。自分の調子よりも予定を優先して行動しなければいけないときに苦痛を感じてしまう。
「待ち合わせ 間に合う 方法 確実」みたいなことを検索欄に打ち込んで出てきた方法を片っ端から試してなんとか予定に間に合うように家を出られた朝の電車で、とんでもない忘れ物に気づく。
それだけ、たまのうっかりなら笑えるかもしれないけれど、間に合うことに注力しすぎた結果なのだろうか、自分で自分が信じられなくなるくらいのもの忘れを頻発したりする。間に合うことに全力を注いで間に合い続けることができた数日目に疲弊によって玄関先で座り込んだまま立ち上がれなくなり、紐まで結んだ革靴の先を見つめて過ごす、というパターンもある。
予定が苦痛なのではない、何かしらの理由があるとも言えない。心と身体と意思とが足並みを揃えてくれることの方がむしろ奇跡のようなのだ。
またいっときの衝動を抑えることができずに先のことを考えない行動をして自分だけでなく周囲にも迷惑をかけたり、意図しない形で他者を傷つけてしまうこともあった。そうやって説明も取り返しもつかないような大小の失敗を重ねてゆくうちに、できない自分、凹凸の凹のほうの自分を当たり前だと思うようになってしまった。
あきらめと恥ずかしさ。
明らかに人に迷惑をかけるような「できなさ」がある上で得意なことだけ一丁前にこなしてみせる自分が嘘つきのようで、年齢を重ねるごとに自分で自分を信用できなくなってゆくことが精神的にこたえた。
優しさからかけられたであろう慰めの言葉も自分の不甲斐なさを攻撃しているような気がする。自信のなさから対人的に疑心暗鬼になってそのように感じてしまうこともあった。できないひとと思われること、それを他者にリカバーさせ続けること、そういうことを繰り返しながら共同体に馴染めない自分が社会に参加する意味があるのか分からない。失敗が怖くて、徐々に引きこもりがちになっていった。
精神科に足を運び発達障害の診断を受けて以降は、自分自身の苦手なことや困りごとに対して通院や投薬、その他多角的な対処ができるようになり生活しやすくはなったと感じる。
それでも起きぬけに寝ぼけ眼で錠剤のシートから朝の薬をぷつりぷつり押し出しながら、なぜ自分が?と思うことはある。
発達障害由来の二次障害と診断された他の精神の持病もあり毎日の投薬は急に止められない。長期的な服薬のリスクと引き換えに担保される生活。
そういう自分にいつの間にかなっていた、選ぶ余地もなく。それがたまらなく恐ろしくむなしく感じられる時がある。
もういいか いや生きようか 手のひらで揺れるくすりは命のサイコロ
(連作「祈りの儀式」 p69、p96)
病気という困難と自分の生活との間に境目はない。
「私たちは決してかわいそうな人生なんかではない」
このあとがきから引いた一文が、それぞれの人生を抱えた読者の目にどう映るだろう。
責任を取らなくていい距離からかけられる「かわいそう」の声。病気でかわいそう、あれができなくて、これを持っていなくてかわいそう。
その声によってかわいそがられる「わたしたち」の努力は、幸せは、過去の涙が今につながってゆくことの希望は。
全部ないものになどならない。
かわいそうに全て回収されてたまるか。
なんらかの病気に罹患したりまた障害を抱えながら生活をする上で、いわゆる「感動ポルノ」に還元されるような単純さで割り切れる物事なんてほとんどない。とても人には見せられないような姿で過ごさざるを得なかったり(何日お風呂に入れなかったろう)、世の中で一般的、多数派とされるような当たり前の健やかさに対する苦しいほどの羨望、泣いて悶えても受け止めきれない心身の痛みから解放されたくて死にこころが傾いてゆく夜、そういったものごとをいくつ越えて自分は今ここにあるだろう。

頑張って貰えるご褒美の日常が人並みのものであればあるいは、けれど薬を飲んだからといって全てが解決するわけではない。
身体や精神の治癒能力は目に見えないし自力でコントロールすることも難しい。それに対する医学的な措置に身を委ねたり、振り回されているように感じ戸惑ったりしつつ、どこに自分があるのか、精神と肉体のいったいどこからどこまでが自分と呼べるのか、不思議に思うことがたびたびある。一錠の薬を飲み忘れるだけで自分が自分でなくなってしまうような脆い日常。
そういう時、自分自身とはさまざまなものごとが流れてゆく一瞬を切り取る額縁のようなもので、何かを選択する主体としての自分なんていうものはどこにも存在しないのではとすら思う。
精神、肉体、自意識、それらが不可分であること。布に染み込んで落ちない色水のように、病気と自分自身ともまた切り離せるものではない。病気や障害という困難と自分の生活との間に境目はない。
病気に翻弄され、時には薬で押さえつけ、時にはうまい付き合い方を模索しながら、それは移動を嫌がり続けるわんちゃんとお散歩するみたいな…いやもっと例えようのない連綿としたもので、そこに明確な勝ち負けなどは存在しない。
かほさほを守ってくれた子宮さん、ありがとう、かほさほはげんきです
(同書 p46)
ぜんぶ自動でグラデーションをなくせられたなら
困難にはわかりやすいものから傍目から見て全然そうじゃない、むしろ特定の目線からは困難じゃなくて恵まれ案件では?と受け取られてしまうようなものまで様々であり、その当事者でない人はいない。さらに困難の様相はグラデーションを呈しており、当事者にしかわからないことも当事者すらわからないことだって多く、まして他者によって白黒分けられないような場合がほとんどだ。
それを分かっていても無意識に自分の主観であれはかわいそう案件、あれはそうじゃないって判断して細かな事情を慮ることを切り捨ててしまったり、さらに返す刃で自分や他者を傷つけてしまうこともある。
白黒つかない曖昧さを曖昧さのまま受け止めることは、答えのない問いを問い続けることだ。白黒じゃない曖昧さ、つまりグレーのグラデーションにとどまる事は疲れる。ぜんぶ自動で白黒ついて考えることを手放せたらどんなに楽だろうと思うことも多い。
黒い雲と白い雲との境目にグレーではない光が見える
(同書 p32)
グレーではない光、見えますか?
自分ではそんなこと考えたことなかった、けれどこの歌集を読みおえてたしかに自分の歩いてきた道の前にも後ろにも、グレーではない光があって、それに導かれてようやく歩いてこられたようなところは確かにあると感じた。感じなおした。
人生を感じなおすということはとりもなおさず人生を生きなおすということではないか。
時間は一方向にしか流れないし過去を消すことは出来ないけれど、頭の中で出来事をとらえなおすことができればその出来事の意味が変わる。もしかしたら、自分を傷つけ続けてきた記憶が自分をケアする記憶に変わりうることだってあるかもしれない。
自分がグレーではない光を息継ぎのようにしてあいまいなあたたかさ、やわらかさ、明るさのある記憶を希望につなぐことでここまで生きて来られたとする。
ひとがどのようにであれただ生きるということにも付きまとう暗さのことを思うと、たぶん生きているひとなら誰でもグレーではない光に先の見えない道を導かれてようやく歩けたような瞬間があるのかもしれないと想像してみる。
単純なことなんてひとつもないかもしれない、けどそれでも大丈夫だよね。って言われたい。大丈夫と大丈夫の間の暗いところも、未来にあるかもしれないあらゆる明るさを想って歩いてゆきたい。
幾度でも愛でてあげよう手術痕わたしを生かす薄桃のすじ
(同書 p52)
死を選びたいんじゃなくて
たとえば時には、死にたい、ていうか生まれたくすらなかったという気持ちが発生したりもする。
死を選びたいんじゃなくて、楽になりたい。けれどそれが自分であっても人間ひとりの命を終わらすことの大きさ。そんなに簡単には楽になれないことも分かっている。分かっていても逃れたくてただ逃げ場がないときのしんどい気持ちが勝手に、自分のいない世界を夢想する。
その夢想が、生きていくことへ必要な分だけの勇気をふたたび持ちなおすためにどうしても必要なのだ。生まれたくなかったと思いながら生きることでしか生活を、命を未来に繋げられない時がある。
そのように二律背反的な想いを抱えながらそれでも生きさせてくれ、そういう事実があることをせめて突き飛ばさないでくれという心の渇き。死にたいだなんて言うなみたいな一刀両断の言葉(時に100%以上の善意や好意による)とかに突き飛ばし斃され、助けてのひとことを言う気力も無くなり、さらに乾かされてゆく。
そういうところに染みる。あらためて発見されたグレーではない光が、大きな痛みを伴いながらも確かに乾いたところへ染み込んでくれる。
痛みに寄り添う短歌がそれぞれ決して完全には他者と分かち合えない困難を抱えながら血の通った今を生きているひとによってたしかに詠まれ、自分のもとまで届き、そうして乾きに染み込んでゆくことのあたたかみ。
誰かがその誰か自身の生と病に向き合うことから産まれた光で自分が照らされること。
それらは偶然でない。
短歌を詠んだ人がいるから、表現した人がいてそれを届けようとする人がいてそれを選んだ自分がいるから、幾つもの意思の介在によってこの本に納められている短歌が、グレーではない光が自分を照らすのだ。そこに必ず誰かの意思があること。
涙がいっぱい出た理由を考えるとしたらそういうことだと思った。本を閉じた時少しだけ、いつもよりまぶたの裏が煌めいて見えた。もがきながら生きるに値する世界、その先に待っているまだ知らない光を信じることが、生きてゆく理由の中の大切な一部分になるだろう。
明日も朝が来る。死にたい朝かもしれないが、生きたい朝になるかもしれない。希望の可能性を抱いてねむるとき傍らにこの本があることが心づよくてあたたかく、こういう出会いがあるならば困難の中でも人間らしい生活を指向する意味は消えない。目を閉じると暗闇の中遠くのほうにかすかな光がさしこむ景色が見える、そんな気がした。
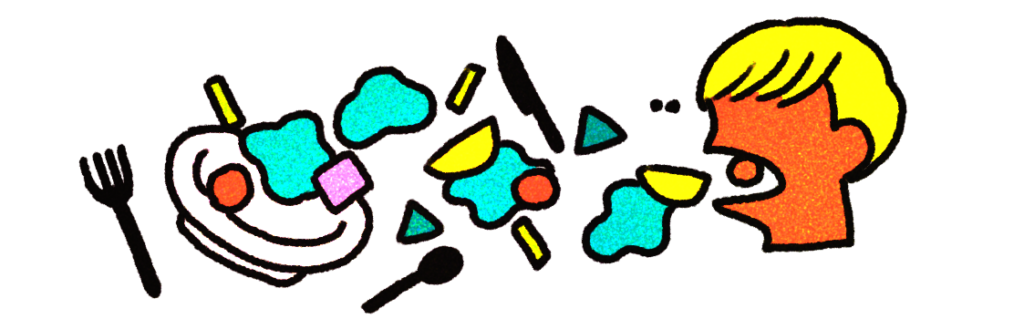
【関連記事】
感動ポルノの幸福な呪い | 映画『フォレスト・ガンプ』, ドラマ『グッド・ドクター』
映画『あの頃。』とJuice=Juice「チクタク 私の旬」
女性の「アツい」叫びを眺める僕の〈語れなさ〉|映画『私をくいとめて』と『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』に宛てて


