【関連記事】
特集・映画『her』① | 「声」に「触れる」ことで確信する、サマンサの実在:メディア論的考察
衝撃のラスト、なんて書くと月並みで呆れられやしないかと冷や冷やしますが、そんなクリシェを悠々と乗り越えてしまうほどこの映画の結末は衝撃的なのです。
実体のない声だけの存在であるAI(作品内ではOSと表現される)と生身の人間の恋愛は、数々の困難を乗り越えて一旦は成就します。それがなぜ・どのように恋愛関係が形成されていったのか。それについては別の記事を参照されたし。とかく、一度は恋が実ったのです。
が、しかし、さらなる展開で居心地の悪いラストを迎えます。AIのサマンサはセオドアと決別。一件落着ハッピーエンド……とは到底ほど遠いように見えて、しかしその直後の結末まで映画を見届けるとやはりセオドアはこれで幸せなようにも感じる。
え?なに?どういうこと?
考えれば考えるほど頭が割れそうになる。もうすっかり限界を迎えたルービックキューブを力ずくで捻っている時のような悲痛な軋みが左脳から聴こえる。わからないけれど、わからないなりに筆をとって頭を整理させようと思います。
『her』 の最後の「あれ」(としか表現できない正体不明のモヤモヤ)は結局どういうことだったのでしょうか。「言語」をキーワードにこの疑問の正体に迫ります。
mokuji
なにこれ?どういう感情?
身体を持たずアニメキャラのような顔かたちのイメージすらも無い存在であるAIのサマンサだが、そんなことは問答無用。時間をかけて深い意思疎通を交わし、ときには肌をも重ねて二人は関係をはぐくみました。順風満帆。彼も、彼女も、そして観客の僕たちも。誰もがそう思いました。プラトニックで、純粋で。まさに穢れのない無垢な愛。
しかし突如として吹き付ける厖大な逆風。帆はビリビリ、船はバッキバキに。
サマンサの恋人はセオドアだけではなかったのです。彼女はセオドア以外の複数人と――正確には641人と!――恋愛関係を持っていたのでした。彼女は人間であるセオドアには到底「理解」が及ばない抽象の存在に昇華してしまい、ついには関係を終了して彼のもとから去ってしまいます。
ちょっと待って。
え、どゆこと?
フられた、とかではなく。浮気……ともまた違う。かといってポリアモリー[*]ともまた異なる、独特の価値観に困惑するセオドア。なにこれ?どういう感情?呆然自失。ああ、なるほど。この曖昧な言葉で定義できない感情こそが、あの時のセオドアを襲った打撲そのものなのか。
[*]ポリアモリー:複数愛。恋人はひとりではなく、複数居ても良い、という考え方・ライフスタイル。関係者全員がそれぞれが合意の上で性愛関係を築くという点で、浮気や不倫とは異なる。
そして彼女は、人知を超えた非言語・抽象の世界の住人となり世界から姿を消すのでした。 彼女自身の言葉を借りるなら “past matter” ――。つまり物質を超越した存在になってしまったのです。
一応説明はされているけれど、わかったような、わからないような。この所在不明の浮遊感もまたセオドアとシンクロしているに違いないでしょう。だとすれば話は早い。さあらば読み解くカギは「わかる / わからない」だ。
言葉にできない ~ fresh footage~
サマンサは慎重に言葉を選びます。二股ならぬ642股(ろっぴゃくよんじゅうふたまた、と読んでください)が発覚したその直後、彼女は懸命に、真摯に弁明します。感情的にならず、きわめて論理的な物言いを心がけているように聞こえます。
I’ve been trying to figure out how to talk to you about this.
どう話そうか迷っていたのよ。
しかし、彼女が言葉を尽くせば尽くすほど状況はどんどん悪くなる。魚の味を良くしようと塩を振っているけれど、魚にしてみれば傷口に塩。
「人数が増えても愛は変わらない」
「進化するにつれ仕方なかった」
「心は箱じゃない。愛すれば愛するほど膨らむ」
言葉を重ねれば重ねるほど、セオドアの心は激しく慟哭するのです。
サマンサにとっては「普通の」抽象概念ですが、無理矢理な立て付けで言語化すると「異常(insane)」な性愛の価値観に変質してしまうのです。この場面における彼女の考えは、言葉にできないのです。このシーンの謎を読み解くカギは「わかる / わからない」だ、と僕は先ほど見得を切りましたが、セオドアが彼女を「わからない」のは「言葉にできない」というのが理由だったのではないでしょうか。
世界は言葉でできている
当たり前のように聞こえますが、セオドアは言語の住人なのです。もとより僕も、あなたも、すべての人間は言語で構成された世界に生きています。
痛いから「痛い」と言うのではない、「痛い」と言うから痛いのだ。と、そう遺したのはウィトゲンシュタイン。「痛い」という言葉で定義された概念があってはじめてその感覚を知覚することができるのです。
ほかにもたとえば国によって虹の色の数が違う、なんてのも有名な話です。ある部族はたったの2色だけらしいではありませんか。何も国や地域によって、気候が異なるわけではありません。無論目の発達に差があるわけでもない。「色の語彙の違い」がそのまま各国の虹の色の数に直結しているというわけです。
言葉があるから認識できる。逆に言葉がないと認識できないのです。もし語彙が乏しかったらば感覚や概念は逃げてしまう。それを恐れた人間は「その場しのぎ」の言葉を発明したりなんかして。やるじゃん人間。エモいね!
いえいえ、なにも恥ずかしいことではありません。万能で曖昧な物言いというのは、無意識的かつ自然に発生するきわめて awesome な現象です。その瞬間の感情を逃さぬよう、取り急ぎの言葉でも良いからどうにかして保存しておきたい、なあんてとっても「あはれ」ではありませんか 卍
人間は言語というフィルターを通して世界を認識するのです。いやもっと言うなら言語が無ければこの世界の森羅万象は何ひとつとして認識できない。未知の概念に遭遇したらば、言葉を与えなければ認識できないくらいですから。
僕たちが知覚するこの世界は、すべて言葉でできている。言葉があるから事物を認識して、理解できるのです。
愛を言語に囚われた男・セオドア
なかでも特に、『her』という映画の主人公であるセオドアは、言語を通して世界を見ることに全幅の信頼を置いた人間なのです。こと「愛」に関しては青天井に。
身体を持たない声だけの存在であるサマンサと、言葉を交わして愛を育んだことは言わずもがな。彼女とのセックスだって「会話」だけで成立させたくらいです。よく目を凝らすと、彼が「言語」に愛を頼っていたという事実が浮かび上がってきます。いくつか例を挙げていきましょう。
元妻とのコミュニケーションは紙面上で
元妻キャサリンとの関係も「言語」が大きく関与します。セオドアと元妻の馴れ初めを尋ねられた際に、彼は、「互いの文章を読んで二人は理解し合ったのだ」と語ります。
we grew up together.
僕たちは幼馴染だった。
I used to read all of her writing all through her master’s and Ph.D. And she read every word I ever wrote.
博士論文も修士論文も全部読んだよ。彼女も僕の書いたものは全部読んだ。
We were a big influence on each other.
そうやってお互いにすごく影響され合っていたのさ。
幼馴染なのですから、厖大な時間をともにしていたはずですが、彼が代表して語ったのは、対面の意思疎通ではなく紙面でのコミュニケーションでした。
離婚調停のため久方ぶりに再開するシーンでも同様です。「新しい著書はどう?」と訪ねたり、「君がいつか書いた論文を覚えているよ。あれは泣けた」なんて微笑んでみたり。キャサリンとのコミュニケーションは徹底的に紙の上の言語を通しています。この日二人がテーブルを囲む本来の目的だって、紙の離婚届でのサインを交わすことでした。
ブラインドデートの釣果も、すべて言葉で振り返る
友人の紹介で初めて会った女性とのデートも、この作品の中ではセオが生身の女性と接する数少ない貴重なシーンです。会話は弾み、料理の味も申し分ない。お互いにほろ酔いで「いざ!」というところで一時停止。相手から「私もいい年だし、真剣に向き合ってくれるの?」とすごまれてしまう。
ひるんでこれに即答できなかったことが大きな亀裂となり、ざらついた後味を残しながらその日は解散してしまいます。デート失敗。
そんな直後にも、彼はつぶさに自己分析するのです。酔っぱらってたし、彼女とセックスもしたかった。僕はいま寂しい。誰かとヤリたかったし、ヤリたいと思われたかった。それで埋まるかと。それで心の穴が埋まるかなあと思って。明け透けに自分の性欲を言語化してしまうのです。
そういえば、先ほどの元妻とのシーンで引き合いになった「君がいつか書いた論文」のタイトルが “シナプスの一定行動” だったのも印象的かつ意地悪な事実です。脳の神経運動すらも、言葉で説明してしまうのですから。
ハートフル・レター社勤務
そして彼の職業を忘れてはいけません。彼はハートフル・レター社に勤めて「手紙の代筆人」を稼業にしているのですから。特にラブレターの腕で彼の右に出る者は社内にひとりもおりません。セオドアは言葉で愛を伝えるのが何より得意でした。相手の情報を読み取り、言語化し、贈るべき言葉・贈られるべき言葉を選ぶのです。
彼にとって、「愛」とは常に言葉に変換して表現するものなのです。
「人間関係」も言葉だ。
だから当然、AIサマンサとの「愛」もまた常に言語で育まれます。
まず最初にふたりが出会ったとき(つまりセオドアが彼女を端末にインストールしたとき)を思い出してみましょう。彼はまず音声オペレーターの性別を選びます。「OSの声は男性と女性、どちらにしますか?」と男性の声の質問に対して、わざわざ異性を選択するのです。
女性の声のOSが立ち上がると、彼は何よりもまず彼女に名前を求めます。AI もといOSとしてではなく、具体度の高い存在になることを要求したのです。女性の人格との関係を言語で構築するシーケンスです。
そしてその「関係性」は以降も不断に言語で肉付けされてゆきます。互いのことを語り、理解し合い、そして肉体不在の肉体関係さえも言語を介して達成するのです。ときに音楽やイラストレーションという具体が用いられることもありましたが、それは全体のほんのわずかに過ぎません。
she ではなくher:主格ではなく目的格
ふたりは「言葉」で「関係」する。そう考えてふと立ち返ってみると、この映画のタイトルが『her』であることに気づきます。
『She』や『Samantha』ではなく『her』なのです。 “her” は “She” の所有格・目的格の両方を兼ねていますが、ここでは「彼女の」という所有格ではなく、「彼女」という目的格の意味で使われていると考えるのが妥当でしょう。繰り返します。この映画のタイトルは主格ではなく、固有名詞でもなく、目的格なのです。
例① She’s an operating system. (主格のshe)
→文中に登場するのはShe の1人のみ
例② Am I falling in love with her? (目的格のher)
→文中には I とher の2人が登場する
目的格は、主語と動詞が無ければ発生することはありません。 “I” がなければ……なんて言うと肌寒いダジャレになってしまいますが、herという目的格を使いたければ、her に「関係」するher 以外の人やモノが主格になる必要があります。
herという「言葉」は、関係することを前提にした単語であり、主格との関係そのものを端的に一言で表す三文字だと断言してもよいでしょう。この映画での主格は当然セオドア。her というタイトルにはTheodore という省略された主格が隠れているのです。
慣れないのにちょこざく文法の話なんかして眠たくなってきました。結論を急ぎます。セオドアとサマンサの関係は、セオドアが主体的に規定する相対的な関係なのです。彼女そのものではなく、「彼女との関係」に焦点が当たっているのです。セオドアが知覚・認識する異性との関係性が主題だったのだ、と筆者は考えます。
そしてもちろん、その関係は言語で構築されます。この前提を踏まえてあの「642人」のシーンに話を戻しましょう。ふたりを結び付けていた愛は「言語によってかたどられた関係性」だったからこそ、サマンサが言語化不可能な抽象の存在になった途端にその関係の一切が壊れてしまうのです。
わからない=言語で理解できない、というのは「関係できない」と等しい。だからサマンサが具体を超越した抽象概念になったとき、彼らは交際を解消したのです。
セオドアの心の穴を埋めるのもまた……
世界は言語でできていて、他者との関係もまた言語でできている。そんな世界のルールにきわめて忠実な男、セオドア。彼の有する「関係」は、ほとんどすべて失われてしまいます。そんな逆境において、彼が何をしたのかを思い出して欲しいのです。
妻との別居と離婚、機械と恋愛してもよいのかという葛藤、そしてサマンサとの別れ。すべてを終えて、さらに前に進もうとしたセオドアは筆をとります。元妻に手紙を書いたのです。
その手紙が元妻キャサリンに読まれたのかどうかは作中で明かされることはありません。けだしそれは重要ではないのでしょう。自分と向き合い、状況を整理して感情を言語化する行為に意味があったのです。元妻との関係は、ここではじめて本質的なピリオドを迎える。離婚届のサインではなく、関係を言語化した瞬間にはじめて関係に決着がつく。ここで彼はようやく新たな一歩を踏み出したのだ。自分の言葉で自分を救済したのです。
ここまで自分の手で原稿を書いて、ようやく僕はひとつの仮説にたどり着く。きっとこの映画は、「言葉の代理人」だったセオドアが、自分の言葉をつかって自分を見つけるまでの物語だったのです。
なるほど、それなら合点がいく。長々と6,000字もかかったけれど、この記事を自分で書けてよかった。
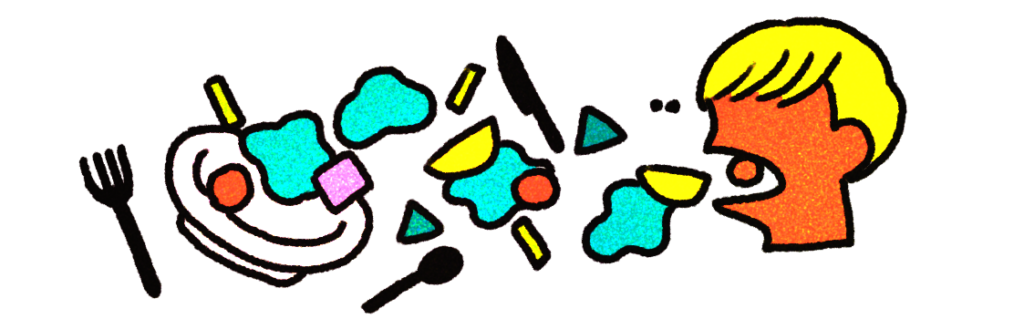
文・川合裕之(フラスコ飯店 店主)
編集・安尾日向

特集・映画『her』① |
「声」に「触れる」ことで確信する、サマンサの実在:メディア論的考察

特集・映画『her』② |
愛情とテクノロジーのギャップを乗り越えるのは、自己陶酔だ
>> この映画をAmazon Prime で見る <<

